ここ数年、一緒に登山をするようになった同級生から勧められた本である。
著者は山岳ガイドで2014年9月27日正午頃の御嶽山噴火(実際には水蒸気噴火)に偶然に遭遇した方である。その時はガイドの仕事ではなく、単独で、後日、御嶽山に一緒に登るお客さんのために下見に来ていた。著者はこの噴火で63名の方が亡くなり、そこから得られる教訓を伝えようと本書を執筆した。活字よりは直接の方が、思いが伝わると考え、数多くの講演もこなされている。
第一章は、著者はじめ、御嶽山の噴火口の周辺にいて生還した人の時系列での行動を記している。迫真の行動録である。一口に御嶽山頂上と言っても、剣ヶ峰、お鉢、八丁ダルミ、王滝山頂、地獄谷など色々な名称がついており、地形や隠れ場所も様々である。火口は地獄谷に開き、著者は外輪を挟んでその反対側のお鉢にいた。第二章は御嶽山に関する事項をまとめている。第二章の前半は、過去の噴火(1979年、1991年、2007年)の様子、2014年9月での山頂周辺の各所での死者の分布、御嶽山の登山の手段(ロープウェイで2150mまで一気に行ける)に対する考察などである。便利な交通手段があり短時間での登山が可能であることは、高所順応としては疑問で、装備も簡易になり易く、登山に相応しいことか疑わしいと著者は思っているようだ。第二章後半は、予知の可能性、今回の噴火の前兆や学術的な報告書からわかる噴火の3つのフェーズの説明などである。第三章は「噴火の爪痕」と題し、捜索活動の困難さ、著者が取材で答えたことと報道内容のずれ、生存者の自責の念への思い、そして遺族とのやり取りなどが記されている。著者は報道ではかなり手痛い目に遭っているようで、顔と名前を出して取材を受けることは、登山と同じくらいのリスク管理が要ると言っている。取材する方も、困難な中で助け合う遭難者たち、などのような期待する筋書きを持っており、どう発言してもそれが筋書きに沿ったものとして歪められてしまう。一方で肝心の教訓は伝えられない。少し長いがその理由を下記に引用する。
報道は噴火や捜索などの状況を伝えるのは得意だが、災害の教訓を伝えるのは得意ではない。なぜなら感情に流され本質を知ろうとしない無責任な世間の声を大事に思えば、当然、言ってよいこと、言わない方がよいこと、言ってはいけないことが出て来るからである。たいていは言ってはいけないことが教訓の核心ではないかと思う。その教訓の核心は、災害で犠牲になった方の行動を非難しているように捉えられかねないからだ。残念ながら教訓は結果からしかわからない。登山者が何をすべきだったかたは、命を落とした登山者を非難していると捉えられるから、報道では語られない。その代わり警戒レベルを据え置いた気象庁、活火山だと周知しなかった行政などが非難される(171頁、評者要約)。
私(著者)は生死を分けたものは運だけではなく、噴煙を見てからどれだけ早く危険だと判断、行動できるたかだと言っている。この言葉は遺族の心中を考えると・・・「命を落とした自分の家族には危機に対する意識が足りなかった」と聞こえるだろう(205頁)。
第四章が「噴火の教訓」でありここが本書の核心である。
私(著者)は運が良かったと会う人から散々言われ違和感があった。噴火に遭うなんて、それだけで相当運が悪いことを忘れていないだろうか(212頁)。
登山関係者は決して「運がよかった」などとは言わないそうだ。もし、著者に「運」があるとすればそれは自分で掴んだものである。
噴煙を認識してから山頂各所は噴煙に包まれ、真っ暗になった。そこに火山礫(噴石)が飛んでくる。この噴火の死者の殆どは噴石に当たり身体を損傷した方たちである(63名中56名の死因となっている)。著者が注目するのは、山頂各所でも避難できる小屋等の施設があり、視界が利かなくなるまでの時間が60秒と比較的長かった剣ヶ峰で死者が最も多い点である(著者の居たお鉢は真っ暗にはならなかったが、噴火から20秒ほどで火山性ガスが立ち込めて視界がかなり悪くなった)。それでも、剣ヶ峰の死者は63名中32名と約半数も占める。
剣ヶ峰には登山者が多く、何が起きたかわからず、周りが写真を撮っているし、逃げないから大丈夫と思ったのではないか。むしろ「逃げなかったのではなく、逃げられなかった」のではないだろうか。逃げ遅れの心理と集団心理である(227頁)。
世間では御嶽山の噴火の対策として登山時のヘルメット着用の推奨、そしてシェルターの建設が行われた。だが著者は、これらは安心材料にすぎず安全を保証するものではないと言っている。結局は初動に遅れては、シェルターは役立たない。噴石のサイズによってはヘルメットなどあっけなく割れてしまう。
登山者が正常性バイアスにならずに「スイッチ」を入れ替え、即座にそれぞれが自分の命を守る行動に徹したとき、初めてシェルターなどの噴石を遮れるものがあれば生き残る可能性が高くなり、予知できない噴火を最小限の被害で食い止める減災が出来るのではないかと思う。これが、この先に繋がる教訓ではないかと考える(230頁)。
もちろん運もある。著者からすると生死の分かれ目は噴火したときに山頂各所のどこに居たかであり、本書を読めば、隠れる場所もない八丁ダルミに居た人は運が悪い筈で、避難場所があった剣ヶ峰周辺に居た人はむしろ運が良いということになる筈だが、剣が峰周辺の死者が最も多い。
本書は著者が噴火に遭った直後にまとめたメモや生存者、遺族から入手した写真などを元に噴火から2年経った2016年夏に執筆されたものである。文庫版には増補として第五章がある。噴火後10年経った2024年に書かれた。御嶽山の登山の規制解除、著者の講演会の様子、社会や自分の変化などが書かれている。
著者もいう通り、登山は自己責任である。ガイドがいても、出来ることは限られているし、ガイドも危機意識がない登山者を案内したくないだろう。著者も噴火など想定して登った訳でもないし、噴火が起きたらどうすべきか、などは知らない。しかし、噴煙を目にしてすぐに自分の命を守る行動に移っている。それはガイドとしての長年の登山経験が役立ったのだろう。つまりは、それ相応の覚悟がなければ危険な山になど行ってはいけないということになる。教訓を言い立てると亡くなった方たちはそれを守れなかった人たちだと非難しているとも捉えかねないが、至る所で亡くなった方に気を使いながらも、著者は臆せず登山で死なないための教訓を書いている。
この噴火も多くの災害と共通で、著者が最も恐れるのは風化である。本書の執筆の動機も風化を防止したいということだろう。登山と観光の境目も曖昧になってきており、どちらも楽しみのためにすることではあるが、自分も風化に流されず、山に登るときは浮かれずに著者の教訓をしっかり心に刻んで山に登りたい。







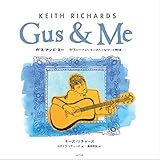


この書評へのコメント