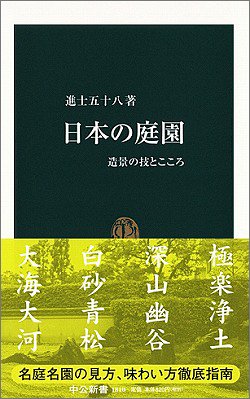休蔵さん
レビュアー:
▼
ぼんやり眺めるだけで楽しめる日本庭園も、基礎的な知識を有していると楽しみ方は多層となるはず。本書は、庭園についての基礎的な知識を得るにはもってこいの1冊。
日本各地に様々な庭園が存在する。
ぼんやり眺めるもよし、水のせせらぎを聞くもよし、風を肌に感じるもよし。
庭園の楽しみ方は人それぞれだろう。
眺め方も建物に座す場合もあれば、散策しながらの場合もあろう。
四季の変化を楽しむこともある。
ふんわり飛んでくる鳥も、庭園に彩りを添える。
ふらりと訪れても十分楽しめるのが庭園の良さではあるが、一定の知識を持つことで、その楽しみ方は重層化するに違いない。
本書は、そんな期待に応える1冊だ。
本書は大きく3つの章からなる。
第1章は「神仏の庭と人間のにわ」で、各時代の庭園の特徴を簡潔にまとめている。
飛鳥・奈良時代の発掘調査事例や神社の磐座から始まり、昭和時代の芸術的庭園まで順を追っている。
第2章は「日本庭園の技術とこころ」で、庭園を構成する要素の各論である。
日本庭園は自然を取り込んだり、再現したりすることを旨とする。
植栽術、水工法、土の造形など、庭園の基本となる構成要素の意味を解説してくれて、庭園を散策する際に参考になる情報が満載である。
現代人は新しいものに目が奪われがちとする。
加えて、「時間の積み重なりの味わい=歴史の美」を楽しむことができるのも人間という。
「庭園文化」は、時間とともに生長・変化・成熟する「空間文化」で、それを十二分に味わうためには、最低限の知識が必要で、本章が示す情報は重要なものと感じた。
第3章は「日本の名庭三十六景」で、36か所の庭園を紹介している。
個人的には4か所しか行ったことがなかった・・・
なんとまあ恥ずかしいこと。
せっかく日本国内に優美な庭園が数多く保護されているのに、ほとんど行ったことがないなんて。
世界の庭園の歴史を著者はざっくりと示している。
すなわち、国王や皇帝のための閉じられた「私庭園」(ガーデン)から、一般市民のための開かれた「公園」(パブリック・パーク)と変遷し、さらに「緑の都市」(アメニティ・タウン)作りを目指す「ランドスケープ・アーキテクチュア」へと展開したという。
そして、「ガーデニング」から「ファーミング」への展開が予測された。
庭園に対して求めるものは時代・社会に応じて変化し、それは取りも直さず人の心の変化であると言えよう。
庭園の研究は、人の心の研究に通ずることなのかもしれない。
そんなことはともかく、庭は良い。
何も考えず、ぼんやり過ごせるところが特に良い。
特に人があまり訪れない、公開してる文化財庭園は、非常に良い。
知識があると庭園への楽しみ方は重層化するが、何の知識がなくても楽しめるのが庭園の良さだ。
でも、知識はあっても邪魔にはならない。
本書は、そんな邪魔にならない知識をそっと仕込ませてくれる良書である。
ぼんやり眺めるもよし、水のせせらぎを聞くもよし、風を肌に感じるもよし。
庭園の楽しみ方は人それぞれだろう。
眺め方も建物に座す場合もあれば、散策しながらの場合もあろう。
四季の変化を楽しむこともある。
ふんわり飛んでくる鳥も、庭園に彩りを添える。
ふらりと訪れても十分楽しめるのが庭園の良さではあるが、一定の知識を持つことで、その楽しみ方は重層化するに違いない。
本書は、そんな期待に応える1冊だ。
本書は大きく3つの章からなる。
第1章は「神仏の庭と人間のにわ」で、各時代の庭園の特徴を簡潔にまとめている。
飛鳥・奈良時代の発掘調査事例や神社の磐座から始まり、昭和時代の芸術的庭園まで順を追っている。
第2章は「日本庭園の技術とこころ」で、庭園を構成する要素の各論である。
日本庭園は自然を取り込んだり、再現したりすることを旨とする。
植栽術、水工法、土の造形など、庭園の基本となる構成要素の意味を解説してくれて、庭園を散策する際に参考になる情報が満載である。
現代人は新しいものに目が奪われがちとする。
加えて、「時間の積み重なりの味わい=歴史の美」を楽しむことができるのも人間という。
「庭園文化」は、時間とともに生長・変化・成熟する「空間文化」で、それを十二分に味わうためには、最低限の知識が必要で、本章が示す情報は重要なものと感じた。
第3章は「日本の名庭三十六景」で、36か所の庭園を紹介している。
個人的には4か所しか行ったことがなかった・・・
なんとまあ恥ずかしいこと。
せっかく日本国内に優美な庭園が数多く保護されているのに、ほとんど行ったことがないなんて。
世界の庭園の歴史を著者はざっくりと示している。
すなわち、国王や皇帝のための閉じられた「私庭園」(ガーデン)から、一般市民のための開かれた「公園」(パブリック・パーク)と変遷し、さらに「緑の都市」(アメニティ・タウン)作りを目指す「ランドスケープ・アーキテクチュア」へと展開したという。
そして、「ガーデニング」から「ファーミング」への展開が予測された。
庭園に対して求めるものは時代・社会に応じて変化し、それは取りも直さず人の心の変化であると言えよう。
庭園の研究は、人の心の研究に通ずることなのかもしれない。
そんなことはともかく、庭は良い。
何も考えず、ぼんやり過ごせるところが特に良い。
特に人があまり訪れない、公開してる文化財庭園は、非常に良い。
知識があると庭園への楽しみ方は重層化するが、何の知識がなくても楽しめるのが庭園の良さだ。
でも、知識はあっても邪魔にはならない。
本書は、そんな邪魔にならない知識をそっと仕込ませてくれる良書である。
お気に入り度:







掲載日:
外部ブログURLが設定されていません
投票する
投票するには、ログインしてください。
ここに参加するようになって、読書の幅が広がったように思います。
それでも、まだ偏り気味。
いろんな人の書評を参考に、もっと幅広い読書を楽しみたい!
書評一覧を取得中。。。
- 出版社:
- ページ数:288
- ISBN:9784121018106
- 発売日:2005年08月26日
- 価格:861円
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。