運命の足音





宗教とは、運命を受け入れ、赦すことなのか――。一枚の写真から始まる作家の人生エッセー。
わたしがあまりにも世間知らずで、ものを知らないので、家内がこれを読んで少しは人の心の在りようというも…

本が好き! 1級
書評数:91 件
得票数:1565 票
後期高齢者です。頭のリハビリも兼ねて、ときどき英語をかじるようにしています。各国著名人による英語の名言(拙訳つき)に興味のある方は、下記のブログ(ameblo)へどうぞ。
どちらかと言えば作品そのものより、他の書評家or読書家が書いた文章のほうに興味を惹かれるタイプです。ただし、他人のコメントや重箱の隅をつついて優越感に浸るような、さもしい根性の高齢者にだけはなりたくないと思っています。





宗教とは、運命を受け入れ、赦すことなのか――。一枚の写真から始まる作家の人生エッセー。
わたしがあまりにも世間知らずで、ものを知らないので、家内がこれを読んで少しは人の心の在りようというも…





人とは真逆の角度から人生を眺め、新天地への地平をクリアした元警察官。
このシリーズ、初めて出た『交通誘導員ヨレヨレ日記』がもつ書影のインパクトに釣られて読み始めたのだが、…






先物嫌いを自称するわたしといえども、手に取らざるを得ない本であった。
めったに本屋に行かないわたしが、本屋へ行くと言うと珍しく、家内が「好きな本があったら、買っていいよ。…
![]()





「近代」とやらはなぜ、そんなにも「超克」せねばならぬものとなってしまうのか。
まことにお恥ずかしいことながら、評者は「批評」というもの、あるいは「評論」といわれるものを読んだこと…
![]()




人生の主役である自分に忠実であること。迷ったら「やめる」のが鉄則。
本書の著者は「心理カウンセラー」ということである。 それだけあって、内容のほとんどはSNS利用上の…
![]()




平安王朝の御代、必ずしも優雅ならず。庶民の目から見た世界も御覧じろかし。
平安京の世界――といえば、一般的には優雅な女人たちが楚々とした振る舞いで立ち出でる姿などが思い至るで…
![]()





貯金なし、年金少なし、資産ゼロのナイナイ尽くし身のにはちとシンドイ読み物か
あれは、20年ほど前だったか。とある経済評論家が著書で、「年収300万円時代が来る!」と予言したとき…
![]()





自分がいちばん恐れている物事をやってみなさい。そうすれば恐怖心は跡形もなく消える
基本的にわたしはへそ曲がりな性格のせいか、いわゆる「ハウツー本」というものを読んだことがない。いや、…
![]()





徐々に解き明かされてゆく謎のソシオメトリー
帯の謳い文句に、確かあのジェフリー・ディーヴァーが絶賛したとあったので、随分期待していた。……と、過…
![]()




日本の長期政権とは、およそケタが違い過ぎるスケールの壮大さに身の毛がよだった、歴史音痴の評者であった。
タイトルは見てのとおり、『ヒッタイトに魅せられて』である。だが、副題に「考古学者に漫画家が質問!」と…
![]()






自分の似姿を見るような気がする、ある意味、痛ましい書である。はたして希望はあるか。
なんとも凄い本を読んだ。いや、まだ読んでいるといっていい。というのも、気持ちの上では読んでしまったと…
![]()



コラボ狩りを通じて描かれる人間模様に悲しみを見るのか、それとも……。
単刀直入に言おう。正直にいうと、この本はとても読みにくかった。 というのも、日本語の文が何度読んで…
![]()




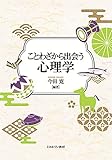
「重要なのは親じゃない、仲間である」とハリスは言いきった。
この度、幸運に恵まれたのは、ミネルヴァ書房さんの『ことわざから出会う心理学』だ。書名からも推し量れる…
![]()




サイエンスコミュニケーションとは、そっくりそのままわたしたちレビュアーにも当てはまる行動指針そのものなのだ。
桝太一さんといえば、テレビでよく見るアナウンサーである。 評者は「真相報道 バンキシャ!」(家内が…





いくら悪人だからって、殺していいってことにはならない。どんな理屈を並べ立てたって、人殺しが正当化できるわけじゃない。たとえ「愛の名において」であっても……。
あれは、何十年前のことになるかしら……。 そう、かれこれ70年以上も前のことになるかしらね。昭和も…






キングは読者の想像ならぬ、創造力に任せてくれる。この話の先は、あなた自身が綴るのだ。
あれは、何年前だったろう。邦題が『ショーシャンクの空の下』(?)だったかの映画をテレビで観て、いたく…
![]()





ニホンジンの耳っておもしろい! なんてったって、自然の音がひとのことばに聴こえてしまうのだから……。
この本は、表向きは確かに「絵本」であって、子どもの喜びそうな絵柄がふんだんに載っている。帯には、 オ…
![]()





実社会での営業ノウハウや対人スキルにも、そしてトレーナーの研修用教材としても使用しうる力量のある本である。
単純に面白かったというに尽きる。と、そういえば小学生の作文かといわれそうだが、いわゆるライトノベルと…
![]()






大切なのは、なにかの到来を「待つ」のではなく、情況を「選び取る」ということなのだ。そこにこそ自由はある。
この本を読み始めたころ、わたしはある本を思い描いていた。 それは、1997年に読んだスティーブン・…




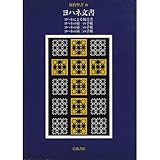
言葉足らずであればこそ、想像力は働き、そこに深い感銘が蓄えられるのである。
In the beginning was the Word, and the Word was to…