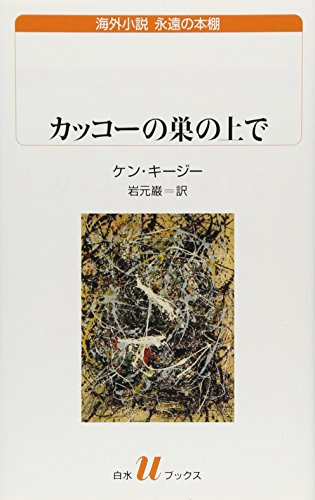darklyさん
レビュアー:
▼
尾崎豊ではないが、支配からの卒業というテーマは時代が変わろうとも姿カタチを変え生き続けるのだろう。
この作品は元々映画を観たことがあり、もちろん名作と言われるだけあってとても印象深い作品でした。ジャック・ニコルソンの演技ももちろん素晴らしかったですが、それにもまして婦長役のルイーズ・フレッチャーも素晴らしい。ただ終わり方が唐突である印象があり何かモヤモヤとしたものが残っていましたが小説を読みその疑問が氷解しました。
この小説の主人公は精神病患者かつネイティブアメリカンのブロムデンであり、その視点で書かれた作品です。ですのでそれを前提として映画を観れば終わり方が理解できます。なんの情報もなく映画を観ると主人公は明らかにマックマーフィー(ジャック・ニコルソン)であり、その流れで観ていくと終わり方がよくわからないのです。これはもちろん映画監督の策略なのでしょう。賛否両論ありそうですが私はそれを差し引いても素晴らしい映画だと思います。
刑務所労働を逃れるため精神病のふりをして精神病院に入ったマックマーフィーは、支配され抑圧された入院患者たちに驚き、皆が人間らしい入院生活ができるように支配者であるラチェッド婦長と戦う。マックマーフィーは人格者でも人権派弁護士でもない、単なる荒くれ者だが不当な仕打ちに対しては徹底抗戦するいわば自己肯定感の塊のような男だ。もちろん彼は普通の人間であり体制側に迎合するのが得策という考えも頭によぎったりもするが。
彼に影響され次第に人間性を回復する入院患者たち、微笑を浮かべあの手この手を使いながら自らのマウントボジションを死守しようとする婦長及び病院。治療と称した拷問にも全く屈せず病院は次第にマックマーフィーのペースになっていくが彼が企てた乱痴気騒ぎの果ての悲劇により我を失ったマックマーフィーはついに婦長に襲い掛かる。
精神科の歴史はよく知りませんが、現在でもよく分かっていない人間の精神を扱うだけにその治療法は実験的で荒っぽく今の価値観からすれば非人道的であったことが推測できます。作者は精神科病棟の勤務経験があり当時よく知られていなかった精神病院というものの実態を明らかにするといった意図もあったのだろうと思います。
さらに人間社会においてよく見られる現象、手段の目的化も一つのテーマではないかと思います。当初は患者のためとして行われる治療や規則という手段が次第にそれを維持することが目的となり治療や規則は懲罰や秩序維持という色彩を帯びてきます。なぜそうなるのか?それは婦長にとって患者は一人一人の「人間」ではなく、管理するべき「モノ」となってしまっているからです。
医者はそうはいっても患者を人間として見る人が多数だろうと思います。しかし数十年に渡り牢名主のように君臨する婦長にとって大事なのは管理と秩序維持なのです。どこの会社にもいると思います。ある狭い分野での経験が長く蛸壺の中で自分の権益を守ろうと情報を遮断するお局さんやおじさんが。このような意味でマックマーフィーが戦うべき相手は医者ではなく婦長としたところが秀逸です。
今でこそ精神科も進歩し非人道的な行為は行われないようになったと思われますが現代ではまたそれは別の問題となって現れてきています。それは高齢者施設における虐待やいじめです。これも高齢者を一人の人間として見ていないために発生するものであり、ナチスを始めこのような例は枚挙に暇がないと思われます。
ホットな話題で言えばコロナ肺炎での議論では、少しでも体調が悪ければ病院で検査してほしい(するべき)という立場の人と医療体制に限界があるのだから軽症の人は病院に行かず自宅で様子をみるべきという立場の人がいます。後者はある意味人を「モノ」と見ているフシがあります。「モノ」という言い方が乱暴であるならば「種」や「多数」を救う派とで言いますか。一見後者のほうが理があるように思えますが、それは単に死亡率が低いだけのことでこれが致死率50%であればそう物事は単純ではない。これは「白い巨塔」の里見助教授と財前教授の対立にも見られます。「人」対「種」「多数」「効率」。
話が逸れましたが婦長を敵役としたと同時に秀逸なのが主人公をネイティブアメリカンとしたところです。ブロムデンは社会的差別の中で精神を患いひたすら自分を殺して日々をやり過ごしていましたが、患者の中でもマックマーフィーから最も大きく影響を受け、自分の人間としての尊厳を取り戻すわけですが、それは精神病院という檻それはある意味安きに流れる自分を守ってくれるという部分もあるものですがそこを離れ、アメリカ社会におけるネイティブアメリカンという位置づけに立ち向かっていく覚悟ができたということなのでしょう。
ブロムデンの存在は精神病の症状があっても普通に生活できなくはない人間が精神病を装わざるを得ないアメリカの社会状況へのアンチテーゼなのでしょう。さらに病院内でも聾唖を装わざるを得ない。正に社会構図が入れ子状態になっているのです。
映画では誰もが無理だという中でマックマーフィーは水飲み台(小説ではコントロールパネル)を持ち上げようとします。結局持ち上げられなかったわけですが、彼は「とにかくおれはチャレンジしたのだ」と言います。彼から彼の精神を受け継いだブロムデンが映画の最後水飲み台を持ち上げて窓を割り荒野を走っていく場面がとても印象です。まあとにかく小説と映画どちらも素晴らしいです。
この小説の主人公は精神病患者かつネイティブアメリカンのブロムデンであり、その視点で書かれた作品です。ですのでそれを前提として映画を観れば終わり方が理解できます。なんの情報もなく映画を観ると主人公は明らかにマックマーフィー(ジャック・ニコルソン)であり、その流れで観ていくと終わり方がよくわからないのです。これはもちろん映画監督の策略なのでしょう。賛否両論ありそうですが私はそれを差し引いても素晴らしい映画だと思います。
刑務所労働を逃れるため精神病のふりをして精神病院に入ったマックマーフィーは、支配され抑圧された入院患者たちに驚き、皆が人間らしい入院生活ができるように支配者であるラチェッド婦長と戦う。マックマーフィーは人格者でも人権派弁護士でもない、単なる荒くれ者だが不当な仕打ちに対しては徹底抗戦するいわば自己肯定感の塊のような男だ。もちろん彼は普通の人間であり体制側に迎合するのが得策という考えも頭によぎったりもするが。
彼に影響され次第に人間性を回復する入院患者たち、微笑を浮かべあの手この手を使いながら自らのマウントボジションを死守しようとする婦長及び病院。治療と称した拷問にも全く屈せず病院は次第にマックマーフィーのペースになっていくが彼が企てた乱痴気騒ぎの果ての悲劇により我を失ったマックマーフィーはついに婦長に襲い掛かる。
精神科の歴史はよく知りませんが、現在でもよく分かっていない人間の精神を扱うだけにその治療法は実験的で荒っぽく今の価値観からすれば非人道的であったことが推測できます。作者は精神科病棟の勤務経験があり当時よく知られていなかった精神病院というものの実態を明らかにするといった意図もあったのだろうと思います。
さらに人間社会においてよく見られる現象、手段の目的化も一つのテーマではないかと思います。当初は患者のためとして行われる治療や規則という手段が次第にそれを維持することが目的となり治療や規則は懲罰や秩序維持という色彩を帯びてきます。なぜそうなるのか?それは婦長にとって患者は一人一人の「人間」ではなく、管理するべき「モノ」となってしまっているからです。
医者はそうはいっても患者を人間として見る人が多数だろうと思います。しかし数十年に渡り牢名主のように君臨する婦長にとって大事なのは管理と秩序維持なのです。どこの会社にもいると思います。ある狭い分野での経験が長く蛸壺の中で自分の権益を守ろうと情報を遮断するお局さんやおじさんが。このような意味でマックマーフィーが戦うべき相手は医者ではなく婦長としたところが秀逸です。
今でこそ精神科も進歩し非人道的な行為は行われないようになったと思われますが現代ではまたそれは別の問題となって現れてきています。それは高齢者施設における虐待やいじめです。これも高齢者を一人の人間として見ていないために発生するものであり、ナチスを始めこのような例は枚挙に暇がないと思われます。
ホットな話題で言えばコロナ肺炎での議論では、少しでも体調が悪ければ病院で検査してほしい(するべき)という立場の人と医療体制に限界があるのだから軽症の人は病院に行かず自宅で様子をみるべきという立場の人がいます。後者はある意味人を「モノ」と見ているフシがあります。「モノ」という言い方が乱暴であるならば「種」や「多数」を救う派とで言いますか。一見後者のほうが理があるように思えますが、それは単に死亡率が低いだけのことでこれが致死率50%であればそう物事は単純ではない。これは「白い巨塔」の里見助教授と財前教授の対立にも見られます。「人」対「種」「多数」「効率」。
話が逸れましたが婦長を敵役としたと同時に秀逸なのが主人公をネイティブアメリカンとしたところです。ブロムデンは社会的差別の中で精神を患いひたすら自分を殺して日々をやり過ごしていましたが、患者の中でもマックマーフィーから最も大きく影響を受け、自分の人間としての尊厳を取り戻すわけですが、それは精神病院という檻それはある意味安きに流れる自分を守ってくれるという部分もあるものですがそこを離れ、アメリカ社会におけるネイティブアメリカンという位置づけに立ち向かっていく覚悟ができたということなのでしょう。
ブロムデンの存在は精神病の症状があっても普通に生活できなくはない人間が精神病を装わざるを得ないアメリカの社会状況へのアンチテーゼなのでしょう。さらに病院内でも聾唖を装わざるを得ない。正に社会構図が入れ子状態になっているのです。
映画では誰もが無理だという中でマックマーフィーは水飲み台(小説ではコントロールパネル)を持ち上げようとします。結局持ち上げられなかったわけですが、彼は「とにかくおれはチャレンジしたのだ」と言います。彼から彼の精神を受け継いだブロムデンが映画の最後水飲み台を持ち上げて窓を割り荒野を走っていく場面がとても印象です。まあとにかく小説と映画どちらも素晴らしいです。
お気に入り度:









掲載日:
外部ブログURLが設定されていません
投票する
投票するには、ログインしてください。
昔からずっと本は読み続けてます。フィクション・ノンフィクション問わず、あまりこだわりなく読んでます。フィクションはSF・ホラー・ファンタジーが比較的多いです。あと科学・数学・思想的な本を好みます。
この書評へのコメント
- Yasuhiro2020-03-31 15:14
懐かしいですね。題名の件ですがちょっと痛い思い出があります。大学の英語の授業でこの映画の題名が話題に上がり、私が映画雑誌の受け売りで「the cuckoo's nest」は「精神病棟」の隠語ですと発言したところ、とても真面目な先生がそんなスラングは聞いたことがない、それが書いてある辞書をぜひ見せてくれと言われてしまいました。それからいろいろ探したんですが結局どんな辞書にもみつからないままでした。以来謎のままでしたが、darklyさんのコメを見て何十年かぶりにちょっと溜飲が下がりました(w。
クリックすると、GOOD!と言っているユーザーの一覧を表示します。 
コメントするには、ログインしてください。
書評一覧を取得中。。。
- 出版社:白水社
- ページ数:518
- ISBN:9784560071922
- 発売日:2014年07月08日
- 価格:2160円
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。