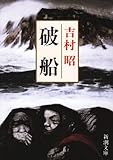紅い芥子粒さん
レビュアー:
▼
ついに”お船様”が来た。殺し、盗み、盗品を公平に分配し、貧しい村は、よろこびに沸いた。
どこであるか、地名は書かれていない。
江戸時代、日本列島のどこかの半島の先、海沿いの村の物語である。
戸数は、わずか17戸。
海に突き出た岬の断崖で、南を閉ざされている。
村の前にひろがる海には岩礁が多い。豊かな漁場だが、船が近づけば破船する。
北には険しい山が迫り、耕せる土地はごくわずか。穀物の自給はできない。
隣の村との往来には、険しい山道を歩いて、三日もかかる。
そんな村の人々が、待ち望んでいるものがある。
それが、”お船様”。
岩礁の多い海で、破船した船のことだ。
商船なら、多くの荷を積んでいる。
米や、油や、砂糖や、美しい布や……、村にはないものばかりだ。
”お船様”が到来すると、村のひとたちは、船乗りたちを殺し、積み荷を盗む。
船を完全に破壊し、木材を燃料や家屋の修理に使う。
恐ろしい犯罪だが、村びとたちに罪の意識はない。
”お船様”は、一時的にせよ、村びとたちを貧窮から救ってくれる。
”お船様”は、海の神様のめぐみだ。
村には、”お船様”を招くための神事さえある。
”お船様”を岩礁の海に呼び込むために、あえて船が遭難しそうな夜に塩を焼く。
物語の主人公は、九歳の少年、伊作である。
父母と、弟、二人の妹の六人家族。下の妹は、生まれたばかりの赤ん坊である。
父親は、隣の村の廻船問屋に舟子として年季奉公に行っている。
家族を飢えから救うために、三年の年季で自分の身を売ったのである。
伊作がものごころついてから、”お船様”の到来はない。
”お船様”さえ来てくれていれば、父親は身を売らずにすんだのである。
物語は、父親が不在だった三年間のできごとである。
伊作はまだ子どもだが、一人前の男として、漁に出て家族を養う。
母親は、伊作を殴って労働に駆り立てる。
その母親も、力仕事を担う。伊作がまだ非力だから。
あかんぼうの妹の、あっけない死。
一つ年上の少女への淡い思い。
村の女子には、ふたつの道がある。
となりの村へ身売りするか、村の男の妻になり、男の家の労働力になるか。
自分の道を自分で決めることはできない。
親が決めるのだが、”お船様”が来れば、身売りは避けられるかもしれない。
そして、ついに”お船様”が来た。
殺し、盗み、盗品を公平に分配し、よろこびに沸く村。
翌年も”お船様”は来た。
その船は、破船ではなく流れ船だった。
船の人は、殺さなくても、すでに死んでいた。
荷は積んでいなかった。
村びとたちは、死人が来ていた赤い着物を剥いで、分配した。
かれらが見たこともない美しく柔らかい布だった。
そのあと、村に恐ろしい病が広がる。天然痘…… 閉ざされた村では、経験したことのない病だった。物語は、想像を絶する悲惨な結末を迎える。
まるで、辺境の村の民俗誌を文学に昇華したような小説だった。
性別不明の村おさは、神の声を聞く予言者で、村おさを支える村のリーダーは経験を積んだ男である。それは、古代の姫彦制を思わせる。
おそらく遠い昔に海から流れ着いた人たちの子孫なのだろう。
死ねば魂は海に還り、また村の女の胎内に戻ってくるという信仰がある。
男女のまぐわいは、そのための儀式とされる。
村のひとたちは、貧しく平等で、富は公平に分配される。
村おさの指示は神の声だから、絶対である。
個我を主張する者はなく、村にいさかいはない。
原始共産制とは、こういう社会をいうのかと思った。
ごくまれに、搾取と懲罰のために訪れる藩の役人の存在さえなければ。
江戸時代、日本列島のどこかの半島の先、海沿いの村の物語である。
戸数は、わずか17戸。
海に突き出た岬の断崖で、南を閉ざされている。
村の前にひろがる海には岩礁が多い。豊かな漁場だが、船が近づけば破船する。
北には険しい山が迫り、耕せる土地はごくわずか。穀物の自給はできない。
隣の村との往来には、険しい山道を歩いて、三日もかかる。
そんな村の人々が、待ち望んでいるものがある。
それが、”お船様”。
岩礁の多い海で、破船した船のことだ。
商船なら、多くの荷を積んでいる。
米や、油や、砂糖や、美しい布や……、村にはないものばかりだ。
”お船様”が到来すると、村のひとたちは、船乗りたちを殺し、積み荷を盗む。
船を完全に破壊し、木材を燃料や家屋の修理に使う。
恐ろしい犯罪だが、村びとたちに罪の意識はない。
”お船様”は、一時的にせよ、村びとたちを貧窮から救ってくれる。
”お船様”は、海の神様のめぐみだ。
村には、”お船様”を招くための神事さえある。
”お船様”を岩礁の海に呼び込むために、あえて船が遭難しそうな夜に塩を焼く。
物語の主人公は、九歳の少年、伊作である。
父母と、弟、二人の妹の六人家族。下の妹は、生まれたばかりの赤ん坊である。
父親は、隣の村の廻船問屋に舟子として年季奉公に行っている。
家族を飢えから救うために、三年の年季で自分の身を売ったのである。
伊作がものごころついてから、”お船様”の到来はない。
”お船様”さえ来てくれていれば、父親は身を売らずにすんだのである。
物語は、父親が不在だった三年間のできごとである。
伊作はまだ子どもだが、一人前の男として、漁に出て家族を養う。
母親は、伊作を殴って労働に駆り立てる。
その母親も、力仕事を担う。伊作がまだ非力だから。
あかんぼうの妹の、あっけない死。
一つ年上の少女への淡い思い。
村の女子には、ふたつの道がある。
となりの村へ身売りするか、村の男の妻になり、男の家の労働力になるか。
自分の道を自分で決めることはできない。
親が決めるのだが、”お船様”が来れば、身売りは避けられるかもしれない。
そして、ついに”お船様”が来た。
殺し、盗み、盗品を公平に分配し、よろこびに沸く村。
翌年も”お船様”は来た。
その船は、破船ではなく流れ船だった。
船の人は、殺さなくても、すでに死んでいた。
荷は積んでいなかった。
村びとたちは、死人が来ていた赤い着物を剥いで、分配した。
かれらが見たこともない美しく柔らかい布だった。
そのあと、村に恐ろしい病が広がる。天然痘…… 閉ざされた村では、経験したことのない病だった。物語は、想像を絶する悲惨な結末を迎える。
まるで、辺境の村の民俗誌を文学に昇華したような小説だった。
性別不明の村おさは、神の声を聞く予言者で、村おさを支える村のリーダーは経験を積んだ男である。それは、古代の姫彦制を思わせる。
おそらく遠い昔に海から流れ着いた人たちの子孫なのだろう。
死ねば魂は海に還り、また村の女の胎内に戻ってくるという信仰がある。
男女のまぐわいは、そのための儀式とされる。
村のひとたちは、貧しく平等で、富は公平に分配される。
村おさの指示は神の声だから、絶対である。
個我を主張する者はなく、村にいさかいはない。
原始共産制とは、こういう社会をいうのかと思った。
ごくまれに、搾取と懲罰のために訪れる藩の役人の存在さえなければ。
投票する
投票するには、ログインしてください。
読書は、登山のようなものだと思っています。読み終わるまでが上り、考えて感想や書評を書き終えるまでが下り。頂上からどんな景色が見られるか、ワクワクしながら読書という登山を楽しんでいます。
- この書評の得票合計:
- 35票
| 読んで楽しい: | 7票 |
|
|---|---|---|
| 参考になる: | 26票 | |
| 共感した: | 2票 |
あなたの感想は?
投票するには、ログインしてください。
書評一覧を取得中。。。
- 出版社:新潮社
- ページ数:227
- ISBN:9784101117188
- 発売日:1985年03月01日
- 価格:500円
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。