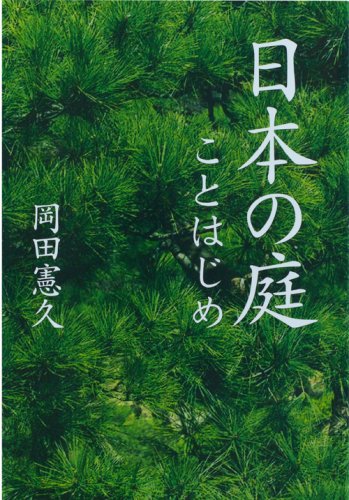休蔵さん
レビュアー:
▼
なんとなく眺めて楽しい日本庭園について、分かりやすく解説してくれる1冊。見る目がきっと変わるはず。
国内旅行の目的地に著名な日本庭園を組み込む人は多いはず。
特に京都旅行の場合、目的地から庭園を外すことのほうが難しいかもしれない。
では、目的地について、庭園を目の前にしたとき、見方が分からずはたと困ったことはないだろうか。
鯉が泳ぐ池があり、その向こうに山が築かれている。
水の代わりに白砂が敷かれ、そこに箒で文様が刻まれている場合もある。
遠望できる山を借景にしているとか解説される場合もあろう。
解説されるがまま、目の前に広がる景色を眺めるがまま、庭園を楽しむことはできる。
しかし、満喫したと言えるだろうか。
そんな不満を持つ方にお薦めの1冊が本書である。
本書は日本庭園についての概説書である。
通常、古い時代から特徴を追うことが多いものの、本書はいきなり近現代から取り上げるところが面白い。
時代的に近いところから解説しようということらしい。
そして、第2章で「自然を造形する」という内容を展開する。
庭そのものではなく、庭が具備するであろう、日本の原風景についての解説だ。
ここでは「神を迎える造形」、「農における自然の造形」、「都市の自然」について取り上げる。
庭に対して何が求められているのか、その具体について迫っており、庭園鑑賞のポイントを自分なりに醸成することができよう。
第3章は「大陸から伝わったもの」ということで、中国、韓国の庭園について解説する。
日本庭園の骨格は第2章で示されたポイント通りであるが、庭園の型式については大陸の影響が大きい。
もともとは自然神への崇拝の表現だったものに大陸との交流により型を獲得することになった。
そして、型を自分なりの解釈で変容させていく、日本文化お得意の手法と言えようか。
第4章以降がいよいよ日本庭園の具体で、まずは変遷を示す。
そして、第5章の庭園の様式として、池庭や枯山水庭園、露地、坪庭と具体を教えてくれる。
ただし、「農の景」に取り組むところは独自性が打ち立てられていて面白い。
さらに、第6章では細部に突っ込む。
時間概念のデザイン化、庭園の骨格、庭園のディテールである。
特に庭園のディテールでは、細部を解説する。
飛び石も垣根も橋すら解説してくれる。
まあ、でもあまり細かく眺めるのがいいわけではなさそうだ。
日本庭園は、単に眺めるだけでも十分愉しめる。
緑豊かな景色を眺めるもよし、白砂に託された思いをくみ取るもよし、石組に写し込まれた真の姿を透かし見るもよし。
それでも、一定の知識を持つことは、庭園観察に少しばかりでも深みを与えてくれるに違いない。
単なる庭園論に留まらない本書の企みは、多くの概説書からは得られにくいビターな深みを与えてくれるはず。
できれば、本書を開く前に本書に掲載された庭園を観察し、その後で本書を読み、改めて同じ庭園を訪れてみたい。
きっと同じものを見ているとは思えないほど、感じるものは変わると思う。
かくいう僕は1か所だけ試してみました。
なかなか面白かった。
特に京都旅行の場合、目的地から庭園を外すことのほうが難しいかもしれない。
では、目的地について、庭園を目の前にしたとき、見方が分からずはたと困ったことはないだろうか。
鯉が泳ぐ池があり、その向こうに山が築かれている。
水の代わりに白砂が敷かれ、そこに箒で文様が刻まれている場合もある。
遠望できる山を借景にしているとか解説される場合もあろう。
解説されるがまま、目の前に広がる景色を眺めるがまま、庭園を楽しむことはできる。
しかし、満喫したと言えるだろうか。
そんな不満を持つ方にお薦めの1冊が本書である。
本書は日本庭園についての概説書である。
通常、古い時代から特徴を追うことが多いものの、本書はいきなり近現代から取り上げるところが面白い。
時代的に近いところから解説しようということらしい。
そして、第2章で「自然を造形する」という内容を展開する。
庭そのものではなく、庭が具備するであろう、日本の原風景についての解説だ。
ここでは「神を迎える造形」、「農における自然の造形」、「都市の自然」について取り上げる。
庭に対して何が求められているのか、その具体について迫っており、庭園鑑賞のポイントを自分なりに醸成することができよう。
第3章は「大陸から伝わったもの」ということで、中国、韓国の庭園について解説する。
日本庭園の骨格は第2章で示されたポイント通りであるが、庭園の型式については大陸の影響が大きい。
もともとは自然神への崇拝の表現だったものに大陸との交流により型を獲得することになった。
そして、型を自分なりの解釈で変容させていく、日本文化お得意の手法と言えようか。
第4章以降がいよいよ日本庭園の具体で、まずは変遷を示す。
そして、第5章の庭園の様式として、池庭や枯山水庭園、露地、坪庭と具体を教えてくれる。
ただし、「農の景」に取り組むところは独自性が打ち立てられていて面白い。
さらに、第6章では細部に突っ込む。
時間概念のデザイン化、庭園の骨格、庭園のディテールである。
特に庭園のディテールでは、細部を解説する。
飛び石も垣根も橋すら解説してくれる。
まあ、でもあまり細かく眺めるのがいいわけではなさそうだ。
日本庭園は、単に眺めるだけでも十分愉しめる。
緑豊かな景色を眺めるもよし、白砂に託された思いをくみ取るもよし、石組に写し込まれた真の姿を透かし見るもよし。
それでも、一定の知識を持つことは、庭園観察に少しばかりでも深みを与えてくれるに違いない。
単なる庭園論に留まらない本書の企みは、多くの概説書からは得られにくいビターな深みを与えてくれるはず。
できれば、本書を開く前に本書に掲載された庭園を観察し、その後で本書を読み、改めて同じ庭園を訪れてみたい。
きっと同じものを見ているとは思えないほど、感じるものは変わると思う。
かくいう僕は1か所だけ試してみました。
なかなか面白かった。
お気に入り度:









掲載日:
外部ブログURLが設定されていません
投票する
投票するには、ログインしてください。
ここに参加するようになって、読書の幅が広がったように思います。
それでも、まだ偏り気味。
いろんな人の書評を参考に、もっと幅広い読書を楽しみたい!
- この書評の得票合計:
- 36票
| 読んで楽しい: | 3票 | |
|---|---|---|
| 参考になる: | 33票 |
あなたの感想は?
投票するには、ログインしてください。
この書評へのコメント

コメントするには、ログインしてください。
書評一覧を取得中。。。
- 出版社:TOTO出版
- ページ数:327
- ISBN:9784887062924
- 発売日:2008年05月15日
- 価格:2625円
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。