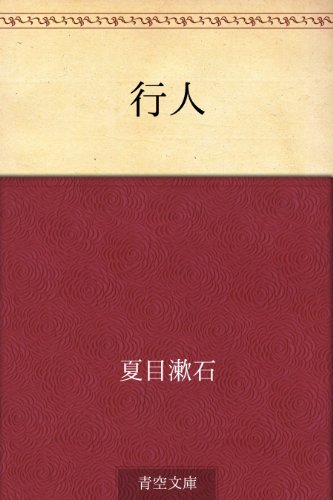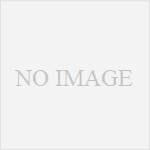紅い芥子粒さん
レビュアー:
▼
書斎の人に”家”は、重すぎる。
行人(こうじん)とは、旅する人のことだろうか。人生という道を行く旅人。
1912年12月6日から1913年11月5日まで朝日新聞に連載された。
途中、病気のため5か月の中断があったという。
小説の中心になるのは、長野一郎、二郎の兄弟。
このあまりにも安易な名付けは、なんだろう。
一郎二郎なんて、長男二男ほどの意味しかないではないか。
そう、この小説は、むかしの家父長制家族の二男から見た長男の物語なのである。
長男として生まれた一郎は、生まれたときから特別だった。
家督を継いで家長になるものとして育てられたのだ。
使用人が何人もいるような裕福な家である。
分家や、分家の分家や、そのまた分家からも人が頼ってくるような大きな家の長になることが、生まれたときから決まっていた。
一郎には、直という妻がある。一郎の両親、弟の二郎、妹の重と同居である。
直は、一郎の妻になる前から二郎となじみがあった。年齢は二郎に近いのだろう。
一郎は、直が二郎を好きなのではないかと邪推している。
広い家でも狭い家でも、むかしは同居があたりまえだったから、あ、ウチも同じ!と思った当時の新聞読者も、少なくなかっただろう。
嫁と義弟とか、嫁とまだ若い舅とか、疑い出せばきりがない。
そういう人は、続きを読むのが楽しみだったにちがいない。
一郎は、邪推するだけではすまなかった。直の貞節を試すために、弟と直を、二人きりで旅行に行かせたのだから、尋常ではない。
二郎はいやだったが、兄には逆らえない。しぶしぶ日帰りのつもりで行ったところ嵐にあって、二郎と直は一泊せざるをえなくなる。
一郎は、嵐の夜に二人に何があったか、ねちねちと知りたがる。
直を書斎によんで、頭を打ったりする。
一郎は、学者である。何の学問かわからないが、家では書斎にひきこもってぶあつい書物を読んで、思索にふけっている。大学で講義もしている。
両親も直も妹も、そして二郎も、一郎は勉強のし過ぎで頭がヘンになったのではないかと疑っている。
一郎が食卓にいると、みんな気づまりで話もはずまない。
一郎夫婦には幼い娘がいるが、父親にまったくなついていない。
二郎と兄嫁は、べつに不道徳な関係ではない。一郎は近寄りにくい人だから、直は親しみやすい義弟と気安く話す。ただそれだけのことなのに。
いたたまれなくなって、二郎は家を出て、ひとり下宿する。
二郎の職業はよくわからない。事務所に勤めているというが、何の事務所かさっぱり。
ともかく二郎は独立した。
家を離れても、兄夫婦のことは気がかりである。
とりわけ一郎のこころの状態は心配だ。
こころのクリニックでもあればいいのだが、当時はそんないいものはない。
二郎は、親友の三沢を介して、兄の親友のHという人に、一郎を気晴らしの旅に連れ出してもらう……
小説は、一郎の親友Hが、旅先からくれた長い手紙で終わっている。
手紙には、旅先での兄の言動とHの見解が記してあるのだが……
その理由が、一郎には、というよりも漱石先生にはまったくわかっていない。
当時の家族制度では、結婚したとたんに、夫は夫権という権力を手にする。
妻は夫に支配される。
おんなが邪になるとしたら、それは、夫の横暴な権力の行使から身を守るためだ。
現に、一郎は直を書斎によんで、頭を打ったではないか。
妻は、夫の血縁で固められた婚家で孤立無援なのだ。
邪にでもならなければ、忍従だけでは、それこそ気がヘンになる。
思うに、一郎に”家”は、重すぎるのだ。彼は書斎の人で、大家族の家長のような俗っぽいことには向かないのだ。むかしの家族制度の犠牲者だと思う。
広辞苑で「行人」を見たら、「自意識に悩む知識人の孤独を描いた」小説とあった。
自意識とか孤独とか、「こころ」もそうだけど、男だけがこの世の苦悩を背負っているような漱石先生の小説には、うんざりする。
1912年12月6日から1913年11月5日まで朝日新聞に連載された。
途中、病気のため5か月の中断があったという。
小説の中心になるのは、長野一郎、二郎の兄弟。
このあまりにも安易な名付けは、なんだろう。
一郎二郎なんて、長男二男ほどの意味しかないではないか。
そう、この小説は、むかしの家父長制家族の二男から見た長男の物語なのである。
長男として生まれた一郎は、生まれたときから特別だった。
家督を継いで家長になるものとして育てられたのだ。
使用人が何人もいるような裕福な家である。
分家や、分家の分家や、そのまた分家からも人が頼ってくるような大きな家の長になることが、生まれたときから決まっていた。
一郎には、直という妻がある。一郎の両親、弟の二郎、妹の重と同居である。
直は、一郎の妻になる前から二郎となじみがあった。年齢は二郎に近いのだろう。
一郎は、直が二郎を好きなのではないかと邪推している。
広い家でも狭い家でも、むかしは同居があたりまえだったから、あ、ウチも同じ!と思った当時の新聞読者も、少なくなかっただろう。
嫁と義弟とか、嫁とまだ若い舅とか、疑い出せばきりがない。
そういう人は、続きを読むのが楽しみだったにちがいない。
一郎は、邪推するだけではすまなかった。直の貞節を試すために、弟と直を、二人きりで旅行に行かせたのだから、尋常ではない。
二郎はいやだったが、兄には逆らえない。しぶしぶ日帰りのつもりで行ったところ嵐にあって、二郎と直は一泊せざるをえなくなる。
一郎は、嵐の夜に二人に何があったか、ねちねちと知りたがる。
直を書斎によんで、頭を打ったりする。
一郎は、学者である。何の学問かわからないが、家では書斎にひきこもってぶあつい書物を読んで、思索にふけっている。大学で講義もしている。
両親も直も妹も、そして二郎も、一郎は勉強のし過ぎで頭がヘンになったのではないかと疑っている。
一郎が食卓にいると、みんな気づまりで話もはずまない。
一郎夫婦には幼い娘がいるが、父親にまったくなついていない。
二郎と兄嫁は、べつに不道徳な関係ではない。一郎は近寄りにくい人だから、直は親しみやすい義弟と気安く話す。ただそれだけのことなのに。
いたたまれなくなって、二郎は家を出て、ひとり下宿する。
二郎の職業はよくわからない。事務所に勤めているというが、何の事務所かさっぱり。
ともかく二郎は独立した。
家を離れても、兄夫婦のことは気がかりである。
とりわけ一郎のこころの状態は心配だ。
こころのクリニックでもあればいいのだが、当時はそんないいものはない。
二郎は、親友の三沢を介して、兄の親友のHという人に、一郎を気晴らしの旅に連れ出してもらう……
小説は、一郎の親友Hが、旅先からくれた長い手紙で終わっている。
手紙には、旅先での兄の言動とHの見解が記してあるのだが……
結婚すると女は邪になると、一郎はいう。
その理由が、一郎には、というよりも漱石先生にはまったくわかっていない。
当時の家族制度では、結婚したとたんに、夫は夫権という権力を手にする。
妻は夫に支配される。
おんなが邪になるとしたら、それは、夫の横暴な権力の行使から身を守るためだ。
現に、一郎は直を書斎によんで、頭を打ったではないか。
妻は、夫の血縁で固められた婚家で孤立無援なのだ。
邪にでもならなければ、忍従だけでは、それこそ気がヘンになる。
思うに、一郎に”家”は、重すぎるのだ。彼は書斎の人で、大家族の家長のような俗っぽいことには向かないのだ。むかしの家族制度の犠牲者だと思う。
広辞苑で「行人」を見たら、「自意識に悩む知識人の孤独を描いた」小説とあった。
自意識とか孤独とか、「こころ」もそうだけど、男だけがこの世の苦悩を背負っているような漱石先生の小説には、うんざりする。
掲載日:
書評掲載URL : http://blog.livedoor.jp/aotuka202
投票する
投票するには、ログインしてください。
読書は、登山のようなものだと思っています。読み終わるまでが上り、考えて感想や書評を書き終えるまでが下り。頂上からどんな景色が見られるか、ワクワクしながら読書という登山を楽しんでいます。
この書評へのコメント

コメントするには、ログインしてください。
書評一覧を取得中。。。
- 出版社:
- ページ数:263
- ISBN:B009IXL130
- 発売日:2012年09月27日
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。