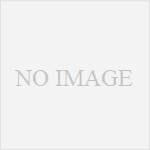ぷるーとさん
レビュアー:
▼
こんな食べ方をしたかったんじゃない!

主人公は、摂政藤原基経に仕えている五位の男。彼は風采の上がらない男で、同位の者たちは、彼を格好のひやかし、いたずらの対象として翻弄している。そればかりか、彼は、下位の者、道で遊んでいる子どもにまで馬鹿にされている。
貧相でだらしない感じのこの男は、数年前から芋粥に異常な執着を持っている。当時、この芋粥は無上の佳味としてもてはやされており、五位のような身分のものにとっては、滅多に食べることのできないものだったからだ。年に一度ほど、主人に臨時の客があったとき、主人が客のために用意した芋粥の残り物をいただけるときがある。彼らのような下っ端に回ってくる量は僅かに喉を潤すに足るほどの少量でしかないのだが、それがこの男にとっては何よりもの喜びなのだ。五位は、いつしか、芋粥を飽きるほど飲んでみたいという夢想を持つようになり、このことが彼の唯一の欲望にさえなっていた。
ところが、五位の思いもかけぬことに、彼のこの願望を聞きつけて、望みをかなえてやろうという男が現れた。その男は、五位の夢をかなえるために、五位を敦賀にまで連れて行った。
どんなに「飽きるほど食べさせてやろう」と豪語したとしても、食する地が京の地であったなら、その量もそうそう多くはあるまいと思われる。だが行く先は敦賀、その長い旅の先の地はいかにも山芋がふんだんに手に入りそうな田舎だ。
敦賀に着いた五位の心境は複雑である。
五位は、何年となく辛抱して待っていた。実はその待つということこそが楽しみだったのだ。しかも、ほんの少しだけ食べることができる、というのがいいのだ。
そのため、五位は、出切る事ならこの約束がフイになってほしい、そしてまたいつものようにやっとのことでありつけたというふうになってほしい、と思う。
だが、五位を招待した利仁は、そんな五位の心の機微など斟酌しない。「飽きるほど食べたい」というのだから、本当に飽きるほど食べられるように準備する。それには、「こんなものを食べたがるなんと」という、ちょっと五位を見下し泡をふかせてやれといった思いもあっただろう。
かくして、敦賀の館の庭には山芋が二三千本以上も積み上げられ、大釜がいくつも火にかけられ、朝の膳に出た椀は一斗も入るかといった大きなもので、それに並々と芋粥が注がれているということになった。
五位が欲したのは、このような芋粥ではない。 確かに「飽きるほど食べたい」と彼は言ったが、その「飽きるほど食べる」は、このような食べ方ではなかった。
誰の家にもそんなにたくさんあるわけではない貴重な山芋で、だからこそ本当は自分のような身分の者になど手の届くはずのないものなのだが、それがどういった幸運からか自分のような者でもいただけることになった。そのような芋粥を、少しずつ少しずつ有難がっていただく。五位が欲した芋粥とは、そのような芋粥であったのだ。
その願った量も、何とも有難いことに自分が満腹と思うちょうど同じくらいか、それより少し多いぐらい。たくさんないものであるからこそそういった幸運に自分が預かるのがうれしいのであり、そういった事情を乗り越えて自分が掴み取った一椀を愛でながら食べるのが楽しいのだ。「飽きるほど食べたい」といったところで、実際に飽きるほどあったのでは、その芋粥のありがたみが、まったくなくなってしまうではないか。
五位は、積みあげられた山芋を見、いくつも並んだ大釜を見た時点で、すでに芋粥に飽きてしまっている。何千本とある山芋には、もはやありがたみなどないからだ。
しかも、自分が長年大切に持っていた夢は、かなえられてしまった。
夢がかなうのを待ちつづけている時間こそが、何よりも幸福な時間なのだ。どんな小さな夢であれ、それがかなってしまったら、人は、喪失感を感じずにはいられない。
五位は、これから何を心のよすがにするのだろう。新たな夢を見つけられるだろうか。
貧相でだらしない感じのこの男は、数年前から芋粥に異常な執着を持っている。当時、この芋粥は無上の佳味としてもてはやされており、五位のような身分のものにとっては、滅多に食べることのできないものだったからだ。年に一度ほど、主人に臨時の客があったとき、主人が客のために用意した芋粥の残り物をいただけるときがある。彼らのような下っ端に回ってくる量は僅かに喉を潤すに足るほどの少量でしかないのだが、それがこの男にとっては何よりもの喜びなのだ。五位は、いつしか、芋粥を飽きるほど飲んでみたいという夢想を持つようになり、このことが彼の唯一の欲望にさえなっていた。
ところが、五位の思いもかけぬことに、彼のこの願望を聞きつけて、望みをかなえてやろうという男が現れた。その男は、五位の夢をかなえるために、五位を敦賀にまで連れて行った。
どんなに「飽きるほど食べさせてやろう」と豪語したとしても、食する地が京の地であったなら、その量もそうそう多くはあるまいと思われる。だが行く先は敦賀、その長い旅の先の地はいかにも山芋がふんだんに手に入りそうな田舎だ。
敦賀に着いた五位の心境は複雑である。
我五位の心には、何となく釣合いのとれない不安があった。第一、時間のたっていくのが、待遠い。しかもそれと同時に、夜の明けると云う事が、ー芋粥を食う時になると云う事が、そう早く、来てはならないような心もちがする。
五位は、何年となく辛抱して待っていた。実はその待つということこそが楽しみだったのだ。しかも、ほんの少しだけ食べることができる、というのがいいのだ。
そのため、五位は、出切る事ならこの約束がフイになってほしい、そしてまたいつものようにやっとのことでありつけたというふうになってほしい、と思う。
だが、五位を招待した利仁は、そんな五位の心の機微など斟酌しない。「飽きるほど食べたい」というのだから、本当に飽きるほど食べられるように準備する。それには、「こんなものを食べたがるなんと」という、ちょっと五位を見下し泡をふかせてやれといった思いもあっただろう。
かくして、敦賀の館の庭には山芋が二三千本以上も積み上げられ、大釜がいくつも火にかけられ、朝の膳に出た椀は一斗も入るかといった大きなもので、それに並々と芋粥が注がれているということになった。
五位が欲したのは、このような芋粥ではない。 確かに「飽きるほど食べたい」と彼は言ったが、その「飽きるほど食べる」は、このような食べ方ではなかった。
誰の家にもそんなにたくさんあるわけではない貴重な山芋で、だからこそ本当は自分のような身分の者になど手の届くはずのないものなのだが、それがどういった幸運からか自分のような者でもいただけることになった。そのような芋粥を、少しずつ少しずつ有難がっていただく。五位が欲した芋粥とは、そのような芋粥であったのだ。
その願った量も、何とも有難いことに自分が満腹と思うちょうど同じくらいか、それより少し多いぐらい。たくさんないものであるからこそそういった幸運に自分が預かるのがうれしいのであり、そういった事情を乗り越えて自分が掴み取った一椀を愛でながら食べるのが楽しいのだ。「飽きるほど食べたい」といったところで、実際に飽きるほどあったのでは、その芋粥のありがたみが、まったくなくなってしまうではないか。
五位は、積みあげられた山芋を見、いくつも並んだ大釜を見た時点で、すでに芋粥に飽きてしまっている。何千本とある山芋には、もはやありがたみなどないからだ。
五位は眼をつぶって、唯でさえ赤い鼻を、一層赤くしながら、堤に半分ばかりの芋粥を大きな土器(かわらけ)にすくって、いやいやながら飲み干した。・・・始めから芋粥は、一椀も吸いたくない。それを今、我慢して、やっと堤に半分だけ平らげた。
しかも、自分が長年大切に持っていた夢は、かなえられてしまった。
夢がかなうのを待ちつづけている時間こそが、何よりも幸福な時間なのだ。どんな小さな夢であれ、それがかなってしまったら、人は、喪失感を感じずにはいられない。
五位は、これから何を心のよすがにするのだろう。新たな夢を見つけられるだろうか。
お気に入り度:







掲載日:
外部ブログURLが設定されていません
投票する
投票するには、ログインしてください。
ホラー以外は、何でも読みます。みなさんの書評を読むのも楽しみです。
よろしくお願いします。
- この書評の得票合計:
- 33票
| 読んで楽しい: | 11票 | |
|---|---|---|
| 参考になる: | 17票 | |
| 共感した: | 5票 |
あなたの感想は?
投票するには、ログインしてください。
この書評へのコメント

コメントするには、ログインしてください。
書評一覧を取得中。。。
- 出版社:
- ページ数:17
- ISBN:B009IWPSD0
- 発売日:2012年09月27日
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。