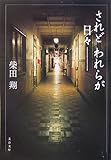すずはら なずなさん
レビュアー:
▼
「あなたは私の青春でした。」そう言い切って、次へ踏み出す女性に拍手。
世代がばれてしまうと思いますが、私が大学生になった頃の「ヘルメットの人」はどこか孤独で不安そうに見えました。
仲間を求め、勧誘しているとしても 宗教のサークルの「あなたは今幸せですか」「その幸せは本物ではありません。もっと幸せについて考えましょう」的な 近づき方をしてくる人たちの方が 押しが強く元気があったように思います。
どちらにしても、時代は移ろっていて、そんな「同士」を求める声に耳を貸す人は そんなにいなかったように思います。(※『大学の入口辺りで演説しているヘルメットの人』と聞いても何のことだか想像もつかない人も多いかもしれませんね)
それからもっとさかのぼり、大学生、いえ高校生たちまでも 日本の政治を変えるための武力による闘争 というものを信じていた時代がありました。
物語はそんな時代を潜り抜けた元大学生たちのその後と、手紙の形を取って その頃の彼らの思い、悩みが浮き彫りにされていきます。
ただ主人公の文夫(東大を出て 今は大学院の卒業を控えています)は そういった時代の流れからは一歩引いて、政治がらみの活動にも参加せず、幾人かの女子大生と愛の無い付き合いを繰り返して、今は親の薦めた幼馴染の婚約者もいて、安定した将来を予想できる立場にいます。
物語が動き出すのは一冊の古本。その蔵書印に 文夫の婚約者、節子はある男性を思い出します。
とはいえ、それが付き合っていた人だとか、好きだった人だとか そういう単純なものではないのが 却って物語に深みを与えます。文夫も手伝って その本の元持ち主の「その後」を訪ね、時代の移ろいとその中で生きて、悩んだ人たちの葛藤を浮き彫りにしていきます。
節子にその蔵書印と同じものの入った本を貸してくれた人は、激しい政治運動の最中に逃げ出したことを気に病みつつ、普通の企業人として生き、あるきっかけで生きることの虚しさに耐え切れず自殺していまいます。彼の「その後」を追ってたどり着いた彼の「遺書」。
遺書の中、人は最後に何を思い出すのだろう、そんな問いかけに、節子は日々を顧みます。
文夫との婚約について、自分の生き方について。そして 彼女の周りに生きる友人たちの生き様について。熱い想いで見つめ続けた人がいたこと。
男子目線の物語かと思っていたら、意外なことに女子の方がそれぞれの生き方を 読者に見せます。不倫相手に薦められて見合い結婚を決める女性や、婚約者がいながら行きずりの男性と関係を持つ女性。文夫の回想の中で出てくる女性たち、妊娠の末、結果、自殺してしまう女性。
それぞれの女性の気持ちの揺れがきちんと描かれていて、そんなところも意外ではありました。却ってオトコたちの考え方や身の処し方がズルかったり 頼りなかったり、情けなかったり。
武力闘争で国を変えることを信じていた人たちは、共産党の方向転換に衝撃を受け、今まで持ってきた価値観や信念が崩れてしまいます。その後 自分で何を信じ何を求めるか、今まで自分たちがやってきたことをどう捉え、どんな立場で生きるのか、確かに難しいことと思います。でも、時代の移ろいに合わせてでも 自分自身を肯定しないと生きていけない。幸せな生活はできません。
そういう人たちがいたことを背景にしながらも、主人公の文夫と婚約者の節子の悩みや葛藤はもっと別のところにあります。文夫の方は一貫してぼんやりした悩み(のように私には思えます)が、節子のそれは切実で、不幸な事故は「自殺」ではなかったものの、自分の生き方を見つめ直し、自分と婚約者の関係に足りないものを問います。
節子の手紙の中、積み木遊びをした幼い頃の思い出は象徴的で、ただ自分が高く積むことに熱中し、邪魔を許さなかった文夫に対し、たとえ積み木が崩れても それさえ楽しめた節子、一緒に遊んでいるそのことこそ喜びだった節子の思いは そのまま大人になった二人の求めるものの違いを示唆しているようです。
だからこそ、節子の決断には拍手を送りたいし、失いそうになって初めて相手を「大事」に思えた文夫のもたつきが歯がゆく思えます。
「あなたが私の青春でした」という節子の手紙の締めくくりを読んで、どこで聞いたのだろうと一瞬解りませんでしたが 後に荒井由実の「卒業写真」でこのフレーズは使われています。
良かったのか、報われたかどうかはともかく 熱い志を持った人たちのいた時代のことを描いて「昔はよかった、今の若者は…」と言わんばかりの物語になるのかと思っていたのですが
「やがて、私たちが本当に年老いた時、若い人たちがきくかも知れない、あなた方の頃はどうだったのかと」と始まるメッセージがあるのには衝撃でした。以下 少し長い引用になります。
「私たちの頃にも同じように困難があった。もちろん時代が違うから違う困難ではあったけれども、困難があるという点では同じだった。そして、私たちはそれと馴れ合って、こうして老いてきた。だが、私たちの中にも、時代の困難から抜け出し、新しい生活へ勇敢に進み出そうとした人がいたのだと。そして、その答えをきいた若い人たちの中の誰か一人が、そういうことが昔もあった以上、今われわれにもそうした勇気を持つことは許されていると考えるとしたら、そこまで老いて行った私たちの生にも、それなりの意味があったと言えるのかも知れない。」
次の時代の若い人たちの「困難」はどんなものだと作者はその頃考えたのでしょうか。今の時代の「困難」に直面して若い人たちはどれほど真摯に戦っているでしょうか。
それをどれが偉いとかどっちが凄いとか言うことなく、それぞれの生の意味を肯定しようとすることに作者の想いを感じます。
にしても、さほど歳の違わない婚約者の女性が相手の男性に敬語で語るとか、自分の過去を赤裸々にさらす長文の「手紙」を書くとか、今の感覚では違和感があるのも、「時代」なんだなぁと思います。
仲間を求め、勧誘しているとしても 宗教のサークルの「あなたは今幸せですか」「その幸せは本物ではありません。もっと幸せについて考えましょう」的な 近づき方をしてくる人たちの方が 押しが強く元気があったように思います。
どちらにしても、時代は移ろっていて、そんな「同士」を求める声に耳を貸す人は そんなにいなかったように思います。(※『大学の入口辺りで演説しているヘルメットの人』と聞いても何のことだか想像もつかない人も多いかもしれませんね)
それからもっとさかのぼり、大学生、いえ高校生たちまでも 日本の政治を変えるための武力による闘争 というものを信じていた時代がありました。
物語はそんな時代を潜り抜けた元大学生たちのその後と、手紙の形を取って その頃の彼らの思い、悩みが浮き彫りにされていきます。
ただ主人公の文夫(東大を出て 今は大学院の卒業を控えています)は そういった時代の流れからは一歩引いて、政治がらみの活動にも参加せず、幾人かの女子大生と愛の無い付き合いを繰り返して、今は親の薦めた幼馴染の婚約者もいて、安定した将来を予想できる立場にいます。
物語が動き出すのは一冊の古本。その蔵書印に 文夫の婚約者、節子はある男性を思い出します。
とはいえ、それが付き合っていた人だとか、好きだった人だとか そういう単純なものではないのが 却って物語に深みを与えます。文夫も手伝って その本の元持ち主の「その後」を訪ね、時代の移ろいとその中で生きて、悩んだ人たちの葛藤を浮き彫りにしていきます。
節子にその蔵書印と同じものの入った本を貸してくれた人は、激しい政治運動の最中に逃げ出したことを気に病みつつ、普通の企業人として生き、あるきっかけで生きることの虚しさに耐え切れず自殺していまいます。彼の「その後」を追ってたどり着いた彼の「遺書」。
遺書の中、人は最後に何を思い出すのだろう、そんな問いかけに、節子は日々を顧みます。
文夫との婚約について、自分の生き方について。そして 彼女の周りに生きる友人たちの生き様について。熱い想いで見つめ続けた人がいたこと。
男子目線の物語かと思っていたら、意外なことに女子の方がそれぞれの生き方を 読者に見せます。不倫相手に薦められて見合い結婚を決める女性や、婚約者がいながら行きずりの男性と関係を持つ女性。文夫の回想の中で出てくる女性たち、妊娠の末、結果、自殺してしまう女性。
それぞれの女性の気持ちの揺れがきちんと描かれていて、そんなところも意外ではありました。却ってオトコたちの考え方や身の処し方がズルかったり 頼りなかったり、情けなかったり。
武力闘争で国を変えることを信じていた人たちは、共産党の方向転換に衝撃を受け、今まで持ってきた価値観や信念が崩れてしまいます。その後 自分で何を信じ何を求めるか、今まで自分たちがやってきたことをどう捉え、どんな立場で生きるのか、確かに難しいことと思います。でも、時代の移ろいに合わせてでも 自分自身を肯定しないと生きていけない。幸せな生活はできません。
そういう人たちがいたことを背景にしながらも、主人公の文夫と婚約者の節子の悩みや葛藤はもっと別のところにあります。文夫の方は一貫してぼんやりした悩み(のように私には思えます)が、節子のそれは切実で、不幸な事故は「自殺」ではなかったものの、自分の生き方を見つめ直し、自分と婚約者の関係に足りないものを問います。
節子の手紙の中、積み木遊びをした幼い頃の思い出は象徴的で、ただ自分が高く積むことに熱中し、邪魔を許さなかった文夫に対し、たとえ積み木が崩れても それさえ楽しめた節子、一緒に遊んでいるそのことこそ喜びだった節子の思いは そのまま大人になった二人の求めるものの違いを示唆しているようです。
だからこそ、節子の決断には拍手を送りたいし、失いそうになって初めて相手を「大事」に思えた文夫のもたつきが歯がゆく思えます。
「あなたが私の青春でした」という節子の手紙の締めくくりを読んで、どこで聞いたのだろうと一瞬解りませんでしたが 後に荒井由実の「卒業写真」でこのフレーズは使われています。
良かったのか、報われたかどうかはともかく 熱い志を持った人たちのいた時代のことを描いて「昔はよかった、今の若者は…」と言わんばかりの物語になるのかと思っていたのですが
「やがて、私たちが本当に年老いた時、若い人たちがきくかも知れない、あなた方の頃はどうだったのかと」と始まるメッセージがあるのには衝撃でした。以下 少し長い引用になります。
「私たちの頃にも同じように困難があった。もちろん時代が違うから違う困難ではあったけれども、困難があるという点では同じだった。そして、私たちはそれと馴れ合って、こうして老いてきた。だが、私たちの中にも、時代の困難から抜け出し、新しい生活へ勇敢に進み出そうとした人がいたのだと。そして、その答えをきいた若い人たちの中の誰か一人が、そういうことが昔もあった以上、今われわれにもそうした勇気を持つことは許されていると考えるとしたら、そこまで老いて行った私たちの生にも、それなりの意味があったと言えるのかも知れない。」
次の時代の若い人たちの「困難」はどんなものだと作者はその頃考えたのでしょうか。今の時代の「困難」に直面して若い人たちはどれほど真摯に戦っているでしょうか。
それをどれが偉いとかどっちが凄いとか言うことなく、それぞれの生の意味を肯定しようとすることに作者の想いを感じます。
にしても、さほど歳の違わない婚約者の女性が相手の男性に敬語で語るとか、自分の過去を赤裸々にさらす長文の「手紙」を書くとか、今の感覚では違和感があるのも、「時代」なんだなぁと思います。
お気に入り度:





掲載日:
外部ブログURLが設定されていません
投票する
投票するには、ログインしてください。
実家の本棚の整理を兼ねて家族の残した本や自分の買ったはずだけど覚えていない本などを読んでいきます。今のところ昭和の本が中心です。平成にたどり着くのはいつのことやら…。
- この書評の得票合計:
- 38票
| 読んで楽しい: | 3票 |
|
|---|---|---|
| 素晴らしい洞察: | 1票 |
|
| 参考になる: | 24票 | |
| 共感した: | 10票 |
あなたの感想は?
投票するには、ログインしてください。
この書評へのコメント
- noel2020-12-21 22:47
高く積むことに熱中し、邪魔を許さなかった文夫に対し、たとえ積み木が崩れてもそれさえ楽しめた節子、一緒に遊んでいるそのことこそ喜びだった節子の思いはそのまま大人になった二人の求めるものの違いを示唆している。
この洞察に感銘を受けました。団塊の世代に属しながら、いわゆるノンポリとして政治にはなんの興味も持たなかった一人として、その虚無感はいまだ続いています。
生きることが社会的地位の確立や名誉などではなく、生きてあること自体を愉しめる節子の姿勢に共感を覚えます。メットをかぶり、石ころ一個?円で投擲を手伝っていた連中もいまはもう、何事もなかったようにひっそりと生きています。
ノンポリ学生も死にました。いま生きているのは綺麗な顔をしたマネキンのようなお姉さん・お兄さんたち。そこに憂いはなく「キミたちが本当に年老いた時、あなた方の頃はどうだったのか」と問われたとき、彼らはいったいどう答えるのでしょう。クリックすると、GOOD!と言っているユーザーの一覧を表示します。 
コメントするには、ログインしてください。
書評一覧を取得中。。。
- 出版社:文藝春秋
- ページ数:269
- ISBN:9784167102050
- 発売日:2007年11月01日
- 価格:560円
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。