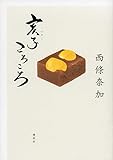hackerさん
レビュアー:
▼
セリーヌが20世紀が生んだ最高の作家の一人であることは間違いありません。今まで、彼の八つの長編小説はすべてレビューを書いていますが、今年は残りの「セリーヌの作品」シリーズを読んでみます。
新年はとうに過ぎ、旧正月の願というわけではありませんが、今年は、今まで手がついていなかった、若しくは再読しようと思っていた、長めの小説の全集や選集を読んでみようと思っています。昨年末より読みだしたカフカ全集もその一環なのですが、他にバルザック全集という大物がありますし、ドストエフスキーやカミュの諸作も再読したいと思っています。そして、この「セリーヌの作品」も、その一つです。
さて、本書には、言い方は悪いですが、戯曲のように完成した作品もありますが、書かれた時代もバラバラの色々な未完の断片的作品も収められています。個別に簡単に紹介します。
・『戦争』
自分の生涯が色濃く反映されたセリーヌの作品群ですが、彼の生涯と対比させると、少年時代を描いた『なしくずしの死』(1936年)と、志願兵として出征した第一次大戦以降を描いた『夜の果てへの旅』(1932年)の間を、本作は埋めるものになります。ただ、この作品の原稿は、第二次大戦中は対独協力者と見なされていたセリーヌが、連合軍の進行を受けてパリを脱出する前に、レジスタンスを名乗る暴徒に自宅を襲われた際に持ち去られたと言われ、いわば幻の作品だったのですが、後に、ここに収録された第一章だけが見つかったものです。未発表だったことから、セリーヌはまだ手を入れるつもりだったのでしょうが、セリーヌ節は健在です。
「(軍馬の世話係は)仕切りから仕切りへと忙しく動きまわって、馬糞集めをやり始めた。馬のケツの後で、本当の離れ業って奴だ。やっこさんが、突っ込む、ドンピシャだ....糞が、湯気をブワーと噴き上げて、ほとばしり出て来る....それで、やっこさんの箕の中に、ピタリと納まるんだ....名人芸だ....やっこさん、実に見事に動き回って、まさにその瞬間に跳びつくんだ!脚を巧みに送りながら....ナニが噴き出さないうちに、ブリッブリッと流れ出す前に....うまく平衡を保ちながら、そうやって収穫したやつを、戻って来ては、積み上げる....小山のようにそびえ立ち、ぽかぽか湯気をたてていやがる」
これは、志願兵となった主人公が、初日に受ける洗礼の一部ですが、何とおかしいこと!もちろん、この部分だけでは評価などできないのですが、『夜の果てへの旅』では比較的軽い描写だった戦争の実態を、もっと赤裸々に描いた作品だったのだろうと思うと、永遠に失われてしまったのが本当に残念です。
・『胸甲騎兵デトゥーシュの手記』
第一次大戦開始前の騎兵時代の作者の思いがメモ程度に書かれたもので、資料として見るべきものです。なお、セリーヌの本名はルイ=フェルディナン・デトゥーシュです。
・『教会』
アフリカの植民地、ニューヨークの劇場、国際連盟、パリのビストロと舞台を変える五幕の戯曲です。書かれたのは『夜の果てへの旅』(以下『旅』と略す)より前なのですが、出版されたのは『旅』が評判となった後の1933年です。主人公は、これも作者の分身である、バルダミュ(『旅』の主人公と同じ名前)医師で、『旅』の前半部分と同じ作者の人生を反映しているようですし、『旅』への助走的作品と言えそうです。ところで、本書には教会はまったく出てきません。訳者解説では、この点を、次のように説明しています。
「『教会』Eglise の語源は『人々の集まり』(ギリシャ語)であったことを考えるなら、これが、『集団』ないし『社会』をも含意していることが分る。つまり、『教会』とは、集団によって形作られる人間の社会そのものであり、人々は、その社会を維持し、築き上げることに汲々として、『集団の言葉』しか話そうとしない」
これ自体を否定するつもりはありませんが、個人的には、フランス社会に根深いカトリックへの反発も、この題名には含まれているような気がします。なんせ、自分の墓に「NON(否)」とだけ刻んだセリーヌですから。
ただ、戯曲にしてしまうと、腐敗と偽善に満ちた社会全体と自分自身を罵倒する、セリーヌ節の面白さが消えてしまい、全体とすると、凡庸な印象しか受けません。『夜』の発表前は、出版してくれる会社がいなかったという事実が、それを証明しているようです。
・『プログレ』
この戯曲の題名の意味は「進歩」です。こちらも、わけの分からない題名です。出版されたのは1978年ですが、書かれたのは1920年代とされ、セリーヌ初期の習作的位置づけの作品です。『教会』より更に前に書かれたもののようで、多少なりとも話の筋道がある『教会』と比べても、ある家庭の一場面から始まり、最後は、売春宿でお客と娼婦のセックスを覗きが趣味の別の客が見るというドンチャン大騒ぎの場面で終わるというハチャメチャな展開の戯曲です。それに、書かれた時代に、こんな内容でまともに公演なんかできるわけもなく、セリーヌも発表するつもりはなかったのではないでしょうか。
・『音楽もなく、だれもおらず、何もないバレー』
1959年に刊行された、五つのバレー台本が収録されている本ということになっています。個別には紹介しませんが、内容を読むと、とてもバレーではありません。それどころか、舞台で上演できそうもない内容です。例えば、こんな怪物が登場します。
「この黙示録の半人半獣の動物は釘と鉤と鋸歯の背甲がついた巨大なとかげの形をしており....顔だけが人間の顔で、絶えず怒気を含み凄まじい形相をしている....手の先は長い鉤爪で終っており....足は巨大な金槌風で其の両の足を怪物は調べにのせて....大きな音をたてて打ち合わせる....鉤のついた吸盤風の口からは、ねばねばと物をつかもことのできる深紅の舌が律動的に飛び出してくる」(『雷霆(らいてい)と矢』より)
こんな衣装(着ぐるみ?)で登場したら、役者は動けないでしょうし、観客は大笑い(これはセリーヌの狙い通りでしょうが)しますね。実は、この「バレー台本」なるものは、品のないミュージカル映画のシノプシスと呼んだ方がよくて、場面転換といい、登場するキャラクタといい、映画でなければ、とても処理できません。ただ、ミュージカルである以上トーキーが前提なのですが、キャラクタの表情や動きはサイレント映画の影を引きずっていて、まぁ、現実的には、これを映画にしようと考える奇特な人はいないでしょう。
・『島の秘密』
1936年に発表された映画シノプシスです。明らかにサイレント映画向けのものだとだけ言っておきます。
さて、本書を総括すると、セリーヌの緒作品に、たびたび登場する、淫靡な美女、そういう美女の虐殺、官能的な踊り、足に障害のある少女、無垢なる存在、猥雑さへの共感といったものが、全体を通じて感じとることができます。そういうセリーヌの一貫性を知るためのあくまでも参考資料ということになりそうです。
さて、本書には、言い方は悪いですが、戯曲のように完成した作品もありますが、書かれた時代もバラバラの色々な未完の断片的作品も収められています。個別に簡単に紹介します。
・『戦争』
自分の生涯が色濃く反映されたセリーヌの作品群ですが、彼の生涯と対比させると、少年時代を描いた『なしくずしの死』(1936年)と、志願兵として出征した第一次大戦以降を描いた『夜の果てへの旅』(1932年)の間を、本作は埋めるものになります。ただ、この作品の原稿は、第二次大戦中は対独協力者と見なされていたセリーヌが、連合軍の進行を受けてパリを脱出する前に、レジスタンスを名乗る暴徒に自宅を襲われた際に持ち去られたと言われ、いわば幻の作品だったのですが、後に、ここに収録された第一章だけが見つかったものです。未発表だったことから、セリーヌはまだ手を入れるつもりだったのでしょうが、セリーヌ節は健在です。
「(軍馬の世話係は)仕切りから仕切りへと忙しく動きまわって、馬糞集めをやり始めた。馬のケツの後で、本当の離れ業って奴だ。やっこさんが、突っ込む、ドンピシャだ....糞が、湯気をブワーと噴き上げて、ほとばしり出て来る....それで、やっこさんの箕の中に、ピタリと納まるんだ....名人芸だ....やっこさん、実に見事に動き回って、まさにその瞬間に跳びつくんだ!脚を巧みに送りながら....ナニが噴き出さないうちに、ブリッブリッと流れ出す前に....うまく平衡を保ちながら、そうやって収穫したやつを、戻って来ては、積み上げる....小山のようにそびえ立ち、ぽかぽか湯気をたてていやがる」
これは、志願兵となった主人公が、初日に受ける洗礼の一部ですが、何とおかしいこと!もちろん、この部分だけでは評価などできないのですが、『夜の果てへの旅』では比較的軽い描写だった戦争の実態を、もっと赤裸々に描いた作品だったのだろうと思うと、永遠に失われてしまったのが本当に残念です。
・『胸甲騎兵デトゥーシュの手記』
第一次大戦開始前の騎兵時代の作者の思いがメモ程度に書かれたもので、資料として見るべきものです。なお、セリーヌの本名はルイ=フェルディナン・デトゥーシュです。
・『教会』
アフリカの植民地、ニューヨークの劇場、国際連盟、パリのビストロと舞台を変える五幕の戯曲です。書かれたのは『夜の果てへの旅』(以下『旅』と略す)より前なのですが、出版されたのは『旅』が評判となった後の1933年です。主人公は、これも作者の分身である、バルダミュ(『旅』の主人公と同じ名前)医師で、『旅』の前半部分と同じ作者の人生を反映しているようですし、『旅』への助走的作品と言えそうです。ところで、本書には教会はまったく出てきません。訳者解説では、この点を、次のように説明しています。
「『教会』Eglise の語源は『人々の集まり』(ギリシャ語)であったことを考えるなら、これが、『集団』ないし『社会』をも含意していることが分る。つまり、『教会』とは、集団によって形作られる人間の社会そのものであり、人々は、その社会を維持し、築き上げることに汲々として、『集団の言葉』しか話そうとしない」
これ自体を否定するつもりはありませんが、個人的には、フランス社会に根深いカトリックへの反発も、この題名には含まれているような気がします。なんせ、自分の墓に「NON(否)」とだけ刻んだセリーヌですから。
ただ、戯曲にしてしまうと、腐敗と偽善に満ちた社会全体と自分自身を罵倒する、セリーヌ節の面白さが消えてしまい、全体とすると、凡庸な印象しか受けません。『夜』の発表前は、出版してくれる会社がいなかったという事実が、それを証明しているようです。
・『プログレ』
この戯曲の題名の意味は「進歩」です。こちらも、わけの分からない題名です。出版されたのは1978年ですが、書かれたのは1920年代とされ、セリーヌ初期の習作的位置づけの作品です。『教会』より更に前に書かれたもののようで、多少なりとも話の筋道がある『教会』と比べても、ある家庭の一場面から始まり、最後は、売春宿でお客と娼婦のセックスを覗きが趣味の別の客が見るというドンチャン大騒ぎの場面で終わるというハチャメチャな展開の戯曲です。それに、書かれた時代に、こんな内容でまともに公演なんかできるわけもなく、セリーヌも発表するつもりはなかったのではないでしょうか。
・『音楽もなく、だれもおらず、何もないバレー』
1959年に刊行された、五つのバレー台本が収録されている本ということになっています。個別には紹介しませんが、内容を読むと、とてもバレーではありません。それどころか、舞台で上演できそうもない内容です。例えば、こんな怪物が登場します。
「この黙示録の半人半獣の動物は釘と鉤と鋸歯の背甲がついた巨大なとかげの形をしており....顔だけが人間の顔で、絶えず怒気を含み凄まじい形相をしている....手の先は長い鉤爪で終っており....足は巨大な金槌風で其の両の足を怪物は調べにのせて....大きな音をたてて打ち合わせる....鉤のついた吸盤風の口からは、ねばねばと物をつかもことのできる深紅の舌が律動的に飛び出してくる」(『雷霆(らいてい)と矢』より)
こんな衣装(着ぐるみ?)で登場したら、役者は動けないでしょうし、観客は大笑い(これはセリーヌの狙い通りでしょうが)しますね。実は、この「バレー台本」なるものは、品のないミュージカル映画のシノプシスと呼んだ方がよくて、場面転換といい、登場するキャラクタといい、映画でなければ、とても処理できません。ただ、ミュージカルである以上トーキーが前提なのですが、キャラクタの表情や動きはサイレント映画の影を引きずっていて、まぁ、現実的には、これを映画にしようと考える奇特な人はいないでしょう。
・『島の秘密』
1936年に発表された映画シノプシスです。明らかにサイレント映画向けのものだとだけ言っておきます。
さて、本書を総括すると、セリーヌの緒作品に、たびたび登場する、淫靡な美女、そういう美女の虐殺、官能的な踊り、足に障害のある少女、無垢なる存在、猥雑さへの共感といったものが、全体を通じて感じとることができます。そういうセリーヌの一貫性を知るためのあくまでも参考資料ということになりそうです。
お気に入り度:





掲載日:
外部ブログURLが設定されていません
投票する
投票するには、ログインしてください。
「本職」は、本というより映画です。
本を読んでいても、映画好きの視点から、内容を見ていることが多いようです。
この書評へのコメント

コメントするには、ログインしてください。
書評一覧を取得中。。。
- 出版社:国書刊行会
- ページ数:0
- ISBN:9784336026781
- 発売日:2003年09月01日
- 価格:3570円
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。