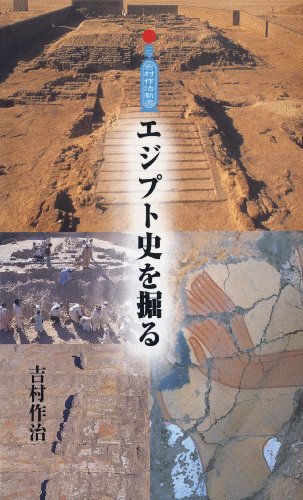DBさん
レビュアー:
▼
発掘調査についての詳細の本
エジプト考古学の第一人者といってもいい吉村作治教授が、初めてエジプトに行った時の思い出や発掘を振り返った本です。
1965年、学園紛争真っ最中の早稲田大学でエジプト学研究会を発足させた学生時代の吉村教授は、オリエント考古学専門の川村教授を隊長にエジプトを目指して勉強会を始める。
そして「とにかくエジプトへ行こう。行く以上は大学を休学して、一年くらい行ってみよう」というかけ声のもとに集まった五人の学生が、アルバイトで資金をためアラビア語を勉強し、1966年9月にタンカーに乗ってアラビアを目指し出発した。
「やれば出来るものなのだなあとしみじみ思った」と見送る川村教授の言葉がすべてでしょう。
カイロの雑踏にもまれピラミッドを見学し、とうとうジェネラル・サーベイへ乗り出していく。
カイロを出発してファユーム、エル・ミニア、アシュート、ルクソールへ。
ルクソールでは今でも観光名所となっているカルナック神殿からルクソール神殿、王家の谷、女王の谷、ハトシェプスト葬祭殿、メムノンの巨像と見るものがたくさんある。
王家の谷の近くの砂漠に、本書に出てくるカーターハウスに並んで早稲田ハウスもあったのを思い出した。
墓の村クルナは泥棒の村として前を通っただけだったが、村中に数千の墓が存在し、そこから掘り出したものを売って生活しているのだとか。
約二万の住民を新しい場所に移住させようとしたが、誰も引っ越しをせずそのままになっているらしいです。
ファラオの時代から現代まで墓泥棒の被害は甚大なようです。
アスワンからフィライ島、そしてアブ・シンベルまで巡ってジェネラル・サーベイを終え、「ナイルの水を飲んだ者は必ずナイルに戻れる」という言い伝えにあやかってナイルの水を飲んで帰国した吉村教授は、翌年カイロ大学考古学部の聴講生としてエジプトへ戻ってきます。
そして1971年、紆余曲折を経て南マルカタにて本格的な発掘が始まった。
現地の人との交渉や、お役所の書類に振り回されるなどの苦労もありながら憧れの地で発掘できるという喜びが推進力になっているようだ。
1974年1月、早稲田大学古代エジプト調査隊としてコム・エル・サマックの発掘をしていた川村教授率いる調査隊は極彩色の階段を掘り出していた。
日乾煉瓦の階段に両手を後ろ手に縛られたヌビア人とアジア人の捕虜らしい人物像と二張野弓が交互に配列された絵柄の彩色画が描かれていたそうです。
アメノフィス三世の遺跡らしくカトルーシュも出てきて興奮に包まれる発掘隊ですが、何者かによって階段が壊されるという災難に見舞われる。
エジプト史を掘るということを実体験とその意義について検討した本でした。
1965年、学園紛争真っ最中の早稲田大学でエジプト学研究会を発足させた学生時代の吉村教授は、オリエント考古学専門の川村教授を隊長にエジプトを目指して勉強会を始める。
そして「とにかくエジプトへ行こう。行く以上は大学を休学して、一年くらい行ってみよう」というかけ声のもとに集まった五人の学生が、アルバイトで資金をためアラビア語を勉強し、1966年9月にタンカーに乗ってアラビアを目指し出発した。
「やれば出来るものなのだなあとしみじみ思った」と見送る川村教授の言葉がすべてでしょう。
カイロの雑踏にもまれピラミッドを見学し、とうとうジェネラル・サーベイへ乗り出していく。
カイロを出発してファユーム、エル・ミニア、アシュート、ルクソールへ。
ルクソールでは今でも観光名所となっているカルナック神殿からルクソール神殿、王家の谷、女王の谷、ハトシェプスト葬祭殿、メムノンの巨像と見るものがたくさんある。
王家の谷の近くの砂漠に、本書に出てくるカーターハウスに並んで早稲田ハウスもあったのを思い出した。
墓の村クルナは泥棒の村として前を通っただけだったが、村中に数千の墓が存在し、そこから掘り出したものを売って生活しているのだとか。
約二万の住民を新しい場所に移住させようとしたが、誰も引っ越しをせずそのままになっているらしいです。
ファラオの時代から現代まで墓泥棒の被害は甚大なようです。
アスワンからフィライ島、そしてアブ・シンベルまで巡ってジェネラル・サーベイを終え、「ナイルの水を飲んだ者は必ずナイルに戻れる」という言い伝えにあやかってナイルの水を飲んで帰国した吉村教授は、翌年カイロ大学考古学部の聴講生としてエジプトへ戻ってきます。
そして1971年、紆余曲折を経て南マルカタにて本格的な発掘が始まった。
現地の人との交渉や、お役所の書類に振り回されるなどの苦労もありながら憧れの地で発掘できるという喜びが推進力になっているようだ。
1974年1月、早稲田大学古代エジプト調査隊としてコム・エル・サマックの発掘をしていた川村教授率いる調査隊は極彩色の階段を掘り出していた。
日乾煉瓦の階段に両手を後ろ手に縛られたヌビア人とアジア人の捕虜らしい人物像と二張野弓が交互に配列された絵柄の彩色画が描かれていたそうです。
アメノフィス三世の遺跡らしくカトルーシュも出てきて興奮に包まれる発掘隊ですが、何者かによって階段が壊されるという災難に見舞われる。
エジプト史を掘るということを実体験とその意義について検討した本でした。
掲載日:
外部ブログURLが設定されていません
投票する
投票するには、ログインしてください。
好きなジャンルは歴史、幻想、SF、科学です。あまり読まないのは恋愛物と流行り物。興味がないのはハウツー本と経済書。読んだ本を自分の好みというフィルターにかけて紹介していきますので、どうぞよろしくお願いします。
この書評へのコメント

コメントするには、ログインしてください。
書評一覧を取得中。。。
- 出版社:株式会社アケト
- ページ数:221
- ISBN:9784903000060
- 発売日:2009年07月01日
- 価格:500円
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。