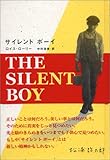休蔵さん
レビュアー:
▼
歴史研究は文献史料だけではなく、遺跡の発掘調査成果や現存する寺社も素材として活用すべきということを実感できる1冊。各地の食もまた歴史的背景を持つ大事な歴史の証人と言えるようだ。
歴史の研究は文献史料を丹念に読む解くことからはじまる。
でも、それだけ十分とは言えないと思う。
本書は遺跡や現存する寺社の探訪を通して歴史の解釈を新しくする試みだ。
本書は平安時代から戦国時代におよぶ全12章からなる。
それに合わせて対象地域も12。
取り上げられる遺跡、寺社は熊野古道(和歌山県)や平等院鳳凰堂(京都府)、厳島神社(広島県)のような世界遺産にも選定されるものから、博多(福岡県)や菅生の岩谷(愛媛県)など、一般的とは言えず、中世史との関わりが見えにくいものも含まれる。
この幅広さが本書の奥行きを深いものにしている。
日本中世史の文献史学者である筆者の遺跡の見方、評価の仕方は、独特の切れ味がある。
例えば、平等院の場合。
平等院は藤原頼道が永承7年(1052)3月28日に父道長から与えられた別業(別荘)を寺に改めたもの。
そして、その前提として道長が寛仁4年(1020)正月に京の鴨川畔に創建した法成寺の無量光院の存在があったとされている。
この無量光院の建立意図は、現在に伝わる供養願文から判断できるそうだ。
そして、供養願文には無量光院は鴨川西畔に建立するということが記されている。
鴨川の景観を取り込んで造寺計画が練られていたのだ。
無量光院に対する鴨川は、平等院の宇治川にあたる。
ただ、現在の風景からは宇治川と平等院の関わりが分かりにくい。
宇治川の堤やその近くの家々により、もともと平等院が宇治川を取り込んだ景観が分かりにくくなっているためだ。
しかし、発掘調査で当時の景観が明らかになった。
どうやら、創建当時は堂の前側、後側の池が現在より広く、庭園は宇治川へと地続きで繋がっていたというのだ。
無量光院、平等院ともに周囲の山々も景観を取り込んだ建立計画のもと建てられていた。
そこに阿弥陀堂を据え置くことで極楽浄土を現世に築き上げようとしたのである。
平等院が建立されたのは、仏法が衰えると考えられた末法に入った年。
社会を不安感が覆い包もうとしていた時代だけに、極楽への切なる願いが伝わってくる。
文献史料は多くのことを我々に伝えてくれる。
ただし、歴史の舞台に足を運び、目で見て、肌で感じることは、文字では残されなかった多くの情報の存在に気づかせてくれるはず。
引き出す努力を惜しまなければ、それらもまた雄弁なはず。
例え、ビル群が立ち並ぶ殺風景な現在の景観越しでも。
本書各章は、筆者が現地で特産品を味わうことで締めくくられていて、そこも楽しみと言える。
平等院の章では宇治茶である。
現地の味もまた歴史の証人の一人と言えるだろう。
旅をしながら歴史を学ぶ際の大切な相棒になるに違いない。
でも、それだけ十分とは言えないと思う。
本書は遺跡や現存する寺社の探訪を通して歴史の解釈を新しくする試みだ。
本書は平安時代から戦国時代におよぶ全12章からなる。
それに合わせて対象地域も12。
取り上げられる遺跡、寺社は熊野古道(和歌山県)や平等院鳳凰堂(京都府)、厳島神社(広島県)のような世界遺産にも選定されるものから、博多(福岡県)や菅生の岩谷(愛媛県)など、一般的とは言えず、中世史との関わりが見えにくいものも含まれる。
この幅広さが本書の奥行きを深いものにしている。
日本中世史の文献史学者である筆者の遺跡の見方、評価の仕方は、独特の切れ味がある。
例えば、平等院の場合。
平等院は藤原頼道が永承7年(1052)3月28日に父道長から与えられた別業(別荘)を寺に改めたもの。
そして、その前提として道長が寛仁4年(1020)正月に京の鴨川畔に創建した法成寺の無量光院の存在があったとされている。
この無量光院の建立意図は、現在に伝わる供養願文から判断できるそうだ。
そして、供養願文には無量光院は鴨川西畔に建立するということが記されている。
鴨川の景観を取り込んで造寺計画が練られていたのだ。
無量光院に対する鴨川は、平等院の宇治川にあたる。
ただ、現在の風景からは宇治川と平等院の関わりが分かりにくい。
宇治川の堤やその近くの家々により、もともと平等院が宇治川を取り込んだ景観が分かりにくくなっているためだ。
しかし、発掘調査で当時の景観が明らかになった。
どうやら、創建当時は堂の前側、後側の池が現在より広く、庭園は宇治川へと地続きで繋がっていたというのだ。
無量光院、平等院ともに周囲の山々も景観を取り込んだ建立計画のもと建てられていた。
そこに阿弥陀堂を据え置くことで極楽浄土を現世に築き上げようとしたのである。
平等院が建立されたのは、仏法が衰えると考えられた末法に入った年。
社会を不安感が覆い包もうとしていた時代だけに、極楽への切なる願いが伝わってくる。
文献史料は多くのことを我々に伝えてくれる。
ただし、歴史の舞台に足を運び、目で見て、肌で感じることは、文字では残されなかった多くの情報の存在に気づかせてくれるはず。
引き出す努力を惜しまなければ、それらもまた雄弁なはず。
例え、ビル群が立ち並ぶ殺風景な現在の景観越しでも。
本書各章は、筆者が現地で特産品を味わうことで締めくくられていて、そこも楽しみと言える。
平等院の章では宇治茶である。
現地の味もまた歴史の証人の一人と言えるだろう。
旅をしながら歴史を学ぶ際の大切な相棒になるに違いない。
お気に入り度:







掲載日:
外部ブログURLが設定されていません
投票する
投票するには、ログインしてください。
ここに参加するようになって、読書の幅が広がったように思います。
それでも、まだ偏り気味。
いろんな人の書評を参考に、もっと幅広い読書を楽しみたい!
この書評へのコメント

コメントするには、ログインしてください。
書評一覧を取得中。。。
- 出版社:岩波書店
- ページ数:210
- ISBN:9784004311805
- 発売日:2009年03月01日
- 価格:735円
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。