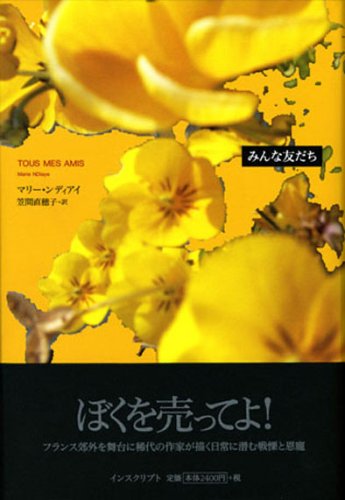hackerさん
レビュアー:
▼
17歳で処女長編を発表し、2001年にフェミナ賞(『ロジー・カルプ』)、2009年にゴンクール賞(『三人の逞しい女』)を受けた、現代仏文学界を代表する作家マリー・ンディアイの2004年刊の短編集です。
1967年生まれのマリー・ンディアイを日本に初めて紹介した本書には、5作収録されており、いずれも素晴らしい作品ばかりですが、訳者笠間奈穂子による「マリー・ンディアイの世界」と題された解説も、この作者の作品と世界を、平易な言葉で丁寧に語っていて、とても参考になります。そういう二重の意味で、ンディアイに興味がおありの方にとって、本書は必読書です。その解説の中で、笠間奈穂子は、作者の特徴について、次のように述べています。
「フランス文学の風土にあっては珍しいほど、英米、とくにアメリカの近現代小説を読み込んでいることだろう。初めて大きな感銘を受けた小説は13歳の時に読んだジョイス・キャロル・オーツの『かれら』だったという」
今まで意識したことはありませんでしたが、文学の世界では、確かに、母国語若しくは処女作を発表した言語で書かれた作品に影響を受けた小説家の方が、そうでない作家より、圧倒的に多いでしょう。私は、映画が好きなもので、例えば、ヌーヴェル・ヴァーグの監督たちが、ジャン・ルノワールなどの例外を喉いて、フランスの監督よりも、ジョン・フォードやハワード・ホークスやアルフレッド・ヒッチヒッチコックなどの英米の監督の方に熱狂していたのを知っていますし、デイヴィッド・グーディスやジム・トンプスンなどは、フランスが「発見」したことも知られています。あまり気づいていなかったのですが、映画では言葉はある意味で一つの道具でしかなく、ミステリーには言葉以上に重要な要素があるのは言うまでもありませんから、こういうことは珍しく感じなかったのだろうと思います。
しかし、文学作品となると、言葉がすべてであるため、どうしても文学者は自分に馴染みのある言語若しくは類似言語の作品への嗜好が強まるのだろうと思います。もちろん、シェイクスピアやドストエフスキーやチェーホフなどの古典は別でしょう。ただ、ンディアイが13歳の時に『かれら』を原語で読んだとは思えませんから、翻訳を読んでいるはずで、そう考えると、翻訳という仕事の重要性と大変さが分かりますし、様々な言語の海外文学を読むことができる日本の現状には感謝したいものです。誰が言ったのかは忘れましたが、「翻訳は文学だ」というのは正しいと思います。
前置きが長くなりました。さて、短編集に関しては、気に入った収録作品の内容を簡単に紹介するというのが、私のレビューのいつもの流れなのですが、本書に関しては止めておきます。一つには、素晴らしい作品ばかりであることなのですが、もう一つには、内容を紹介しても、とても作者の言語世界を紹介することになりそうもないからです。
ただ、『少年たち』における、少年の人身売買、『クロード・フランソワの死』における、中年になってから再開する少女時代の親友、『みんな友だち』の20年経ってから再会する元教師と教え子の女性と彼女の元恋人と現在の夫という元教師の不毛の愛、『プリュラールの一日』における、若いころ端役で映画に出たこともある中年女性を中心に、その別れた夫や娘をめぐる一日、『見出されたもの』における、精神疾患のある息子を施設に入れようとバスに乗る母親のように、歳月が引き金となる、家庭や愛情や友情の崩壊ばかりを扱っているということは指摘していいでしょう。
そして、この作者に限らず、近年の小説の特徴かもしれませんが、謎は謎として説明されないまま終わるものばかりです。特に衝撃的なラストを持つ『少年たち』では、それが顕著です。『クロード・フランソワの死』の元親友たちや『プリュラールの一日』の元夫婦も、これからどうなるのか、読者に判断が委ねられています。唯一、やや希望を抱かせる雰囲気のエンディングの『見出されたもの』も、その雰囲気がはたして持続するものなのかは、分からないままです。そして、どの作品も、忘れがたい余韻を残します。読み終わったその場から、もう一度読みたくなるような短編集なのです。
セネガル人の父親とフランス人の母親を持つ作家という先入観もあるでしょうが、フランス文学伝統の心理描写や、ヌーヴォー・ロマンなどの影響も受けつつ、他の世界の文学のエッセンスも詰め込まれたような作風に、今後も期待したいものです。
「フランス文学の風土にあっては珍しいほど、英米、とくにアメリカの近現代小説を読み込んでいることだろう。初めて大きな感銘を受けた小説は13歳の時に読んだジョイス・キャロル・オーツの『かれら』だったという」
今まで意識したことはありませんでしたが、文学の世界では、確かに、母国語若しくは処女作を発表した言語で書かれた作品に影響を受けた小説家の方が、そうでない作家より、圧倒的に多いでしょう。私は、映画が好きなもので、例えば、ヌーヴェル・ヴァーグの監督たちが、ジャン・ルノワールなどの例外を喉いて、フランスの監督よりも、ジョン・フォードやハワード・ホークスやアルフレッド・ヒッチヒッチコックなどの英米の監督の方に熱狂していたのを知っていますし、デイヴィッド・グーディスやジム・トンプスンなどは、フランスが「発見」したことも知られています。あまり気づいていなかったのですが、映画では言葉はある意味で一つの道具でしかなく、ミステリーには言葉以上に重要な要素があるのは言うまでもありませんから、こういうことは珍しく感じなかったのだろうと思います。
しかし、文学作品となると、言葉がすべてであるため、どうしても文学者は自分に馴染みのある言語若しくは類似言語の作品への嗜好が強まるのだろうと思います。もちろん、シェイクスピアやドストエフスキーやチェーホフなどの古典は別でしょう。ただ、ンディアイが13歳の時に『かれら』を原語で読んだとは思えませんから、翻訳を読んでいるはずで、そう考えると、翻訳という仕事の重要性と大変さが分かりますし、様々な言語の海外文学を読むことができる日本の現状には感謝したいものです。誰が言ったのかは忘れましたが、「翻訳は文学だ」というのは正しいと思います。
前置きが長くなりました。さて、短編集に関しては、気に入った収録作品の内容を簡単に紹介するというのが、私のレビューのいつもの流れなのですが、本書に関しては止めておきます。一つには、素晴らしい作品ばかりであることなのですが、もう一つには、内容を紹介しても、とても作者の言語世界を紹介することになりそうもないからです。
ただ、『少年たち』における、少年の人身売買、『クロード・フランソワの死』における、中年になってから再開する少女時代の親友、『みんな友だち』の20年経ってから再会する元教師と教え子の女性と彼女の元恋人と現在の夫という元教師の不毛の愛、『プリュラールの一日』における、若いころ端役で映画に出たこともある中年女性を中心に、その別れた夫や娘をめぐる一日、『見出されたもの』における、精神疾患のある息子を施設に入れようとバスに乗る母親のように、歳月が引き金となる、家庭や愛情や友情の崩壊ばかりを扱っているということは指摘していいでしょう。
そして、この作者に限らず、近年の小説の特徴かもしれませんが、謎は謎として説明されないまま終わるものばかりです。特に衝撃的なラストを持つ『少年たち』では、それが顕著です。『クロード・フランソワの死』の元親友たちや『プリュラールの一日』の元夫婦も、これからどうなるのか、読者に判断が委ねられています。唯一、やや希望を抱かせる雰囲気のエンディングの『見出されたもの』も、その雰囲気がはたして持続するものなのかは、分からないままです。そして、どの作品も、忘れがたい余韻を残します。読み終わったその場から、もう一度読みたくなるような短編集なのです。
セネガル人の父親とフランス人の母親を持つ作家という先入観もあるでしょうが、フランス文学伝統の心理描写や、ヌーヴォー・ロマンなどの影響も受けつつ、他の世界の文学のエッセンスも詰め込まれたような作風に、今後も期待したいものです。
お気に入り度:









掲載日:
外部ブログURLが設定されていません
投票する
投票するには、ログインしてください。
「本職」は、本というより映画です。
本を読んでいても、映画好きの視点から、内容を見ていることが多いようです。
書評一覧を取得中。。。
- 出版社:インスクリプト
- ページ数:256
- ISBN:9784900997134
- 発売日:2006年05月23日
- 価格:2520円
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。