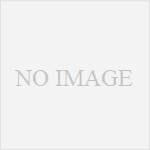hackerさん
レビュアー:
▼
「わたしがひとつ発見したのは、奇妙なことって本当に起こるということ。それもしょっちゅう。例えば今日、わたしの親友のジルの猫が口をきいた」(本書収録『日記』の冒頭)
う~ん、吸引力ありますねぇ。
ぱせりさんの書評で、この素晴らしい本のことを知りました。感謝いたします。
本書は「そこに住むことを運命づけられている」ニューヨーク州ロングアイランドの架空のフランコーニアという町のグレーテル・サミュエルソンという少女を主人公とした15作からなる連作短編集ですが、グレーテルの12歳から20代半ばまでを描いた長編小説でもあります。彼女は「町を歩くと見えてくるのは、フランコーニア高等学校、フランコーニア商店街、フランコーニア食堂、(中略)フランコーニア・ステーキハウス」という田舎町にうんざりしています。
グレーテルの家族には、癌になったお母さんのフランシス、お母さんと別れて家を出て別の女と再婚したお父さんのサム、ハーヴァード大学への早期入学が認められていたほどの秀才だったものの、両親の離婚を機に目標を見失い生活のために働くようになった兄のジェイソンがいて、大の親友には「長い金髪で、男の子たちを夢中にさせるお砂糖のように甘い声」のジルがいます。本書では、これらの登場人物を中心に、どこにでもある「本当に起こる」「奇妙なこと」が語られていきます。
「運命は好きなように、カタカタ、ゴロゴロと私たちを動かしていく」
実際、いろいろなことが起こります。祖母のフリーダが、自分の命と引き換えに、娘フランシスの命を救ってくれる契約を神とした(つもり)後で死んでしまったり、ジルが「地球が丸いということを習わなかったらしい」ボーイフレンドのエディの子供を妊娠して結婚したり、グレーテル自身がドラッグ・ディーラーのソニー・ガーネットに初恋をしたり、母親が癌を再発して自分の墓地を買いに行ったり、人生で誰もが経験するようなことが語られます。
そして、本書の巻末の表題作『ローカル・ガールズ』のラスト、これが私はとても好きです。
成人した独身のグレーテルが、自分が生まれ育った家は他人の物となっている故郷を久しぶりに訪問し、いまや三人の子持ちになったジルと、暑くて眠れない夜にビールを飲みながら、最近、近くのガレージで今の人生を悲観して自殺した二人の少女を話題にする場面です。
「『馬鹿な子たち』ジルは首を振る。『少し待てばよかったのよ。待ちさえすればよかった。大人になれば何もかも解決したのに』
『わたしたち、待ってよかったわね』」
そして、グレーテルの腕に「青ざめた黄色い光が、SOSのように点滅している」一匹のホタルが止まります。
「『殺しちゃう?』ジルは言う。
ふたりはけたたましく笑う。近隣の人びとがすべて寝静まっている6月の真夜中に歩道で笑いころげる。笑ううちに、ホタルは飛び去る。高く高く舞いあがったので、星と見分けがつかなくなる。
『生きることにしたのね』とグレーテル。
結局そういう簡単なことなのだ。
『そう、あっぱれだわ』そのホタルがもう見えないと知りながら、ジルは目をあげて木々のあいだに瞳をこらす。『わたしたちもあっぱれね』ジルは言う」
何人かの人間が死に、何人かの子どもが産まれる本書の、現在形で語られているこのラストの余韻には泣きそうになります。ただ同時に、私は、人間がいかに不自由にしか生きられないのだろうとも思います。特にジェイソンの転落は、心にしみます。ですが、そういう不自由も含めて、これが人生というものなのでしょう。
1952年生まれの作者アリス・ホフマンもロングアイランド出身で、1999年刊の本書には彼女の少女時代そして自らの癌体験とそこからの回復体験が反映されていると思います。なお、本書で採用している人称ですが、前半のグレーテルの少女時代は彼女の一人称で語られることが多く、後半は三人称で語られることが多くなっています。作者にとっても、本当の自分は、社会に出る前の、少女時代にしかないということなのかもしれません。
本書は「そこに住むことを運命づけられている」ニューヨーク州ロングアイランドの架空のフランコーニアという町のグレーテル・サミュエルソンという少女を主人公とした15作からなる連作短編集ですが、グレーテルの12歳から20代半ばまでを描いた長編小説でもあります。彼女は「町を歩くと見えてくるのは、フランコーニア高等学校、フランコーニア商店街、フランコーニア食堂、(中略)フランコーニア・ステーキハウス」という田舎町にうんざりしています。
グレーテルの家族には、癌になったお母さんのフランシス、お母さんと別れて家を出て別の女と再婚したお父さんのサム、ハーヴァード大学への早期入学が認められていたほどの秀才だったものの、両親の離婚を機に目標を見失い生活のために働くようになった兄のジェイソンがいて、大の親友には「長い金髪で、男の子たちを夢中にさせるお砂糖のように甘い声」のジルがいます。本書では、これらの登場人物を中心に、どこにでもある「本当に起こる」「奇妙なこと」が語られていきます。
「運命は好きなように、カタカタ、ゴロゴロと私たちを動かしていく」
実際、いろいろなことが起こります。祖母のフリーダが、自分の命と引き換えに、娘フランシスの命を救ってくれる契約を神とした(つもり)後で死んでしまったり、ジルが「地球が丸いということを習わなかったらしい」ボーイフレンドのエディの子供を妊娠して結婚したり、グレーテル自身がドラッグ・ディーラーのソニー・ガーネットに初恋をしたり、母親が癌を再発して自分の墓地を買いに行ったり、人生で誰もが経験するようなことが語られます。
そして、本書の巻末の表題作『ローカル・ガールズ』のラスト、これが私はとても好きです。
成人した独身のグレーテルが、自分が生まれ育った家は他人の物となっている故郷を久しぶりに訪問し、いまや三人の子持ちになったジルと、暑くて眠れない夜にビールを飲みながら、最近、近くのガレージで今の人生を悲観して自殺した二人の少女を話題にする場面です。
「『馬鹿な子たち』ジルは首を振る。『少し待てばよかったのよ。待ちさえすればよかった。大人になれば何もかも解決したのに』
『わたしたち、待ってよかったわね』」
そして、グレーテルの腕に「青ざめた黄色い光が、SOSのように点滅している」一匹のホタルが止まります。
「『殺しちゃう?』ジルは言う。
ふたりはけたたましく笑う。近隣の人びとがすべて寝静まっている6月の真夜中に歩道で笑いころげる。笑ううちに、ホタルは飛び去る。高く高く舞いあがったので、星と見分けがつかなくなる。
『生きることにしたのね』とグレーテル。
結局そういう簡単なことなのだ。
『そう、あっぱれだわ』そのホタルがもう見えないと知りながら、ジルは目をあげて木々のあいだに瞳をこらす。『わたしたちもあっぱれね』ジルは言う」
何人かの人間が死に、何人かの子どもが産まれる本書の、現在形で語られているこのラストの余韻には泣きそうになります。ただ同時に、私は、人間がいかに不自由にしか生きられないのだろうとも思います。特にジェイソンの転落は、心にしみます。ですが、そういう不自由も含めて、これが人生というものなのでしょう。
1952年生まれの作者アリス・ホフマンもロングアイランド出身で、1999年刊の本書には彼女の少女時代そして自らの癌体験とそこからの回復体験が反映されていると思います。なお、本書で採用している人称ですが、前半のグレーテルの少女時代は彼女の一人称で語られることが多く、後半は三人称で語られることが多くなっています。作者にとっても、本当の自分は、社会に出る前の、少女時代にしかないということなのかもしれません。
お気に入り度:









掲載日:
外部ブログURLが設定されていません
投票する
投票するには、ログインしてください。
「本職」は、本というより映画です。
本を読んでいても、映画好きの視点から、内容を見ていることが多いようです。
この書評へのコメント

コメントするには、ログインしてください。
書評一覧を取得中。。。
- 出版社:みすず書房
- ページ数:240
- ISBN:9784622075646
- 発売日:2010年09月11日
- 価格:2625円
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。