京都東山 美術館と夜のアート (創元推理文庫)【Kindle】





「京都市在住の文筆家の端くれとして、ここは紙の上なりとも京都市美術館の在りし日の姿を記録しておかなくてはならない。これは地元の住人に課せられた義務であり、特権とはいえまいか。」(あとがき、301頁)
美術館を舞台にしたミステリーです。「館」がついていますが「館もの」ではありませんので、殺人事件は起…

本が好き! 1級
書評数:691 件
得票数:8219 票
学生時代は書評誌に関わってました。今世紀に入り、当初はBK1(現在honto)、その後、TRCブックポータルでレビューを掲載してました。同サイト閉鎖から、こちらに投稿するようになりました。
ニックネームは書評用のものでずっと使ってます。
サイトの高・多機能ぶりに対応できておらず、書き・読み程度ですが、私の文章がきっかけとなって、本そのものを手にとってもらえれば、うれしいという気持ちは変わりません。 特定分野に偏らないよう、できるだけ多様な書を少しずつでも紹介していければと考えています。
プロフィール画像は大昔にバイト先で書いてもらったものです。





「京都市在住の文筆家の端くれとして、ここは紙の上なりとも京都市美術館の在りし日の姿を記録しておかなくてはならない。これは地元の住人に課せられた義務であり、特権とはいえまいか。」(あとがき、301頁)
美術館を舞台にしたミステリーです。「館」がついていますが「館もの」ではありませんので、殺人事件は起…






もっと、もっと「エジプト人の物語」を!
2004年刊行と、類書としてはずいぶんと古い部類に入るのかもしれないが、今なお手にするに値する新鮮…





「作家生活、四十年をすぎまして。/私には、判ったことがあります。/新井素子って、どうも、小説が書けるらしい。」(「あとがき」より、304頁)
時々「同じ作家のもの」「同じような作風のもの」を求める自分がいることに気がつく。意識的に「違うもの…






「海賊なんてわけのわからないものをなぜ研究するのかとよく聞かれる」(「あとがき」より、239頁)
世間より遅ればせながら 『村上海賊の娘』 を手にして以来、日本の海賊の関連書を少しずつ読んでいる。…






「大学の中なのに新宿の裏道を通ったような気分だった」(「白い糸」101頁)って、どんな気分?
表紙には今風の女子高生を真横から描いた姿。この印象的な姿とタイトルのかっこよさから迷わず手にとった…





「ポスターや絵葉書などとは異なり裏面まで活用でき、数も多く作ることができ、手元にもおけるしおりは企業にとっては最適の広告アイテムだったといえます。」(3頁)
「しおり」集めを意識しはじめたのは、ちくま文庫のものからだった。以前は安野光雅による絵だった。「な…





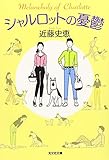
家族で散歩に行くと、シャルロットの目の輝きが全然違う。/交互にわたしと浩輔の顔を見上げ、まるで笑っているような顔になる。/――楽しいねえ。楽しいねえ。(37ー38頁)
最近、近所のワンちゃんがとても気になるのです。「かなり大きい」のだけれど、まだ1歳とちょっとらしく…






「おかしな毎日だった。こうした暮らしが戦争と呼べるなら、おかしな戦争だった」(54頁)
「今、読むべき本は何か」を考えたとき、思いついたのがこの本だった。学生時代に手にした本を掘り出して…





「たとえば学校で、国際戦時法について教えてこなかった。国際条約の課す義務なのに」(331ー2頁)
著名な社会学者による戦争と軍事の社会学の試みである。在籍していた大学で10年ほど続けてきた「軍事社…





「こんなはずではなかった。なんでこうなってしまったのか。ときにそんなため息をつきながら、四十五歳を懸命に生きている。十八歳のときに思い描いていた人生とは、まるで違う日々を。」(223頁)
舞台は現代の神奈川県の秦野市。主要登場人物は40代半ばをむかえた男女たち。彼らが取り組む私設天文台…






「こうした正統と異端をめぐる軋轢は、中世ヨーロッパだけの問題ではない」(3~4頁)
最近、時々感じることがある。自分の関心のあるものを読んだとしても、なんら自分の知見も世界も広がらな…






「いなかの春風のなかには眠り薬がまじっている。」 (本書の書き出し)
芥川賞作家といえども、時の流れは厳しいようです。現在、大型書店の店頭でも見かける三浦哲郎作品の文庫…






「ほどよく荒廃した城跡は暗い森のなかに静かにたたずみ、崩れながらもなお高くそびえる石垣は、織田信長の天下統一への気概とその挫折をそのままに語りかけてくるようでした。」(10頁)
「私は今日の整備がすすむまえの安土城城跡が好きでした。」という一節に続けて上のように語るのは、最近…






「この城には、憂き世には、そのように抗えぬ弱き者の方が多いもの。」(405頁)
言わずとしれた人気作家・米澤穂信氏の燦然と輝く直木賞受賞作。また、何度か候補にはなってきたはずです…





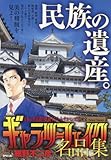
「せやけど・・・うちに言わせたら、京はしょせん飾りもんです。東京が日本の “本妻” なら、京都は “妾” です。」(7話「KYOTO POP」)
正直、こうしたコンビニで売られている名作マンガの「再編集版」を軽く見てました。すみません、やはりギ…






「笑いを取りに行くときは遠慮せずに取りに行かないと、読んでる方が恥ずかしくなるんですよね~」。(担当編集者T嬢のことば、「あとがき」208頁)
ここ数年の大学出版界での最大の話題作である。 なんといっても「大学出版」という業界の先駆けであ…






「余計なおせっかいかもだけど、あなたに見てほしいの。本当に、海ってきれいだから」(102頁)
作者名とタイトル、そして表紙をはじめ随所に挿まれるコミカルなイラストを見て、「これは愉快な作品であ…





「明日爆撃すると言うなら、なぜ今日ではないのかと私は言いたい!」(239頁)
なんとも魅力的なタイトルに抗い難く手にとって読んでみる。 「ゲーム理論」をはじめ様々なノイマン…






「大した事件は起こらなかったがたいへんな休暇だった、と思う。」(「微熱休暇」より、110頁)
1990年代、河出文藝文庫のカバーのマットな肌触りが気に入っていた頃に読了していた1冊。親本刊行は…






「こうしたことすべてが終わっていざ帰国ということになると、すっかり気落ちしてしまった。それは、ニュースに接するときのあの生き生きとした緊迫感を失ってしまったのに気づいたときのことである。」(231頁)
最近になって本書が文庫化されたことを知り、手元の本を引っ張りだして再読してみた。 著者はアメリ…