言語学バーリ・トゥード【Kindle】






「笑いを取りに行くときは遠慮せずに取りに行かないと、読んでる方が恥ずかしくなるんですよね~」。(担当編集者T嬢のことば、「あとがき」208頁)
ここ数年の大学出版界での最大の話題作である。 なんといっても「大学出版」という業界の先駆けであ…

本が好き! 1級
書評数:696 件
得票数:8276 票
学生時代は書評誌に関わってました。今世紀に入り、当初はBK1(現在honto)、その後、TRCブックポータルでレビューを掲載してました。同サイト閉鎖から、こちらに投稿するようになりました。
ニックネームは書評用のものでずっと使ってます。
サイトの高・多機能ぶりに対応できておらず、書き・読み程度ですが、私の文章がきっかけとなって、本そのものを手にとってもらえれば、うれしいという気持ちは変わりません。 特定分野に偏らないよう、できるだけ多様な書を少しずつでも紹介していければと考えています。
プロフィール画像は大昔にバイト先で書いてもらったものです。






「笑いを取りに行くときは遠慮せずに取りに行かないと、読んでる方が恥ずかしくなるんですよね~」。(担当編集者T嬢のことば、「あとがき」208頁)
ここ数年の大学出版界での最大の話題作である。 なんといっても「大学出版」という業界の先駆けであ…






「余計なおせっかいかもだけど、あなたに見てほしいの。本当に、海ってきれいだから」(102頁)
作者名とタイトル、そして表紙をはじめ随所に挿まれるコミカルなイラストを見て、「これは愉快な作品であ…





「明日爆撃すると言うなら、なぜ今日ではないのかと私は言いたい!」(239頁)
なんとも魅力的なタイトルに抗い難く手にとって読んでみる。 「ゲーム理論」をはじめ様々なノイマン…






「大した事件は起こらなかったがたいへんな休暇だった、と思う。」(「微熱休暇」より、110頁)
1990年代、河出文藝文庫のカバーのマットな肌触りが気に入っていた頃に読了していた1冊。親本刊行は…






「こうしたことすべてが終わっていざ帰国ということになると、すっかり気落ちしてしまった。それは、ニュースに接するときのあの生き生きとした緊迫感を失ってしまったのに気づいたときのことである。」(231頁)
最近になって本書が文庫化されたことを知り、手元の本を引っ張りだして再読してみた。 著者はアメリ…





「なんでもかでも三十八文。あぶりこかな網三十八文。枕、かんざし三十八文。はしからはしまで三十八文。」(お瑛が店頭で)
「町人もの」の時代小説の舞台はたいてい長屋だと思っていましたが、本作の舞台は三十八文圴一で色々なモ…





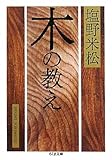
「学ぶことの基本は驚きです。/驚きは新しい知識につながるのです。」(「まえがき」より、11頁)
宮大工・西岡常一氏をはじめ、数多くの木に関わる職人たちへの聞き書きをもとにした1冊である。聞き取り…





『いやあ、結構な節分のお化けだった!』(303頁)
神楽坂にあるという寄席「神楽坂倶楽部」を舞台にした落語×ミステリー三部作の完結作が本書です。主人公…






「初めに数があった。」(「聖なる伝承」の冒頭)
1年ほど前に書店で、「数の女王をもっと楽しむ! フリーペーパー」というものを入手した。A4ペラで本…






「何かの流れがあればそこには必ず渋滞が発生するものなのである。」(4頁)
硬めの本としては、たいへんなベストセラーとなり、今なお売れている1冊と言う。昨年の韓国・梨泰院での…





「いいえ、夢じゃダメよ。覚めて終わる夢なんて、意味がないもの。(後略)」(マッチ売りの少女・エレン、197頁)
『むかしむかしあるところに、死体がありました』 に続く連作ミステリーです。前作が日本の昔話がモチー…





「発展や対立の問題においては、地球上にどれほどの人がいるかよりも、どこに、誰がいるかのほうがはるかに重要だ。」(本書、9頁)
やたらと長いサブタイトルと、サブタイトルと区別しづらい種々の謳い文句に囲まれて、邦訳版は本来の趣旨…





ぬいぐるみ警部! 事件は犯行現場ではなく、街で起きてます!!
『ぬいぐるみ警部の帰還』に続く「ぬいぐるみ警部」もの(短編集)です。残念ながら今回も、主人公である…






ちなみに本書は著者による書き下ろしで、翻訳ではないそうです。
著者は「日本の選挙」を密着調査して『代議士の誕生』という著作(博士論文とか)にまとめた著名な政治学…






そして、君は途方に暮れる。
ゆっくりと読み進めて全3巻を読了。第2巻から感じていたもやもやが、今ひとつ晴れないまま完結してしま…





本書が刊行されたのは2022年。コロナ禍でなかなか旅に行けなかったという思いも、著者と読者とで共有できるかもしれません。
日本史上の事物を写真として見せるものは少なくないのですが、本書は「ちょっと」だけ違います。趣旨は「…






「それにしても、「サラリーマン」とは不可思議な存在ではないか。」(本書、17頁)
興味深いことに2022年には、日本の「サラリーマン」についての研究書が2冊も出された(両方とも博士…






本書をひと言でまとめると、「『サラリーマン』という『普通の人々』のイメージの歴史の記述」(258頁)である。単なる「サラリーマンの歴史」ではない。
本書の冒頭「まえがき」で著者は、研究の動機として2つの点を挙げる。1つは著者自身が20代をサラリー…





「なんか、落ち着き過ぎと違う? 娘の一大事でしょ。」 「大事ねぇ。親が焦ったからとて、どうなるもんでもなし。・・・」 (文子と母のやりとり、59頁)
1981年に『アイコ十六歳』で文藝賞を受賞した作家の、おそらくは第2作。高校生デビューを飾った彼女…






「あした」はわからないが、「あさっては」という心意気
2019年の刊行当時にも話題となった1冊。ここ数年は他にも「独学**」という本が刊行されており、在…