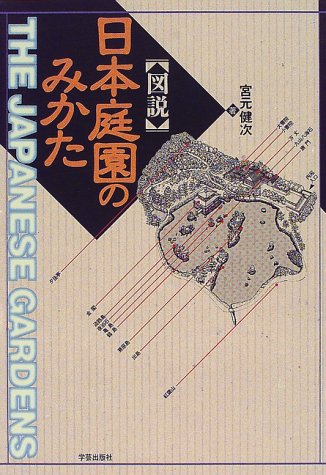休蔵さん
レビュアー:
▼
日本庭園に関する概説書。写真ではなく“図説”というところが本書の特徴と言えよう。
日本各地にさまざまな庭園がある。
新築の一軒家に小さな自分だけの庭を作る人も多いはず。
ただ、その基本は長い造園史の積み重ねにより練り上げられた型によるものと思う。
本書は日本庭園の基本型を教えてくれる概説書。
写真に頼ることなく、鳥観図で的確に教えてくれる。
ただ、図面が小さいところが難点か。
本書は大きく3つの章からなる。
第1章は自然風景式庭園だ。
庭のもっとも基本的な姿と言えるだろう。
しかし、単なる自然風景の導入ではない。
第1項目は「浄土式庭園」だ。
極楽浄土を写したもので、十円玉にも採用された平等院鳳凰堂が代表格。
第2項は寝殿造系庭園。
寝殿造と聞くと『源氏物語』を想起してしまうが、やはりそこには独自の庭園が導入されたようである。
そして、書院造系庭園。
寺院庭園である銀閣寺庭園から大名庭園である兼六園まで幅広い。
定義は武家屋敷の庭園がベースという。
う~ん、定義が難しい。
第2章は枯山水だ。
枯山水はイメージしやすい。
白砂敷で、そこに箒で波紋を刻み付ける手法で、寺院でたまに見かける。
ここでは枯山水を前・後期で分け、さらに普陀落山や須弥山、三尊石と守護石など、石組にこめられた思想を解説してくれる。
波紋のイメージしかなかったが、そんな単純なものではないらしい。
第3章は露地。
茶室の庭園だ。
茶室の前には庭園がつきもの。
それを確立したのは千利休で、そこに古田織部が人工的な要素を加え、小堀遠州が人工味を強調したようだ。
ここにも独自の要素があり、露地門とそれを介する外露地と内露地の概念、腰掛、雪隠などが解説される。
雪隠はトイレのことで、緊急的に用を足すこともある外露地の「下腹雪隠」とトイレとして使用しない「砂雪隠」がある。
トイレすら庭園の要素として取り入れ、美として確立してしまったようだ。
日本各地にある庭園は、観光目的にもなる。
ただ、緑を眺めてゆったりと楽しむことも良し。
白砂に箒で刻んだ紋を眺めるも良し。
石組に込められた思想を創造することも良し。
でも、庭園の歴史と各要素にこめられた想いをしっかりと汲み取ることは、庭園鑑賞の充実度を相当に大きくしてくれるに違いない。
訪問した庭園で解説を読んだり聞いたりすることもいいが、ある程度基本知識を持っておくことは、自分だけの解釈も可能にするはず。
そんな庭園知識を取り入れるためのお供として、本書はお薦めである。
新築の一軒家に小さな自分だけの庭を作る人も多いはず。
ただ、その基本は長い造園史の積み重ねにより練り上げられた型によるものと思う。
本書は日本庭園の基本型を教えてくれる概説書。
写真に頼ることなく、鳥観図で的確に教えてくれる。
ただ、図面が小さいところが難点か。
本書は大きく3つの章からなる。
第1章は自然風景式庭園だ。
庭のもっとも基本的な姿と言えるだろう。
しかし、単なる自然風景の導入ではない。
第1項目は「浄土式庭園」だ。
極楽浄土を写したもので、十円玉にも採用された平等院鳳凰堂が代表格。
第2項は寝殿造系庭園。
寝殿造と聞くと『源氏物語』を想起してしまうが、やはりそこには独自の庭園が導入されたようである。
そして、書院造系庭園。
寺院庭園である銀閣寺庭園から大名庭園である兼六園まで幅広い。
定義は武家屋敷の庭園がベースという。
う~ん、定義が難しい。
第2章は枯山水だ。
枯山水はイメージしやすい。
白砂敷で、そこに箒で波紋を刻み付ける手法で、寺院でたまに見かける。
ここでは枯山水を前・後期で分け、さらに普陀落山や須弥山、三尊石と守護石など、石組にこめられた思想を解説してくれる。
波紋のイメージしかなかったが、そんな単純なものではないらしい。
第3章は露地。
茶室の庭園だ。
茶室の前には庭園がつきもの。
それを確立したのは千利休で、そこに古田織部が人工的な要素を加え、小堀遠州が人工味を強調したようだ。
ここにも独自の要素があり、露地門とそれを介する外露地と内露地の概念、腰掛、雪隠などが解説される。
雪隠はトイレのことで、緊急的に用を足すこともある外露地の「下腹雪隠」とトイレとして使用しない「砂雪隠」がある。
トイレすら庭園の要素として取り入れ、美として確立してしまったようだ。
日本各地にある庭園は、観光目的にもなる。
ただ、緑を眺めてゆったりと楽しむことも良し。
白砂に箒で刻んだ紋を眺めるも良し。
石組に込められた思想を創造することも良し。
でも、庭園の歴史と各要素にこめられた想いをしっかりと汲み取ることは、庭園鑑賞の充実度を相当に大きくしてくれるに違いない。
訪問した庭園で解説を読んだり聞いたりすることもいいが、ある程度基本知識を持っておくことは、自分だけの解釈も可能にするはず。
そんな庭園知識を取り入れるためのお供として、本書はお薦めである。
お気に入り度:







掲載日:
外部ブログURLが設定されていません
投票する
投票するには、ログインしてください。
ここに参加するようになって、読書の幅が広がったように思います。
それでも、まだ偏り気味。
いろんな人の書評を参考に、もっと幅広い読書を楽しみたい!
この書評へのコメント

コメントするには、ログインしてください。
書評一覧を取得中。。。
- 出版社:学芸出版社
- ページ数:190
- ISBN:9784761511609
- 発売日:1998年06月10日
- 価格:1995円
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。