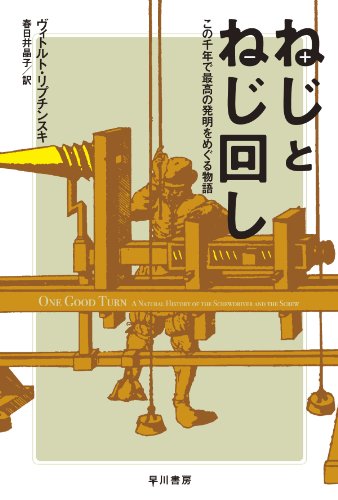「過去1000年間で最高の発明」について新聞にコラムを書くことになった著者は、奥さんのアドバイスでまずねじ回し(スクリュードライバー、日本では単にドライバーともいう)の歴史について調べ始めることに。
<でも、実際にはねじ(スクリュー)の方がねじ回しよりもずっと早く実用化されていたはずではないかな。日本人がねじを知ったのは種子島に来たオランダ人から火縄銃を入手したのが初めだと言われているが、その火縄銃の尾栓(銃身の後ろの蓋)はネジではあるがドライバーを使って開け閉めしたようには見えない(写真)。ネジは大発明だが、ドライバーはあれば便利だがなくても何とかなる。ドライバーはおまけのようなものではないかな。> なお、<>内は僕の独り言。
ともかく著者は英国でスクリュードライバーについて調べ始める。するとスクリュードライバーは英国では元々はターンスクリュー(字の通りねじ回しだ)と呼ばれていて、これはフランス語からの直訳らしいことを突き止めた。
しかしこの辺りでドライバーの調査が行き詰ったため、ねじの方を調べることにした。<初めからそうすれば良かったのに!>
<ところで、ここでねじ(スクリュー)という言葉の意味を確認した方がよいかもしれない。ねじというのは「らせん状の溝」があるものの総称だそうだ。この溝自体をねじと呼ぶこともある。雄ねじをボルト、雌ねじをナットと呼ぶこともある。小さなねじをビスと呼ぶことも。ねじの頭にはマイナスやプラスの溝があって、これにドライバーの先を差し込んで回す。でも最近では頭が六角形のタイプや、頭に六角形の穴が開いていて、六角レンチを差し込んで回すタイプが機械類では多く使われている。ねじの頭に蝶のような形のつまみがあり指で直接回せるのは蝶ねじと呼ばれる。また、木工には木ねじと呼ばれる部分的にねじが切られているタイプが使われる(ねじの溝を加工することをねじを切るという)。>
西洋でねじが使われるようになったのは16世紀半ばらしい。腕時計(と著者は書いているが、時代が早すぎないか?)、鉄砲、甲冑などに使われたが、一本ずつの手作りのため高価だった。1760年に英国で木ねじの量産方法に関する特許が出されて、ねじ一本が5、6秒で作れるようになった。このねじは扉の背出し蝶番の流行に乗ってヒット商品になった。ねじはその後、木工、造船、家具や自動車の生産に使われていった。
次はねじの頭の形について。ネジの製造が機械化された後もねじの頭には一本の溝が掘ってあってマイナスドライバーで閉めていたが、ドライバーの先端がねじから外れて手を怪我したりするトラブルが多かった。まずカナダ人のロバートソンが四角くて先端が尖った穴をねじの頭に加工した。これはフォードの車体に一時使われたが、特許権の問題などで広まらなかった。このロバートソンのねじを米国人のフィリップスが改良したのが現在も使われているプラスねじだ。最初はジェネラルモータースの1936年製のキャディラックで使われた。一方のロバートソンねじも今でも職人や日曜大工愛好者に支持されて生き残っているとか。
話の最後はいわゆるネジの話から離れて、ねじ(スクリュー)の本来の意味である「らせん」を用いた機械の話になる。中世には紙漉き用の圧搾機があり、ここから印刷機に発展したと思われる。ローマ時代にはワインやオリーブオイルの圧搾機が使われていた。らせんを用いた機械の歴史はすごく古い。大プニウスの「博物誌」には圧搾機はアレクサンドリアの数学者のヘロンが発明したと書いてある。
ヘロンはウォームギアと歯車を組み合わせた「無限ねじ」を使って各種の機械を発明したという。ウォームギアは長いねじというか、棒にらせんを切ったもので、この棒の回転運動を歯車の回転運動に変換する装置だ(今でも沢山使われている)。でもこれらは木製だった。今のところ古代ローマ人が鉄製のボルトとナットを使ったという証拠はない。
著者はねじの生みの親は古代ギリシャのアルキメデスだという。彼は中空の円筒の中にらせん状のスクリューを入れて回す揚水機を発明したと伝えられている。これはらせんを利用した人類最初の技術だ。ウォームギアも彼の発明かもしれない。
<でも本来の「ねじとねじ回し」の主題からだいぶ離れてしまっているのでないかなあ・・・ボルトとナットを発明したのは誰なのかは結局は分からないみたいでした。きっと中世の無名の職人たちのアイデアの積み重ねが長い時間をかけて作り出したものなのかもしれませんね。>



1957年、仙台に生まれ、結婚後10年間世田谷に住み、その後20余年横浜に住み、現在は仙台在住。本を読んで、思ったことあれこれを書いていきます。
長年、化学メーカーの研究者でした。2019年から滋賀県で大学の教員になりましたが、2023年3月に退職し、10月からは故郷の仙台に戻りました。プロフィールの写真は還暦前に米国ピッツバーグの岡の上で撮ったものです。
この書評へのコメント
- ゆうちゃん2021-10-20 18:26
各種の写真ありがとうございます。本の内容が蘇りとても参考になりました。
ネジと言う身近な道具を扱いながらも奥が深い話をしているのですが、著者が分かり易く書こうと思っていないのではないか、と疑うような構成のまずさです。訳者も困ったのではないかと思っていましたが・・。ご提示いただいたロバートソンねじの図や写真も本に載っていなかったような・・。ロバートソンは第4章のブレークスルーをもたらした人物なのでその発明品の写真があった方が良いと思いました。
ネジの頭、+やーだけではなく、△とか◇とか色々ありますね。パソコンなども捨てる時にハードディスクに一撃を与えようとして開けてビックリでした。クリックすると、GOOD!と言っているユーザーの一覧を表示します。 - 三太郎2021-10-21 04:23
ゆうちゃんさん、おはようございます。
著者はこのエッセイの焦点が絞れなかったのではないでしょうか。ボルトとナット、あるいはネジとネジ穴の歴史ならもっと分かりやすかったでしょうが、資料が見つからなかったのかも。ネジの加工技術については図も使ってもっと詳しく書いて欲しかったかな。
火縄銃の着火装置に小ねじが使われていたと書いているのに、なぜか銃身の尾栓については記載がないのも不思議です。
ところで、三角のねじ穴があるとは知りませんでした。特殊なドライバーでないと開けられないようにでしょうかね。クリックすると、GOOD!と言っているユーザーの一覧を表示します。 
コメントするには、ログインしてください。
- 出版社:早川書房
- ページ数:208
- ISBN:9784150503666
- 発売日:2010年05月30日
- 価格:630円
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。