狼の群れはなぜ真剣に遊ぶのか
![]()





家族を愛し、遊びを楽しむ。群れで生きるオオカミの知恵。
原題は”Die Weisheit der Woelfe(オオカミの知恵)”。 著者はドイツ人で、弁護…

本が好き! 免許皆伝
書評数:1828 件
得票数:50051 票
分子生物学・生化学周辺の実務翻訳をしています。
本の大海を漂流中。
日々是好日。どんな本との出会いも素敵だ。
あちらこちらとつまみ食いの読書ですが、点が線に、線が面になっていくといいなと思っています。
「実感」を求めて読書しているように思います。
赤柴♀(もも)は3代目。
この夏、有精卵からヒヨコ4羽を孵化させました。そろそろ大雛かな。♂x2、♀x2。ニワトリは割と人に懐くものらしいですが、今のところ、懐く気配はありませんw
![]()





家族を愛し、遊びを楽しむ。群れで生きるオオカミの知恵。
原題は”Die Weisheit der Woelfe(オオカミの知恵)”。 著者はドイツ人で、弁護…

アイヌと猟師と野生動物
明治末期の北海道を舞台に、アイヌの金塊をめぐる冒険サバイバル、3巻目。 アイヌの少女、アシ(リ…

現実の事件に着想したフィクションを読むということ
何とももやもやの残る作品である。 作品のベースには、現実にあった事件がある。2016年5月に起きた…

アイヌの暮らしと動物との関わり
隠された金塊を追って旅をする、不死身の元陸軍兵・杉元と、聡明なアイヌの少女・アシ(リ)パの物語、第2…

明治末期の北海道。アイヌの金塊を巡って、不死身と言われる元陸軍兵、アイヌの少女、網走に収監された囚人が交錯する。
人気コミックスの第1巻。 舞台は日露戦争後の北海道である。 主人公の杉元は、日露戦争で死地をくぐ…

男たちは命を奪われ、女たちは心を殺された。
ISISに捕らわれ、サビーヤ(性奴隷)にされながらも、辛くもその手を逃れた女性の物語。 ヤズィ…

文調を移す。詩想を移す。
二葉亭四迷(1864-1909)の翻訳心得。 二葉亭曰く、欧文は音楽的(ミュージカル)である。…

すべての善き翻訳は「創作」である(萩原朔太郎)
詩人、萩原朔太郎(1886-1942)による詩の翻訳論。 前半は俳句に関する考察である。 当…

自国語で考えるということ
哲学者・三木清(1897-1945)の翻訳論。初出は1931(昭和6)年9月の「文芸春秋」。 …

中江兆民の言に曰く「総て完全な翻訳は、原著者以上に文章の力がなくては出来ぬ」
幸徳秋水(1871-1911)。大逆事件で処刑された思想家、ジャーナリスト、社会主義者である。 本…

鷗外先生にうかつに喧嘩を吹っ掛けるべからず
青空文庫には翻訳に関する小文がいくつかあったので、 岸田國士の『翻訳について』 に引き続き読んでみる…

「甲の美を乙の美に置き換へる技が、翻訳の純文学的営み」(岸田國士)
劇作家、岸田國士(1890-1954)の翻訳論。 名は「こくし」と読むのかと思っていたら、「くにお…

だましたのは誰だ。だまされたのは誰だ。責任はどこにあるのか。
伊丹万作(1900-1946)。映画監督・脚本家・俳優・エッセイスト・挿絵画家と多才な人物である。俳…





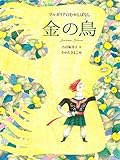
金のりんごを食べにくる まばゆく輝く金の鳥
ブルガリアの昔話です。 むかし、あるところに王さまと3人の王子がいました。 お城には金のりん…

狸、狸、ちょっと熊、狸、狸。
佐藤垢石(さとうこうせき:1888-1956)。エッセイスト、釣りジャーナリスト。 垢の石って何だ…





教育と福祉の狭間で。給食が目指してきたもの、目指していくもの。
学校給食というとどんな思い出があるだろう。 学校で一番楽しい時間だった人もいれば、嫌いなものを食べ…

浅草で飄々と生きる人々
添田唖蝉坊(1872-1944)。演歌師である。 唖蝉坊とは自らを「歌を歌う唖しの蝉」と称した…

(そうか、ゲテモノっていうのは「下手物」のことなんだな・・・)
民藝運動の柳宗悦(1889-1961)が京都に暮らした頃によく通った朝市の話。 京都には月ごと…

活動写真発展期あれこれ
淡島寒月(1859-1926)は作家・画家・古物蒐集家。 淡島家は、軽焼屋で非常に繁盛した。「病が…

詩人が捉える享楽の街の夜明け。
著者・安西冬衛の代表作と言えば、一行詩<春>だろう。 てふてふが一匹韃靼海峡を渡って行った …