赤川次郎の文楽入門―人形は口ほどにものを言い



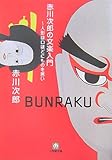
「三十年以上にわたり様々な舞台鑑賞を続けてきた著者が、初心者にも分かりやすく綴ったエッセイ集〜オペラや歌舞伎などの例もふんだんに取り入れることで文楽独自の魅力が浮き彫りになっている」(裏カバーより)
赤川次郎の名前は当然知っていましたが、一冊も著書は読んだことはなく、ただ文楽つながりで読んでみました…

本が好き! 1級
書評数:203 件
得票数:3446 票
2009年10月から母の介護に関わってきましたが、四月末に母は旅立ちました。暫くはレビューを挙げるのを控えたいと思います。喪に服するというよりも六年以上に渡って内向きに生きてきたので、読書数を減らして運動したりアルバイトでもいいから仕事してそれらに没頭したくなりました。いずれまた参加させていただきます。
2016.5.4(2014.8.10初投稿)
⭐️5・・・買って手元に置いときたい。刺激受けました。
⭐️4・・・読んで良かった。読書の喜びを感じる。
⭐️3・・・ウン、なるほど。参考になりました。
⭐️2・・・感心しません。最後まで読み続けるのを悩む。
⭐️1・・・読めません。基本的にレビューしません。



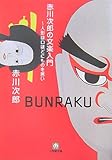
「三十年以上にわたり様々な舞台鑑賞を続けてきた著者が、初心者にも分かりやすく綴ったエッセイ集〜オペラや歌舞伎などの例もふんだんに取り入れることで文楽独自の魅力が浮き彫りになっている」(裏カバーより)
赤川次郎の名前は当然知っていましたが、一冊も著書は読んだことはなく、ただ文楽つながりで読んでみました…





「人形が泣く、人が泣く、文楽。世界中が大注目!知るほどに奥深い〝BUNRAKU〟の楽しみ方をずずずいっとご案内いたします!」(帯より)
著者の中本さんは、舞台が大好きで、特に宝塚歌劇と文楽の世界を熱烈に愛してる人らしい。2008年発刊当…





「文楽に懸ける男たち・勘十郎&玉女が贈る文楽案内本」(帯より)
三浦しをん「仏果を得ず」で文楽の面白さに惹かれたので、しばらく集中して文楽関係の本を読んでいきたい。…





「高校の修学旅行で人形浄瑠璃・文楽を観劇した健は、義太夫を語る大夫のエネルギーに圧倒される。〜若手大夫の成長を描く青春小説」(裏表紙より)
確かに青春小説であるけれども、私たちが日本の伝統芸能の一つ人形浄瑠璃〜文楽に興味を持ち、入り込むため…





「〜恐ろしさを恐ろしさを通して描出することはやめておこう、それは日本人がやってきたことだから、そうではなく、この恐ろしさを灰のなかから甦らせるのだ、〜」(文中から)
この映画を何年も前に観たことがあって、何が何だかよくわからず途中で観るのをやめてしまいました。ただマ…




「〜漂白することで異界と出会いリセットする能世界、そして日本文化を、作品を通じて解き明かす。」(裏表紙より)
作者・安田登は初見の人です。能楽師であるけども、シテ方、囃子方や流派など色々あるなかで、下掛宝生流(…




『〜「祖法大事」と変革の波に乗り遅れていくさま・・・幕府崩壊の遠因となった愚劣な政治に迫る!』(裏表紙より)
内容は 【1】アイヌ民族のルーツと展開編 【2】幕末維新への胎動〜①国学の成立と展開編②幕府…






昨年末のネットニュースでこの本のことを書いてあって知りました。
はじめに「新津春子さん」についてNHK「プロフェッショナル仕事の流儀」ディレクター築山卓観が書いてい…




中国や韓国、日本の左翼系メディアが日本の歴史認識を問う時に、「ドイツはきちんと謝罪したのに」とか「ドイツは戦後補償もした、それにひきかえ日本は・・・」という根拠となる演説であるという。
今、「膨張するドイツの衝撃」(西尾幹二・川口マーン惠美)を読んでいるのですが、その中にこの演説のこと…





「日本のある種の愚かな漁夫たち、古典文学に唯物弁証法を適用しようとしたりしている一部の国文学者たちは、変色した深海魚の色を本来の肌色だと、われわれに思いこませようとしている」(by三島由紀夫)
この本はキーンの「私と20世紀のクロニクル」の吉田健一との交流の中に出てくる。【キーンが東京の嶋中鵬…




徳川幕府の崩壊は、薩長の武力のみならず、もう一つの大きな要因があった〜通貨流出である。米外交官ハリス、駐日英国代表オールコックの知られざる赤裸々な姿を描く。(裏カバーより)
読んでいての率直な感じは「こりゃ小説じゃないな」ということでした。面白くないということではなく、物語…




「1666年、ソ連崩壊は既に運命づけられていた。〜宗教の観点から切り込み、長らくタブーとされてきた古儀式派(分離派)の存在に挑んだ、新しいロシア史」(帯カバーより)
「米原万里、そしてロシア」の中に、下斗米伸夫「1666年のロシア崩壊」という短い評論がありました。切…




「俳句や短歌は、もうやがて二千年前から日本人は使ってきていて、それはほかの国にはない現象です。これは日本の詩歌の一つの魅力で、そして日本の誇るべきことだと思います」(ドナルド・キーン)
この本は福岡ユネスコ協会における講演をまとめたものです。全体で50数ページの薄いものです。 ①ドナ…





2006年読売新聞に一年間連載していたものをまとめたものです。
以前読んだ「古典の楽しみ〜私の日本文学」で、ドナルド・キーンは大まかな日本文学への関わり方を書いてい…





『「新世代のボルヘス」と呼ぶには早すぎるかもしれないが、彼がトップ候補であることに異論はないはずだ。』(New York Times 書評)
みなさんのレビューに惹かれて読んでみました。 ゾラン・ジフコヴィッチは初めて知った作家です。レビュ…




米原万里を入り口としてロシアを語っている本です
寒い地域で生まれた人間と暖かい地域で地域で生まれた人間とは、汗腺の数が違うと聞いたことがある。したが…





「〜何かひとつ出来るたび うおおーと大きな声で叫びたくなる 当たり前のことが 奇跡のように思える 心の底から喜びが湧き立ち 感謝せずにはいられない あなたがいるから わたしは幸せのかけら拾いの名人になれた」
表と裏の表紙に健康そうな娘さんの笑顔の写真が載っている。原マリナさんだ。 anzu_ameさんのレ…





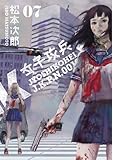
「鋼鉄の少女達は戦争の最前線へと旅立つ、異次元の果てで見つけた〝真実〟とは?」(裏カバーより)
ざっくりとしたアウトラインを書きます。(第七巻で完結です) 舞台設定は未来。 人類が百年かかって…




〝ゴーゴリの『外套』は生活のくすんだ模様に黒孔を穿つグロテスクにも物凄い悪夢である。〜創造的な読者が必要なのだ。これはそうした読者のための物語である。〟(V・ナボコフ「仮面の神化」)
あらすじは、簡単にいえば、サンクトペテルブルクの〝ある局〟の小官吏・文書官アカーキイ・アカーキウィッ…




「後継と血統問題に絶えず悩まされてきた歴代将軍の裏事情と、将軍交代をめぐる水面下の暗闘の内幕を探る」(裏カバーより)
この本は各将軍の継承の部分に主にスポットを当てて書いています。十五代将軍一人一人について、一人で書く…