お家賃ですけど





能町の25歳から27歳の日常の中で出会った理想の家と愛すべき人々への偏愛・執着を記録した自叙伝風小説(裏カバーより)
いい、この人の文章すごくいい。穏やかな考え方や小さなことに喜びを見いだす目のつけ方も好き。西村賢太の…

本が好き! 1級
書評数:203 件
得票数:3446 票
2009年10月から母の介護に関わってきましたが、四月末に母は旅立ちました。暫くはレビューを挙げるのを控えたいと思います。喪に服するというよりも六年以上に渡って内向きに生きてきたので、読書数を減らして運動したりアルバイトでもいいから仕事してそれらに没頭したくなりました。いずれまた参加させていただきます。
2016.5.4(2014.8.10初投稿)
⭐️5・・・買って手元に置いときたい。刺激受けました。
⭐️4・・・読んで良かった。読書の喜びを感じる。
⭐️3・・・ウン、なるほど。参考になりました。
⭐️2・・・感心しません。最後まで読み続けるのを悩む。
⭐️1・・・読めません。基本的にレビューしません。





能町の25歳から27歳の日常の中で出会った理想の家と愛すべき人々への偏愛・執着を記録した自叙伝風小説(裏カバーより)
いい、この人の文章すごくいい。穏やかな考え方や小さなことに喜びを見いだす目のつけ方も好き。西村賢太の…





大正時代の不遇な作家・藤澤清造の没後弟子を名乗って、全集刊行や追悼会に情熱を傾ける一方、同居女性とのやるせない生活を描く。
西村賢太は何冊か積読本ありましたが、きちんと読んだのは初めてでした。内容は「墓前生活」「どうで死ぬ身…




「オーブランの少女」「仮面」「大雨とトマト」「片思い」「氷の皇国」で描かれるのは異なる場所、異なる時代を舞台にしての少女たちの秘密です。
みなさんの「戦場のコックたち」のレビューが面白かったので読もうと思いましたが、「345ページ、しかも…






文士・文壇という言葉が生きていた時代、編集者として長年接した作家の素顔、思い出の数々を卓越した記憶力と観察眼で、昭和文壇の一側面を綴る(帯カバーより)
伊吹和子・・・・1929~2015 京都生まれ。京都大学文学部国語学国文学研究室勤務を経て195…





西村賢太の座持ちの良さもあって、気持ちのいい対談です。
自分は基本的には内向的であるし人づきあいも積極的にしない方なんですけど、若い頃から人の話を聞くのは好…




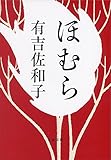
『面白くなければ始まらないわ、小説ですもの。あなたが面白いって言ってくれれば、それでいいのよ」(有吉佐和子が編集者・伊吹和子にいった言葉)
「ほむら」「赤猪子物語」「千姫桜」「紫絵」「薬湯便覧由来」「第八戒」「落陽」「石の庭」の八編からなる…





日本が近代国家としてスタートするにあたり、天皇を親とする〈日本人〉の民族意識を形作ったのは、近代的な法制度や統治機構ではなく、浪花節芸人の発する《声》だった。(カバーより)
先日の「桃中軒雲右衛門・俺の喉 一声千両」を読んでから、〝浪花節〟や〝声〟に焦点を当てた本を読みた…





『安部公房全集』編集に携わる経験を持って、世界的作家安部公房の思想の軌跡と夫妻の歴史をひとり娘・ねりが描く。
山口果林の時も同じなんですけど、自分が知りたいのは身近にいた人間のその人でしか知りえないような人間像…





注目した記事 ①ハリルホジッチ「日本には革命が必要だ」 ②手倉森誠「リオ経由ロシア行きのマスタープラン ③ハビエル・アギーレ「あれから一年が経った。色々と話そう」ほか
ハリルホジッチが日本チームにとっていい監督なのかどうかは自分はまだ分からない。すごく熱心だし理論家だ…





「貧民街」で生まれた「浪曲」を、皇族の御前で演った男!その生涯を曾孫〜岡本和明〜が愛情こめて描いた伝記読み物決定版(帯より)
浪花節は以前好きで何人かのCDを買って聴いてました。しかし、その時は桃中軒雲右衛門のことは知らず、広…





安部公房と山口果林の二十数年の交流の記録
安部公房(1924~1993)大正13年生まれか・・・・。 山口果林(1947~)・・・団塊の世代…




守られた味方からは「伝説」と尊敬され、敵軍からは「悪魔」と恐れられたクリス・カイルは、はたして英雄なのか?殺人者なのか?(裏カバーより)
実際の戦闘現場であるイラクでのあれこれよりも、クリス・カイルの子供時代や大学での牧場でのアルバイト時…






「地唄の世界を舞台に描かれる芸の継承、父娘の確執ー23歳有吉佐和子の圧倒的筆力!」(帯カバーより)
本を読み終えてしまうのが悔しく感じるほど、面白いものでした。 地唄界の長老、大検校菊沢寿久。そして…





「残れとは思うも愚か埋み火の消(け)ぬま仇なる朽木書きして」(近松の辞世句)
近松門左衛門の生涯を描いた小説です。上下の印象記とします。近松門左衛門に関しての資料は少なくその生涯…






近世文学において西鶴、芭蕉と並び称されながら、近松門左衛門の生涯は謎に満ちている。赤穂藩御用に徹した謎の10年とは?スペインとの関係は?300年の「口外無用」の禁を破って九代目が明かす謎。
【近松門左衛門】(1653~1724)〈wikiを参考に簡単にまとめてます〉 江戸時代前期・元禄期…





〜有吉佐和子(1931~1984)の初期の名作『地唄』をはじめ、『墨』『黒衣』『人形浄瑠璃』など、日本の伝統的な芸の世界を舞台にした作品・・・・(裏表紙より)
四編とも面白いものでした。『人形浄瑠璃』を読みたくて、この本を読んだのですが、表題作『地唄』はのちの…





「大正から戦後にかけて、芸道一筋に生きる男と愛に生きる女を描く波瀾万丈の一代記」(裏表紙から)
この本の主人公・茜と三味線弾き・露沢清太郎(のちの徳兵衛)は、四代目・鶴澤清六(1889~1960)…





九歳で文楽に入門しのちに人間国宝へと登りつめた女形の人形遣い・二代目桐竹紋十郎とそれを取り巻く女性たち、そして紋十郎の弟子・染吉〜蝶二郎とその女性たちの姿を描く。
瀬戸内晴美(寂聴)の作品を読むのは初めてですが、人形浄瑠璃の世界を描いた小説として調べると、まずこの…





「愛情こもる三島由紀夫論を中心に近代文学の黎明、鴎外、啄木から、戦後の大江健三郎まで、近代日本の作家と作品を語る鮮烈な文学論集」(裏表紙より)
内容は、森鴎外、正岡子規、石川啄木、谷崎潤一郎、川端康成、太宰治、三島由紀夫、安部公房、大江健三郎な…





「ロダンと花子との面会は世界文化史上一つの目印であろう。西洋人が東洋人を見て、魂まで読めて美術にそれを伝えたことは初めてであろう」(ドナルド・キーン)
今ドナルド・キーンの「日本の作家」を読んでいるのですが、その初っ端に『鴎外の「花子」をめぐって』とい…