カントの批判哲学




哲学者、國分功一郎先生の翻訳によるジル・ドゥルーズがカントの3つの主著、『純粋理性批判』『実践理性批判』『判断力批判』を読み直したといわれる本書はかなりの力業であることを読みながら痛感しました。
本書は現代哲学者であるジル・ドゥルーズが、近代哲学の祖といわれるカントの主著である『純粋理性批判』『…

本が好き! 1級
書評数:2673 件
得票数:40314 票
有坂汀です。偶然立ち寄ったので始めてみることにしました。ここでは私が現在メインで運営しているブログ『誇りを失った豚は、喰われるしかない。』であげた書評をさらにアレンジしてアップしております。




哲学者、國分功一郎先生の翻訳によるジル・ドゥルーズがカントの3つの主著、『純粋理性批判』『実践理性批判』『判断力批判』を読み直したといわれる本書はかなりの力業であることを読みながら痛感しました。
本書は現代哲学者であるジル・ドゥルーズが、近代哲学の祖といわれるカントの主著である『純粋理性批判』『…






ウォール街の歴史のなかで、もっとも成功したファンドマネジャーのひとりであるマイケル・スタインハルト氏の自叙伝です。徒手空拳の彼が巨万の富をつかみ、また慈善活動にもいそしむ姿が描かれております。
この本をはじめて読んだのは大学時代で「旧タイトル」のバージョンでありました。筆者であるマイケル・スタ…





体験を売ることを標榜する「エクスペリエンス・マーケティング」を主催するマーケティング・コンサルタントの藤村正宏氏が伝授する企画書・提案書の書き方です。「伝わる」文書とはこういう風に書くものかと…。
僕は今までに上梓した書籍からツイートにいたるまで、長短や内容を問わず、さまざまな文章を書いてまいりま…




日本国民が国家から押しつけられた借金の原因は歴史的人脈にあった、ということを鋭く描き出した記録です。素人考えではこういうことを書くと色々と『不利益』を被るだろうなと思うのですが、その勇気はすごいです。
よく、選挙が近くなると政治家たちが選挙カーに乗って 「自分に清き一票をよろしくお願いします!」 …





作家、梁石日の自伝的な小説であります。『血と骨』の世界が筆者の分身である少年の目線で描かれ、戦中戦後の時代感覚と、激動の中で生きる人々の「息遣い」が聞こえてくるような濃密な小説であります。
本書は作家、梁石日の代表作である『血と骨』の世界を作者の分身である少年時代の作者の視点で書いた自伝的…






本書は芥川賞作家、西村賢太先生による初めての長編小説です。中学を卒業して以来、場当たり的なその日暮らしをしてきた北町貫多。19歳を迎え、心機一転を図る為に横浜に流れて新しい職と片思いの相手を見つけ…。
無頼派芥川賞作家、西村賢太先生による初めての長編小説です。西村氏が「あとがき」で記しているのですが、…






哲学者・國分功一郎先生が記すジル・ドゥルーズの研究書です。ドゥルーズの方法と対象を、國分先生が精緻に分析し、その実像に鋭く迫ったものですが、お読みになる場合には「格闘する」と言う言葉が当てはまります。
正直なところを言ってしまえば、僕は國分功一郎先生の本に出会わなければ、ジル・ドゥルーズの哲学に関心を…





『ペンブックス16 キリスト教とは何か』の第2巻になります。ここではキリスト教が生み出した文化。絵画や教会や音楽。さらには巡礼地などが紹介されており、「世界宗教」とも言うべき圧倒的な影響力を思わせます。
本書は『ペンブックス16 キリスト教とは何か』の第2巻になります。「世界宗教」であるキリスト教の姿を…



本書が世に問われたのが2002年。筆者が提示した問題がどこまで変わったかはわかりませんが、若者にまつわる「危機」の本質を、経済学・社会学・家族心理学の視点から指摘し、新たな方向性を示唆する本です。
まぁ、そんなこって。本書が世に問われたのは2002年の話。それから時は流れて本書にかかれたことからは…
![]()





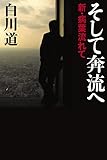
作家。白川道先生の自伝的大河小説『病葉流れて』シリーズです。ここでは広告代理店のサラリーマン生活に倦怠感を覚えた主人公の梨田雅之が一丸という男に導かれる様にして株の世界に飛び込んでいく姿が描かれます。
本書は献本御礼。 僕は数年もの歳月を要して作家。白川道先生の小説やエッセイをすべて読破してまいりま…






本書はエドワード・スノーデン氏から極秘ファイルを託された一人であるグレン・グリーンウォルドによる当事者手記です。こちらでは公開までの顛末のほかに、未公開の機密文書を多数収録されています。
エドワード・スノーデン氏の内部告発によって明るみに出た膨大な機密文書と、アメリカ合衆国が国ぐるみで行…





お客様満足、共生、勤勉、誠実、信用…。現代の商習慣にも十分に伝わる江戸時代の豪商達が残した『思想』をまとめて現代に紹介する一冊です。久しぶりに読み返してみて気づかされることが多い一冊でした。
僕は本書を読んでいたことがきっかけで、とあるセミナーに出席した際、講師が 「江戸時代の商家では加持…

「ヤンキー先生、さようなら」これは現在政治家「センセイ」としてご活躍する義家弘介氏の自伝です。僕は彼と精神的に訣別することで、「大人」になることができたのかもしれないと、現在では思っています。
僕が本書を最初に読んだのは20歳前後の事で、俳優の竹野内豊氏が主演でドラマ化された『ヤンキー母校に帰…



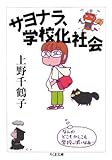
本書は社会学者の上野千鶴子先生が当事者として大学教育を批判的に語った書き下ろしのエッセイでございます。「多元的な価値を見いだし、生き抜く「知恵」をつけよう。」というメッセージは上野先生ならではでした。
この本を初めて読んだのは、もうずいぶんと昔の話になりますが、サラサラと読めます。で、今回再読して大学…





情報学に深く関わってきた大地人者である筆者が記す「ウェブ2.0」の世界とは? 本書が書かれたことからはさらに事象は進化しておりますが、もう一度「情報」とは何かと言うことをを考え直すために必要な一冊です。
僕もささやかながらこうして駄文を綴ることによって、「ウェブ2.0」の恩恵を受けている1人ではあります…




『検索』と言うものが世の中に蔓延していく中で自らものを『考える』事が退化していき、「クウキ」を読むことがますます重要になってくる。そういう世の中に懐疑を持つ筆者が綴る本です。まぁ、賛同と疑問が半々で。
本書に書かれている内容のほとんどは『空気(ここでは『クウキ』とも表示される)を読む』ことを強要するこ…






比叡山延暦寺の千日回峰行を2度満行した行者として有名な故・酒井雄哉大僧正のエッセイです。初めて読んだのはかなり前の話ですが、再読して改めてその言葉の重みを知りました。生前にお会いしたかったです。
天台宗の中でも『究極の荒行』として知られている「千日回峰行」を2度にわたって満行し、大阿闍梨として広…





哲学者・中島義道先生が七転八倒のウィーン留学より10年。大学教授となって妻子にも恵まれ、功成り名を遂げた中島先生が再度訪れたウィーンで目の当たりにした「変化」とは…。しみじみとしてしまいました。
本書は哲学者・中島義道先生は『ウィーン愛憎―ヨーロッパ精神との格闘 (中公新書)』で、「ヨーロッパ中…





ホリエモンとオタキング。このぶっ飛んだ組み合わせが縦横無尽に語りつくす現状を打破するための「考え方」を提示する対談であります。動画で見るか、活字で見るのかは受け手の判断によるかと思われますが…。
本書の基となっているのは2010年5月12日、2011年4月5日、2013年6月18日に都内で行われ…

本書は超巨大船から超高速船まで、その仕組みとメカニズムをテクストと豊富な図版や写真が掲載されており、興味のある方や資料としてお使いになりたい場合は最適な一冊であります。ただ、個人的には…。
本書は船がいかに建造され、動くのかと言うメカニズムを解説に加えて、詳細な図版と写真を用い、解説を行っ…