アレント入門





ドイツの良心的な善良な市民が、なぜユダヤ人の迫害に目をつぶり、ナチスの道徳規範を受け入れたのか。
本書は思想家の「入門もの」であるが、ハンナ・アーレントがドイツを離れて亡命するきっかけに切り口をし…

本が好き! 1級
書評数:103 件
得票数:981 票
ライフワークの沖縄関係を中心に人文系を読んでいます。





ドイツの良心的な善良な市民が、なぜユダヤ人の迫害に目をつぶり、ナチスの道徳規範を受け入れたのか。
本書は思想家の「入門もの」であるが、ハンナ・アーレントがドイツを離れて亡命するきっかけに切り口をし…






核技術の問題と人間が思惟から逃げているという問題はつながっている。
原子力の平和利用が夢のように支持された1950年代に、核戦争の脅威という観点から警鐘を鳴らした知識…





津島佑子の遺作『ジャッカ・ドフニ 海の記憶の物語』(2016年)は、なぜ、3・11後の状況とアイヌの「生存の歴史」を結びつけながら書かれたか。
『津島佑子と「アイヌ文学」 pre-traslation の否定とファシズムへの抵抗』 著者:岡…






なぜ「当事者性」は守られなければならないのか。それは「同情」も「共感」も困難であるがゆえに、「非当時者」とのあいだに線を引くことについて自覚的であるべきだからだ。
「裸足で逃げる」とは、なんと沖縄の「現実」に刺さるタイトルだろう。あの亜熱帯の夜の、生暖かい、しか…




ただめし券に名前はない。施す側と施される側が対面しないことで、むしろ想像力が増す螺旋形のコミュニケーション。
1日1メニュー、まかない、ただめし、あつらえ、さしいれといった、シンプルで「懐かしい」定食屋の開業…





東京山谷にある玉姫公園で黒布が垂らされ、そこで男たちはポーズをとり、著者が撮影するフィルムにおさまる。
東京山谷にある玉姫公園で黒布が垂らされ即席の青空写真館が現れる。そこで男たちはポーズをとり、著者が…




優子と痴漢のコミュニケーションでは、「愛」と「心」が区別される。
「直感で蒲田に住むことにした。」という書き出しで始まる小説の主人公、橘優子は、かつて新聞社に就職し…




これを見たら家族は驚き悲しむだろうと「同情」する。それなら、自分の肉親に対してはどうだったのか。
山形県にある佐藤病院の重度痴呆症病棟の長期取材である。半分ほど読み進めたところで、先を読む意欲が湧…






文学批評は柄谷にとって、「抑圧されたものの回帰」である。
この20年とは、かつての文学批評の仕事をやめて哲学的なそれへ移る時期に重なる。しかし、その「変遷」…





あなたがどこかのグループの一員である必要はなく、「ただ来て、ただ座って、ご飯を食べていたらそれでいい」。
未来食堂のコンセプトは、「あなたの『ふつう』をあつらえる」だという。通常のメニューに加えて、希望す…






安吾の身体の「移動」とは、「根を下ろすこと」は「根」から突き放されることであるという逆説の、一回一回の実践といえよう。
本書の言いつくせぬ魅力についてつらつらと思い巡らすのが愉しい。安吾の「無頼」ぶりが側近の妻によって…





マヌケな場所の各国の事例が魅力的に紹介され、それらが増殖し、世界同時革命を起こすとする世界最大のマヌケ宣言が囁かれる。
「マヌケ」とは何だろう?本書を一読後、マヌケについての思想的意味を問うというマヌケなことを考えてみ…



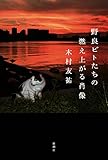
ホームレス男性の個を的確に追いながら、グローバリズム、排外主義、アベノミクスなどへの社会批判を展開している。
多摩川の土手は私にとって原風景といってよい。実家に戻った数年前、久しぶりにそのパノラマを目にしよう…





漱石も参加した俳句結社の句会において、子規とその友人たちは「デモクラティック」な言説空間の創出を生み出していった。
正岡子規の「写生」概念の生成過程を夏目漱石との創造的「交換」をも交え読み解く試み。自分に俳句の教養…




認知症当事者や家族が気軽にお茶を飲みながら、不安や悩みを打ち明けることができる場所。
認知症カフェとは、認知症当事者や家族が気軽にお茶を飲みながら、不安や悩みを打ち明けることができる場…





逃げるのは、幸せになって復讐するという〈革命〉。
あまりにも刺激的な映画を観て原作も気になる。そういうタイプの映画だった。原作は一部をごっそりとカッ…




著者は蒲田の魅力を、新しいもの、異質なものに対して抵抗のない多様性だという。
「危ない」「汚い」「騒がしい」というネガティブなイメージをもたれる蒲田を、地元愛溢れる著者が「そう…






小森陽一は『猫』をどう読んでいるか。
岩波書店の全集刊行などで漱石リバイバルがあった1990年代、雑誌『漱石研究』の編集など、著者はその…






《写生文に現れる語り手は主人公や登場人物の自我を柔らかく包み込む超自我であるといってもいいだろうか》
国民的作家のデビュー作について考えたいことがあり、久方ぶりに本書を紐解く。 『吾輩は猫である…





安吾よ、あなたは自身をも突き放すと言っておきながら、確かに登場人物たちは突き放されているかもしれないが、誰がそうしたのかを明らかにしていないではないか。
坂口安吾といえば、「戦争に負けたから堕ちるのではないのだ。人間だから堕ちるのであり、生きてゐるから…