「オピニオン」の政治思想史: 国家を問い直す




オピニオンといっても普通の名詞での「意見」といった意味ではないようです。政治思想の中では特別な位置づけがあるようで、それについて解説されています。
オピニオンといえば意見とか世論といった意味の言葉だと思っていましたが、どうやら政治思想の専門用語とし…

本が好き! 1級
書評数:2616 件
得票数:37717 票
小説など心理描写は苦手という、年寄りで、科学や歴史、政治経済などの本に特化したような読書傾向です。
熊本県の片田舎でブラブラしています。
コメント大歓迎です。ご感想をお聞かせください。




オピニオンといっても普通の名詞での「意見」といった意味ではないようです。政治思想の中では特別な位置づけがあるようで、それについて解説されています。
オピニオンといえば意見とか世論といった意味の言葉だと思っていましたが、どうやら政治思想の専門用語とし…


題名だけを見ると環境危機の警告のようですが、実際はテクノロジー楽天主義ともいえる内容です。
この本の題名(和訳)からは地球の環境破壊や資源枯渇などで人類の生存が難しくなる事態に対しての記述かと…




少し昔の時代でもその生活の詳細はとても想像できません。それが中世となれば。
歴史小説などで読んだことがあっても、実際に昔の生活というものがどういうものかということは、なかなか想…




今では文豪と呼ばれるような作家はいなくなりましたが、かつては肩を並べて文壇を引っ張っていました。そういった文豪たちはどんな家に住んでいたのか。
最近はなかなか「文豪」と呼ばれるにふさわしい作家が居ないかもしれませんが、かつては確かに「文豪」とい…





中国が日本を追い抜きアメリカと肩を並べる。今では誰もが実感していることですが、本書出版の2012年にはまだ「不愉快な現実」という認識でした。
何が「不愉快」なのか。 本書ではそれが「中国がすでに日本を追い越してアメリカと対抗する地位につ…





桑田佳祐、もちろんサザンオールスターズの桑田君です。その「何を言っているのかよく分からない」歌詞にどういう意味が込められているのか。
桑田佳祐といえばもちろんサザンオールスターズのリーダーおよびボーカルとして、1978年のデビュー以来…




バビロンという名は象徴的に使われていますが、その原点ともいえるメソポタミア文明のバビロンの話です。
古代メソポタミア文明はシュメール人によって始められましたが、その後セム系と考えられるアムル人によりバ…




キリスト教は一神教のはずですが、天使や悪魔などといったものもたくさん存在します。
天使と言われて浮かぶイメージは背中に羽根のある子どもの姿でしょうか。 でも、それはギリシア・ローマ…




旅にトラブルはつきもの。それでもその対処術というものを知っておくと慌てないで済むかもしれません。
日本の鉄道は信頼性が高いことでは世界有数ですが、それでも旅をしていると色々なトラブルにあうことがあり…




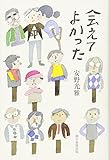
画家の安野光雅さんが親交のあった人々について週刊朝日に連載したエッセーをまとめたものです。交際範囲の広いことに驚きます。
画家で絵本や本の装丁も数多く作成していた安野光雅さんが、親交のあった人々についてのエッセーを週刊朝日…




作家でも億を稼げる人は何人かはいるようですが、ほとんどの人はごく少ない稼ぎです。その内情を明かします。
書名はこうありますが、もちろん「億稼いでいる」作家も数名はいるようです。 しかしそれ以外の作家と呼…





書く字が汚いということで苦労し続けてきた著者の思いのあれこれです。私も一緒でした。
著者の新保さんは編集者兼ライターということですが、子供の頃から「字が汚い」と言われ自分でも自覚し悩み…





ちょっと軽い感じの題名ですが、副題「現代社会学単語帳」という方が内容をよく示しています。社会学を研究する上で必要な単語の意味を解説したものです。
何か軽い感じの題名ですが、副題の「現代社会学単語帳」という方が内容を良く表しています。 編著者…

「草食化」という言葉にひかれて読むと戸惑うかもしれません。あくまでも統計データというものを詳しく解析するという内容です。
本書の内容をうまく表していないような題名で、これに惑わされて読む人もいるかもしれませんが、副題の方が…




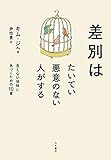
自分は差別なんてしないと言える人はいるのでしょうか。深く考えなくても結構そういった意識はありそうです。
「差別」をする人は悪人で普通の人ではないといったイメージがあるとしたら、どうやら大きな間違いをするよ…




現代人の持っている「昔の文化」というイメージにはかなり事実と違うものがありそうです。
有職故実(ゆうそくこじつ)とは朝廷や公家などの行事やしきたり、その他の事を研究することですが、その有…


SDGsということが言われますが、その説明を聞いても何か釈然としないものが残ります。これらの旗振りをしてきたとも言える著者の説明を読めばわかるかと思いましたが。
この本はそのSDGsに深く関わってきた南さん、稲場さんが書いたということで、その背景や経緯などが少し…





菌根といってもあまりなじみは無いかもしれませんが、マツタケは菌根菌だということは少しは知られているかもしれません。実は他にも多くの植物が菌根菌と共生しています。
菌根といってもあまり馴染みはないかもしれませんが、マツタケはアカマツと共生しているという話は誰もが聞…



ロシアのウクライナ侵攻以来、その戦争などに関する本は色々と出版されました。この本はちょっと違うようで、ウクライナは釣りの餌のようです。
ウクライナ紛争はアメリカ側の報道ではロシアの一方的な侵略かのように報じられていますが、ロシア側にも事…





昔ながらの方言はどんどんと消えていくと言われます。一方、若い人たちがあらたにネオ方言ともいえるものを作っています。方言学というのはまだまだやる価値があるよということを学生さんたちに示しています。
日本語はその使われている地域の独立性が強いためか方言が各地で発展し独特のものとなっていました。 し…