藤森照信の建築探偵放浪記―風の向くまま気の向くまま





世界の名建築を検証する藤森探偵の推理と独断が楽しい
月刊『積算資料』連載の「建築あれこれ探偵団がゆく」の単行本化。連載は2011年から継続中で、世界の…

本が好き! 1級
書評数:280 件
得票数:3479 票
高校の国語教員。現代文専門。教科書や問題集の編集にも関わっている関係で、大学入試に出そうな本、問題化できるような文章を意識して読むこと多し。個人的な好みで、トルコやロシアについての本も多く読みます。





世界の名建築を検証する藤森探偵の推理と独断が楽しい
月刊『積算資料』連載の「建築あれこれ探偵団がゆく」の単行本化。連載は2011年から継続中で、世界の…




憧れのアルタイから遥かな世界へ
「アルタイ」にぼんやりした憧れを抱いています。ただしその位置も実際の姿もはっきりせず、さらに遥かに…






AIブームの本質を斬る決定打。AI怖れるに足らず、AI信奉者こそ危険な存在。
1か月半前に同著者の『ビッグデータと人工知能』を絶賛しました。人間を機械と同等に見なしてシンギュラ…




ロシアにとっての愛国と国民統合。日本でも愛国と政権支持が混同されているのでは。
若手研究者が愛国主義をキーワードにロシアの国民統合を分析します。主な取材や情報が2012年の大統領…





移民政策に関わる論文集。簡潔な文章が並び、広い視野に目配りの効いた1冊。
移民政策を論じる学会の論文集です。多数の著者が名を連ねるように、最大でも6ページ程度の短い論文が多…




世界を巡る永遠の「フーテン老人」と、アジアの岡倉天心。
筆者の『フーテン老人世界遊び歩記』は1998年の刊行でした。本書の前書きでは「大変面白い」のに「部…




「はーい、こちら現場です。これから江戸の町をリポートします。」
江戸時代にタイムスリップした現代人の体験を、ストーリー仕立てで綴る不思議な書き方です。設定は安易で…




オスマン帝国の統治とその崩壊をたどる。現在とは別の形の国家がありえたはず。
現在、地球上に存在する国家はどれも似たような姿です。民主主義を標榜し国民が第一という建前の国民国家…





石田千の短編集。表題作「ヲトメノイノリ」は落語を意識した佳作。ゆるさとベタな設定が妙に魅力的。
私の中ではエッセイのイメージが強い石田千の短編集、彼女の小説は初めてです。10作品が並ぶうち表題作…






黒田龍之助の新刊1-ロシア語学校の歴史と、見返りのない語学学習のよろこび
黒田龍之助の言語エッセイが2冊続けて刊行された。スラブ系諸語を専門に、言語学や外国語学習を楽しく語…





黒田龍之助の新刊2-外国語学習に会話よりも物語を
黒田龍之助の新刊語学エッセイの2冊目。こちらは既にタイトルに彼の思いが詰まっている。本書の「はじめ…





アリストテレスやカントの友情論から現代へ。家族の希薄化と高齢化・ジェンダー・SNSで変わる友達像。
哲学者が語る友情は往々にして理想論だ。友情のあるべき姿や理想の友人が謳い上げられても、そんなものは…





ビジネス書として書かれたのが不思議。アフリカの少数民族をかっこよく写すフォトグラファーは、根っからのゲージツ家かも。
本書は、自らも脱いでアフリカの少数民族の中に入り、彼らのかっこよさを撮るヨシダナギに、ビジネス書を…





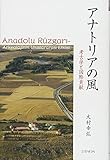
トルコの大地で現地に溶け込みながら5500年の歴史を掘る。
ヒッタイトの首都とされるボアズキョイに近いアラジャホユック、人類最初の街とも言われるチャタルヒュユ…




クラシック音楽にまつわる人物・時代・場所を、さらに易しく語る。
著者の『音楽の聴き方』(中公新書)は、平易な言葉と斬新な発想でクラシックを語り、スノッブに傾きがち…






古今東西を自在に駆け巡り、「ヒト」の文化を探る比較民俗学者の発想。
タイトル『遠国の春』は、柳田国男『雪国の春』にちなむ。柳田民俗学の「雪国」が国内に限られたのに対し…




「脱システム」というキーワードから冒険を論じるストイックな評論と「はじめてのおつかい」。
かつてチベットのヤル・ツアンポー渓谷を踏破し、最近では極夜の北極圏に挑んだ冒険家の筆者。自身の体験…




昭和から平成の日本、時代の流れの中の日本人を群像をとして描く試み
ひとつの夢から物語は始まる。人のいないスーパーマーケットから、車の姿が見えない夜の街へ。するとそこ…





1975年の夏休み、浦和高等学校1年9組佐藤優君は東欧・ソ連を旅する
(上下巻合わせての感想です) 現代の「知の怪物」佐藤優氏が高校1年の夏に敢行した42…





英国の特派員が歩く中国辺境。生身の人々の中に入り、北京政府との揺れる関係を見る。
新疆ウイグル自治区、チベット自治区、雲南省、東北部。これらの地は中国の辺境であるとともに、近現代に…