人口減少と鉄道




がんばれ、鉄道。元JR九州会長の「鉄」で生きる「道」。
著者は車両設計で国鉄時代に入社した人物だ。民営化後はJR九州の初代社長に就任、会長も務めて2002…

本が好き! 1級
書評数:280 件
得票数:3479 票
高校の国語教員。現代文専門。教科書や問題集の編集にも関わっている関係で、大学入試に出そうな本、問題化できるような文章を意識して読むこと多し。個人的な好みで、トルコやロシアについての本も多く読みます。




がんばれ、鉄道。元JR九州会長の「鉄」で生きる「道」。
著者は車両設計で国鉄時代に入社した人物だ。民営化後はJR九州の初代社長に就任、会長も務めて2002…





ランドスケープデザインをめぐる断章。建築と土木とデザインにまたがりつつ、さらに「何か」を加えること。
ランドスケープデザインは風景を生む営為だ。地盤の設計から始まり、建物はもちろん、その配置や公園的な…





狩猟採集民であるヒトに対する効果的な教育方法。ホモサピエンスは読書に適応しているのか。
人類という種が誕生して以来、私たちはずっと狩猟採集生活を送ってきました。それに比して、農耕を営み、…




ナチスドイツに包囲されたレニングラード、25年前に訪れたレニングラード、そして現在のサンクトペテルブルク。交錯する歴史と音楽の力。
サンクトペテルブルクはロシアの中で特異な都市です。 18世紀前半、ピョートル大帝が築いた人工都…






AI論議にわだかまるモヤモヤが一気に解決。人間を超えるAIを唱える者たちの人間観が浅薄なのだ!
思考力や想像力は人間のアイデンティティです。体力や知覚能力はもともと他の動物より劣っているから、機…



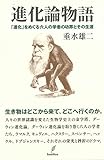
ダーウィンの進化論とその前後の説を、社会との関わりからたどり直す。
研究者も社会の中の人、その研究には時代性や社会が反映します。 地動説の発表をためらったコペルニ…




日本と西欧のファースト・コンタクト。遠来の貴人であり、国を危うくする邪教の徒であり、商人でもあったバテレンとの出会い。
『逝きし世の面影』で、西欧人が見た幕末・明治の日本をみずみずしく描いた渡辺京二氏。しかしそれはセカ…





裸で生まれた人間が、生きる中で身にまとうもの。
8作品所収の短編集を「人が身にまとうもの」というテーマで読んだ。著者の意図に沿う読みかは分からない…





「思い込む力」と「楽しむ力」も備えるオンリーワンのあり方。
きっかけは「オンリーワンになる方法の本を書いてほしい」という依頼だ。個性的であれ、好きなことを仕事…






自動車交通の近未来はいかに? 豊富なデータに基づくうなずける予測
本書をもとに、十数年後のドライブ旅行を予想してみました。 ある週末、自家用車を持たない彼ら…





人と国土から国家を見る。「地政学」を名乗るにふさわしい1冊。
「まちかど」「地政学」「90カ国」「弾丸」。どうもまゆつば物のタイトルです。「地政学」で学術的なも…




機械に過ぎないAIが心を持つはずがない!と言い切りたい。
AIに心が宿る?--そんなはずはありません。所詮AIは機械に過ぎません。人間こそが持つ心を宿すはず…





研修生は働き手。留学生はバイトの掛け持ち。彼らを雇う人手不足の現場。何もしていないに等しい日本の移民政策を放置してはいけない。
桜のシーズンとともに外国人観光客の姿が一層増えた気がします。私の友人でも、ロシアや東欧など、以前は…





蘭学者の共同研究という美談、その中心にいた前野良沢が序文の執筆さえ拒んだという『解体新書』の謎。
オリジナルの杉田玄白『蘭学事始』とともに、菊池寛「蘭学事始」(青空文庫)、吉村昭『冬の鷹』(新潮…




道に迷わなくなった現代人と地図の関係。
初めての街を自分の足に任せて歩くのは楽しい。時間があるなら、最初は地図を持たない散歩をしたい。外国…





日常の中にあるちょっとした冒険から、詩人としての自覚へ。臆病で正直な詩人は、不器用に少しずつ成長していく。
臆病で不器用で正直な詩人が、人との関わりの中へ、小さな初体験を重ねます。 初詣、個人商店の…





私たちとは根本的に異なるムスリムの頭の中をイスラム法によって解剖。
立花隆氏が最新刊(『知的ヒントの見つけ方』文春新書)で、イスラム国がわからないと言っています。「国…





人類学者、今福龍太による寓話集。未来と過去とつながる現在を生き直すために。
22章のうち、奇数章は近未来の都会に生きる「わたし」が語り、偶数章は始原の島に暮らす少年「ノア」を…





多様な顔を持つアフリカは巨大な疑問符。
「未開」の地とされ、果ては「暗黒大陸」と決めつけられ、一部では「希望の大地」とも言われるアフリカで…




新規の顧客開拓よりコアなファンを大切に。社会の変化に対応した、マーケティングの発想の転換。
「ファン」とは「企業やブランド、商品が大切にしている『価値』を支持している人」を指し、その「ファン…