日本語で書くということ

本書は、いかに水村が自覚的な小説家であるか、ということの証左である。
水村美苗の処女作は「続明暗」である。漱石の未完の作から続けて読むと、この作者の凄さがわかる。漱石が書…

本が好き! 1級
書評数:608 件
得票数:3207 票
基本的にベストセラー以外は、なんでも読む雑読派です。活字中毒ですが、最近はアルツ気味で、忘れないようにブログにメモしています。

本書は、いかに水村が自覚的な小説家であるか、ということの証左である。
水村美苗の処女作は「続明暗」である。漱石の未完の作から続けて読むと、この作者の凄さがわかる。漱石が書…

さて本作は、いまの読者に受けるだろうか。いまのところ私の属しているネットの書評サークルに投稿はない。
35年前のベストセラーの続編。田中康夫は、四字熟語ならぬ、四字かな造語(なんクリ、ペログリ、スッチー…

原題は A New History of Life. 21世紀に入って初めて分かったことも含む。恐竜絶滅が隕石衝突によるものだと分かったのが1980年なのだから、地球生命史の研究は新しい知見でいっぱいだ。
著者2人とも、生命は火星に起源し、隕石で地球に運ばれたのだろうと考えている。惑星間パンスペルミア説だ…

近未来、脳間移植手術で海馬を交換するというお話。SFだと考えるのが普通だろうが、本書の体裁は純文学ととらえてほしがっているようにみえる。
海馬は短期記憶にかかわる重要な脳の器官だが、人格そのものではないだろう。だから読み始めると、移植交換…
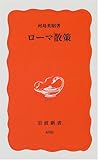
近々ローマを再訪するので本書を読む。3度目だが、いつも深い感慨に捉われる。これはガイド本ではなく秀逸な文学作品である。
内容は正しくは、歴史・文学散策である。 河島は言う。いまは映像の時代であり、視覚から受ける印象…

藤井は、今年少なくとも3冊の本を出している。4月の『大阪都構想が日本を破壊する』『〈凡庸〉という悪魔』、そして7月の本書である。
5月には住民投票で大阪都構想は否決された。橋下構想のインチキを突いた藤井の論述が大きく貢献したのだ。…

私は長い間、柄谷行人という思想家を敬遠してきた。初期の文芸評論の晦渋な文章に辟易したためである。
しかし彼の思想家としての名声は高まるばかりだ。どこかでもう一度柄谷を読まなくてはならないだろうという…

イタリアワインについて書いた著者の前書(2012)。表題はバカっぽいが、内容はマジメ。それをコミカルに描いた好著。TVのイタリア人のおバカタレントとは一線を画す。
この本には書かれていないが、日伊は良く似た歴史をもつ。明治維新とイタリア統一。エマニュエル2世(明治…

今回ボローニャを拠点として、ラヴェンナ、フェッラーラ、モデナと、エミリア・ロマーニャの小都市を街歩きした。
私はエミリア・ロマーニャのワインは、いまいち冴えないという先入観があったのだが、街場のトラットリアに…

ギャッツビー?ギャツビー?
光文社古典新訳文庫の1冊である。09年の最新訳。にもかかわらず先行する6っの既訳との大きな違いがある…

「心身問題は、じつは時間問題である。」
私は、ある時期、哲学というものを無駄話だと思っていたことがある。自然科学こそが世界を解明できるのだ、…

電柱、電線、鉄塔、広告……いかに日本が、みにくい景観に満ち溢れているかを、たくさんの写真で示す。
とにかく自然歴史環境をぶち壊すことが、執念だったとしか思えない。著者は皮肉たっぷりに「せせらぎやコン…

私は白井という論客、話題の「永続敗戦論」、また笠井潔との対談本を読んでも、今ひとつ何が言いたいのか、よく分からない人だった。
「永続敗戦レジーム」などという意味不明な用語を使うせいもある。わかりやすく言えば、日本は対米従属で自…

実に明快なアベノミクス賛成論。ただ高橋は舌鋒鋭すぎるから嫌われるだろう。
池上彰が朝日新聞を批判した記事が不掲載になったころ、高橋の文章も拒否されたという。本書はその全文から…

かつてのソ連邦崩壊と同じように、中国共産党国家の崩壊も間近い。これが本書の主張である。
87歳の著者は10人の助手を使って情報収集しているという。 金融バブルの崩壊はすでに上海株の下…

今揺れに揺れている新国立競技場。
本書は、いちはやく反対を表明した建築家槇文彦の声明文から、派生したシンポジウムなどを収録した小冊子で…

著者は日本での大学教員生活をやめ、文筆一筋に生きることにし、自由の身をまず台湾におく。
2013年秋から2014年春にかけて、台湾の学訪人(客員教授)として招かれたのだ。本書はその滞在記、…

井沢の書いたものを読んできた読者にとっても、半分は既知だろうが、残りは仰天することばかりではないだろうか。
・壬申の乱は、日本国内の百済派(反唐派)と新羅派(親唐派)の代理戦争。天智天皇は天武(実は兄)によっ…

イタリア歴史ミステリー。エーコほど衒学趣味ではなく、ダン・ブラウンのような活劇はないが、知的魅力はたっぷり。
著者をモデルにしたようなボローニャ大学在日本女性をかなめとして展開する、現代、近代、中世の3層の物語…

なんとも奇妙な対談だ。ひとりは並のユダヤ人以上にユダヤ文化を知っている。ひとりは出自はユダヤ人だが日本人以上に宮沢賢治を読んでいる。
お互い日本語で爆弾のようにユダヤ人とは何かを論じ合う。結論は出ない。ヘソが曲がった2人である。いやそ…