休み時間の薬理学





専門で医療系を学ぶ学生には軽すぎたり基本的すぎたりするけども、専門でない人が興味とか教養で薬について概観するには丁度良い水準で書かれているように思う。
テストの薬理学対策に読んだ本だけど、それなりに楽しめた。 同じシリーズの「薬物治療学」に比べる…

本が好き! 1級
書評数:257 件
得票数:1434 票
自然科学、言語、経済、音楽、SF、ミステリー、ラノベ。などなど。
一般向けの科学書が一番多いかと思います。
神経、認知、心理、進化、人工知能。
あまり書評が付いてない本を読み漁る傾向があるようです。
書評書くたびについったで呟いてます。
交流は主についった(@foolon2011)でやってるのでお気軽にフォローどうぞ。





専門で医療系を学ぶ学生には軽すぎたり基本的すぎたりするけども、専門でない人が興味とか教養で薬について概観するには丁度良い水準で書かれているように思う。
テストの薬理学対策に読んだ本だけど、それなりに楽しめた。 同じシリーズの「薬物治療学」に比べる…





興味のある人、といういうよりも、解剖をやる人におすすめかなぁ。 「解剖なんかやらないけど、解剖の成立背景には興味あるよ!」っていう人、いるんだろうか。 いるんならその人も読んだらいいと思う。
興味のある人、といういうよりも、解剖をやる人におすすめかなぁ。 「解剖なんかやらないけど、解剖の成…






生まれてこの方親しんできた日本語ですが、その日本語を通して日本の文化に対する理解が今更ながら深まりました。まさに灯台もと暗しです。
日本語の大家、金田一春彦氏の手による日本語の本です。 この人の名前は父の京介氏と同様に国語辞典で目…




冒頭で筆者が述べてるような「できれば、数学になじみのない方がたにも、数学というものの素顔をわかっていただこうと思ったわけです。」というコンセプトからは、残念ながら遠いと言わざるをえない。
正直に言いますと、たぶんこの本を文字通り半分も理解できなかったように思います。 他の本なりで微分方…

学問と社会のあり方、科学が一人歩きするとどうなるか、「科学的裏付け」とはどうあるべきか、脳をめぐる研究のあり方、・・・そういう問題を考える上でのきっかけとして。
私自身、川島教授にはプラスのイメージを持ちながらも「脳科学」の胡散臭さは否めない、というのがこれまで…





「ヒトの見方」ではまるまる一冊で解剖学を語ってくれてたのですが、この本はそういう本ではなかったようです。 解剖学的なお話はそれほど多くありません。
養老孟司先生のエッセイ集。 東大の解剖学教授をやっていた頃に書かれた文章を集めたものです。文庫本に…





おとぎ話が持つ、読者の心を動かす力。 その正体は何なのか。どうして心を打つのか。 筆者のそうした分析は鋭く、はっとさせられます。
おとぎ話を大人の視点から捉え直そう、っていう本。 ここ数年でおとぎ話はある程度大人の間でも地位を確…




この本、進化論のベーシックなものを押さえてない人には全くもってお勧めできません。ただ、今の進化論の通説を押さえている人が「変わり種」として読む分には非常に面白いです。
うーん。 これは難しい。 この本、進化論のベーシックなものを押さえてない人には全くもってお勧めで…




トピックは広くていいんだけど、どれも簡略化しすぎてごく浅いレベルにとどまってるので、これ自体が知識のストックとして活用できるかというと微妙。
高校で少し生物をかじったくらいの人が読むにはちょうどいいレベルの本。 文系の大学生とか、高校生にお…



普通の人が読んで、「へぇ、病理学ってこういうことやってるのか」っていうのがわかる程度の本。病理学の中身が頭に入るかは別。
情報自体はそこそこの量あるし、情報量に対して価格設定も良いんだけど…うーん… 箇条書きの列挙が中心…

普通の人が興味で読む分には『薬理学』の方で十分に楽しめる気がするのでこの本は基本が分かってる人が各論に行くための橋渡し的な位置。
医歯薬系以外でこの本読もうと思う人いるのかな。 同シリーズの中でも「解剖学」や「生化学」なんかに比…






「脳科学者(Neuroscientist)」を自称する人の胡散臭いイメージを覆すくらいの、好印象な本でした。
久々に「満腹感」が得られる本でした。 いわゆる「脳科学」(学術的な区分でこういう学問は存在しな…



時代ごとにと言っても年代がポンポン飛んでて日本史と世界史を行ったり来たりしてるから、高校の歴史をろくにやってない私なんかはそのエピソードが断片としてしか頭に入らない。
私が歴史について不勉強なせいでしょうか、どうにも最後までテンションが上がらず読み切ってしまいました。…



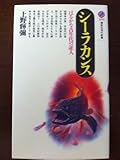
この本が出た当時だったら多分、「シーラカンスに関する話なら、古い話から最新情報までこれ一冊!」という本だったんでしょうけどね……。
丸ごと一冊シーラカンスの一般書とは。 物好きな本を出す人もいたもんです。 シーラカンスについ…





専門でない人には少し難しい内容も、わかりやすく噛み砕いてくれています。要点もよくまとまってる。文量がそんなに多くなくてすぐ読み終わる本ですが、大事なことはすんなりしっかり頭に入るようになってます。
あまりにさっくり読み終わってしまったので3点にしようか迷いましたが…。 本をでかく長くすれば偉いっ…





驚くほど生々しく「現代人」を描いている小説。という印象。よくありそうな日本の平凡な家庭が舞台ですが、それぞれのキャラクターが現代人の典型的なタイプを暗示しているようにも感じる。
意外と分厚いけど、すらすらとテンポ良く一息に読めます。 喉越しが良い、とでも言いましょうか。 …






アメリカという国家のあり方、経済のあり方、民族のあり方について疑問を投げかける内容が多かったように思います。 書いているのがアメリカ在住の日本人なので、日本人の目から書いてくれます。
これは面白い。いろんな意味で。 表題を見て序章を読んだ段階では、「平均的なアメリカ人」の程度の低さ…




この本を通して言っていることはタイトルの通り、「全てといっていいほど多くのものが、実は仮説にすぎないのだ!」ということ。 そして目次を見ればわかるとおり、内容はその論の補強と例示がほぼ全て。
タイトルで思い出したのはポアンカレの「科学と仮説」。 話としては大体そこで出てたものに近いですね。…




高2や浪人生くらいで若干時間を持て余してる人が、息抜きのつもりで読んでみるのなら悪くはないと思う。それから手放しでオススメできるのは人に数学を教える人。
新書としては無難にそこそこちゃんとした本ではある。あるんだけど……。 誰か読んで得するかなぁ、これ…






特にこの本が有用な層は、専門教育を前にした生命系の学生や、生物学に対して意欲のある理系の高校生だと思います。生命系(あるいは生体高分子)の勉強をする上で基本的なことがよくまとまっています。
こういう本に高校生のうちに出会っていたら幸せだったなぁ、と思う本。 でも今読んでも十分に有用な部分…