時をかける少女 〈新装版〉




表題作を含む3編が収められている。どうしてもSFとしてはチープな気がしてしまうんだけど、黎明期としてはこれくらいのアイディアやトリックが驚きの対象だったのでしょうか。
読んだのは新装版じゃなくて、昭和51年初版の古い表紙の方だった↑ 細田アニメ で知って…

本が好き! 1級
書評数:92 件
得票数:590 票
なんぞ?SE




表題作を含む3編が収められている。どうしてもSFとしてはチープな気がしてしまうんだけど、黎明期としてはこれくらいのアイディアやトリックが驚きの対象だったのでしょうか。
読んだのは新装版じゃなくて、昭和51年初版の古い表紙の方だった↑ 細田アニメ で知って…
![]()


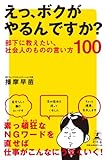
新入社員の素っ頓狂なNGワードをあるあるネタとして楽しみながら、その教育方法を学ぶ一冊…を期待したけれど。。ネタの厳選やアドバイスも甘く、読み物としてもあまり面白くはなかった。
対人関係に対する価値観は「ものの言い方」に現れるというコンセプトの下、ベテラン社員には理解できない(…




そしてこの物語は、必ずハッピーエンドを迎える。なぜなら、この物語は始まりの時点が最も悲惨で、最も間違った状況だからだ。彼らのうち二十四人は、物語の始まりと同時に死亡している。(p11)
悪くはない。語彙が無駄に豊富で、一文毎に改行しない文章は好感が持てる。 主人公輝美の二人を残し…





【漫画】小説版を先に読んだが、やはり原作というのはメッセージを訴えかけるパワーが違う。ギムナジウムという少年だけの世界における、純愛の物語。BLの魅力が少し解った気がした?w
やはり原作というのは、メッセージを訴えかけるパワーが違う。 無理矢理ひとことで言うなら、ギムナ…






震災後1ヶ月で書かれた、原発の今・昔・これから。フクシマでは何が起きているのか、何故フクシマが事故ったのか、他の原発は大丈夫なのか、我々はどうすればいいのか、エネルギー政策はどうすべきか。読むなら今。
予てより日本のエネルギー問題・環境問題についての欺瞞に疑義を投げかけていた「異端の研究者」である著者…






もうハルマゲドンは起こらない。「終わりなき日常」の中で「さまよえる良心」がこじれることで、オウム的なものを作り出してしまう。それを回避するために、ブルセラ少女に見習ってまったり生きようぜ。そんな話。
あとがきで、著者の社会哲学(?)を熱く語っている部分がある。曰く、 戦争が「一般に」悪であるわけでも…
![]()




facebook中級者に向けた応用指南書。アプリ・メッセージ・フェイスブックページ・ノートの4つの使い方が画面遷移図と共に詳細に紹介されている。
第1章 アプリでフェイスブックをさらに楽しく 第2章 新メッセージシステム完全理解 第3章 使いこな…





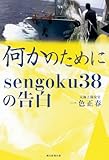
尖閣ビデオ「流出」事件の「犯人」である一色正春氏による憂国のエッセイ。著者は、その人生を賭して日本国民全員に問いかけてくれたのだ。あとは、私たちがそれにどう応えるかだ。
2010年9月7日、尖閣諸島付近で中国漁船が日本の海上保安庁の巡視船に体当たりする事件が発生した。そ…






オタク文化とは何なのかということ分析し、そこから出てくる「動物化したポストモダン」が現代の日本社会にも敷衍して云える概念だと主張する。なぜ「萌え」が売れるのか。世のなべてのオタクは必読の一冊。
所謂オタク文化とは何なのかということを現代思想の観点から分析し、そこから出てくる「動物化したポストモ…






情報のビオトープ化。記号消費からつながり消費へ。他人の視座にチェックインすること。そこから拡がるキュレーションの世界。読者を導くこの流れが鮮やかで無駄がなく、感動的だった。
相変わらず頁数の多い新書だが、あっという間に読了した。 情報のビオトープ化。記号消費からつながり消費…


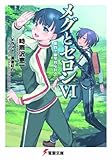
次巻への繋ぎの一冊。アリソンから数えても、シリーズ初の(?)短編集。ラストの話が「あなた」(=読者?)を主語とした文章だったのは斬新だった。読者に新聞部に飛び込んでもらおうという試みだろうか。
ついに短編集の様相になってしまった。どうやら次の巻へのつなぎの一冊であって、この本自体にさほど重要性…





「本の学校」という団体が主催する、出版産業シンポジウムがTIBFの中で開かれている。その2009年の会議の内容をまとめた本。「待ったなし!」だったはずの改革の進捗は、芳しくないようだ。
今年の東京国際ブックフェア(TIBF)までには読まねばと思い、昨年7月から積んであったのを読了。「本…





原作未読。森作品は『スカイ・クロラ』と『小説家という職業』の2冊しか読んでないけど、似た空気を感じる。耽美なw雰囲気を除けば、非常に森博嗣的な小説だと感じた。嫌いではない。これから原作読む。
原作未読。森作品は『スカイ・クロラ』と『小説家という職業』の2冊しか読んでないけど、似た空気を感じる…




民間企業と厚労省の特殊法人。その両方で働いた経験から、公務員の仕事の在り方について様々な問題点を論っていく。しかし「ジャーナリスト」の著作としては甘い。もっと突っ込んだ取材や提案が欲しかった。
大手建設会社と厚労省の外郭団体である特殊法人「日本労働研究機構」で働いた経験を持つ著者が、公務員の仕…




電子書籍に淡い恋心を抱いて長年勤めた紙媒体の出版社を辞めるも、どんなにアイディアを尽くしても電子書籍は気持ちを受け止めてはくれず、遂には電子書籍は世界を滅ぼすと言い始めたおじさんの手記。
電子書籍に淡い恋心を抱いて長年勤めた紙媒体の出版社を辞めるも、どんなにアイディアを尽くしても電子書籍…





やはり読み継がれる作品は安定感が違う。少年時代特有の衝動・情動・感応・官能の描き方が凄い。子供にとって、大人とは社会とは子供とは何なのだろうか。
やはり読み継がれる作品は安定感が違う。少年時代特有の衝動・情動・感応・官能の描き方が凄い。しかし前半…




「キンドルが出版業界に与えた衝撃」というよりは「キンドルが新聞業界に与えた衝撃」についてのリポート。主にアメリカの新聞業界から見た昨今のメディア革命について語られている。
看板に若干の偽りアリ。「キンドルの衝撃」というよりは「主にアメリカの新聞業界から見た昨今のメディア革…





グンゼ創業者・波多野鶴吉の孫、神風特攻隊で出撃直前に終戦、4年間のシベリア抑留、スタンフォードの大学院哲学科に留学。そんな波多野一郎が、アルバイトでイカと向き合い続けて閃いた平和論。と、その考察。
波多野一郎による「烏賊の哲学」本稿と、中沢新一による「イカの哲学から平和学の土台をつくる」の二部構成…


久しぶりに酷い本を読んだ。TBSとTBSと読売新聞の出身者による鼎談と見せかけた、おばちゃんたちの井戸端会議録。曖昧な論拠で話を進めた挙句、最後に情報リテラシーに言及する流れには失笑を禁じ得ない。
久しぶりに時間の無駄だと思える読書体験だった。これはとても鼎談とは呼べない。単なる井戸端会議をまとめ…






辛坊兄弟による、日本経済(≠経済学)の入門書。経済をまともに勉強したことのない私にも非常に分かり易かった。これを読んでかなり視界が拓けた気がする。
全5章で構成されているが、第1章「暴論に騙されないための日本経済入門」に全体の半分以上の紙幅を割いて…