考える快楽―グレイリング先生の哲学講義






読んで理解すれば終わり,の類の本ではない. 取り上げられたテーマについて自分の思うところと, 著者の考えとを照らし合わせて初めてこの本の良さが分かる. 「あ,考えるって面白いな」と.
本書の内容はいたって単純. 哲学書によくある,テーマ(大抵1語)とその意味について語る形式. だ…

本が好き! 1級
書評数:100 件
得票数:470 票
こんにちは、chee-choffもとい、せんだです。
読書が趣味→生活→生活+仕事、とどんどん高じています。
書評のスタイルにとらわれず、「読めば読みたくなる文章」を心がけて文章を載せています。
多種多様、あるいは謎のテーマで三冊本のセットを組んで販売するネット古書店をやっています。
興味がありましたら一度HPにお越し下さい。
本業は現在「ブリコラジール」という屋号で個人事業をやっています。






読んで理解すれば終わり,の類の本ではない. 取り上げられたテーマについて自分の思うところと, 著者の考えとを照らし合わせて初めてこの本の良さが分かる. 「あ,考えるって面白いな」と.
本書の内容はいたって単純. 哲学書によくある,テーマ(大抵1語)とその意味について語る形式. だ…






言いたいことはたくさんあるのに、 それを言葉にできないというのはもどかしい。 そういう思いにさせる本に違いない。 そしてその思いの源は公的なものなのだ。
2009/09/21 23:20 僕が今まで読んできた内田樹の本の中ではトップ3に入る金言の多さ。…





この本は吉岡書店(古本屋)で購入した。 中には帯の他に本書の当時の書評とその時の夕陽妄語(著者が朝日新聞に書いていたコラム)が挟み込まれていた。 古本を買ったときの醍醐味の一つがようやく味わえたと言えるだろう。 さておき。
テーマは国際関係だったりナショナリズムだったり、社会問題全般というべきか、 普段とっつきにくいと(…






『恋文の技術』を読むと手紙が書きたくなるのは本当であった.僕の中で携帯電話の地位がまた一つ下がったことに,なぜか嬉しさを感じる.
森見氏の名言はいつも,僕の心に響く. 「実った恋ほど面白くないものはない」 そりゃそうだ. …




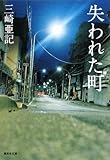
作中の彼らが「本気で生きている」と感じられた瞬間から,読み手たる僕らはもう現実(ここ)にはいない.そしてその「現実でないところ」から,現実と変わらぬ強い想いを受け取り,僕らは現実へと帰ってくる.これは,小説のその本来の姿ではないだろうか.
『失われた町』(三崎亜記)を読む. 著者の社会を切り取る眼の鋭さに感服した. 彼の描…






じぶんの看板というより,むしろじぶんそのものであるような顔,それは皮肉にもじぶんだけが見えないものであり,その意味でひとはじぶんの顔から無限に隔てられている.(p221)
Title : 身体(からだ)を切り取る 鷲田先生初のエッセー集の文庫版. 臨床哲学エッ…





言葉では到底表しきれないものの表現に敢えて挑戦する努力がにじみ出ていて,その気持ちを汲み取った上で彼らの文章を読めば,言わんとすることを理解できなくとも受け取れるものがあるはずだ.
ロウ氏の本著. 「ジェイムズと対話してもらいたい」と最初では調子のいいこと言っておきながら, …





自由と欲望は学校のもっとも嫌う人間の要素でもある.メディア(欲望の肯定)と学校(欲望の抑制)との綱引きで学校が勝利するはずはない.(p.198)
ことばを読むとは,たとえあとになってから批判するにしても,まずはさしあたって表現者の考えかたを受…





”合理性”に”逸脱”がくっついて,二者を取り持つのが”からの”ではなく”への”? …字面を眺めてから本書を読むまではまさに「地続き」であった.「ジャケ買い」ならぬ「タイトル買い」である(正確には「タイトル借り」だが).
最後のアレゴリーの章が面白かった。 難解な用語に埋もれていても、言わんとすることが良く分かった。 …






現状というものは、誰か他人の作っているものではなくて、自分もコミで作っているものだ。だから、「現状がやだ!」と言って下りてしまえば、そのことによって、きみ自身が”停滞した現状”を作る構成要員の一人となることだってある。(p.137-138)
Title : 自分も「コミ」の構造主義 客観的に過ぎて、枠組みばかり考える。 そう言われる…






「関係がないから、分からないのだ。だから、「関係がある」と思わなければならないのだ。」 (p.211)この一言に,橋本治という人の全著作に対する「魂」を感じた.
注)未読了ですが書いちゃいます. まだ読み終えていないけれど、本書の濃密さに改めて驚愕し、…





刹那的な幸福感に追われる僕らに「それがずっと続けられるならいいのだけれど…」と控え目なお節介をかけてくれる,古き良き日本人を知る「おじさん」達の溜め息の書.
あるコンセプトに従って同じ色の付箋を付けた。 それは、「既成観念の裏を見る」である。 すなわち本…





「自分の身体のことなんて他人にことさら言われなくとも分かる。 自分のことなんだから。考える以前の問題だろう。」…本当に?
こういう認識が実は当たり前になっていて、 自分には分かるという「言葉」が先行して自分に入り、 身…





『大人への条件』(小浜逸郎)を読んだ. 「社会人」というものを意識し出してから(それは就職活動を始めた頃だ), 自活性・責任の有無などで学生と社会人が対比される, その同じ枠組みとして見た時,子供と対になる「大人」にも興味が向いた.
まぁ興味を持つのも妥当なところかなぁと自分では思うけれど, その文脈とは別に「教育に対する興味」も…




「人間の心の問題をテーマに幅広く執筆活動を展開」(著者紹介欄より)しているというランディ氏に僕が反応しない道理は無かった。
本書もご多分に漏れず、自分の趣向ど真ん中で 興味深い話題が多かった。 氏の出自(今までずっと「で…






レトリックの問題は,いつも,たちまちレトリックを越えてしまう.言語をめぐるすべての悩みがたちまち言語を越えてしまうことを思い出そう.(p.314)
レトリックは単なる言葉遊びではない. 常識からの逸脱による驚きや癒しの効果も無論ある. が,その…





「細部の描写がリアル」と言ってまぁ間違いはないけれど, これぞ氏の真骨頂と勝手に思った部分を取り出せば, 「主人公の視点の移り変わりがリアル」だという所.
主人公(本作では「望美」)が淡々と流れる日常の一場面において, 周りの状況(の進展)と彼女自身の意…





やっぱ有さん最高. 没入すればするほど分かる軽快なテンポの良さ. そのかるーいノリでふとグサッとくる明言.
登場人物は皆,愛すべき特徴をどこか持っている. それがどっちつかず(に見えて破天荒(に他人には見ら…




会社のみに生きる人間。 自分のために周りを構わぬ人間。 完全なる無垢な慈悲をもたらす人間。 常に破滅と隣り合わせで生の綱を渡る人間。 知悉で計算高くかつ誠実過ぎる人間。
抜粋したい部分があった。 もちろんネタバレしない部分を選ぶ。 著者は主人公の思考場面で幾つか古典…






社会の問題点が単なる知識でなく肌触りを持つ肉感として伝わる. 社会を語ると話が大きく抽象的になりがちだが, その肉感により読者の身体に社会の諸相が感覚をもって落し込まれる. それが「身体を備えた個としてどう振る舞うか」に相対する契機となる.