第三の敗戦




第1の敗戦を明治維新、第2の敗戦を太平洋戦争とし、今年の関東大震災を第3の敗戦と位置づけたうえで、敗戦から復興してきた日本の歴史を糧に現代日本への処方箋を提言する書。
普段読まない系統の本なんですが,とある要請により感想文(書評ではないです)を書いたので. いつもよ…

本が好き! 1級
書評数:100 件
得票数:470 票
こんにちは、chee-choffもとい、せんだです。
読書が趣味→生活→生活+仕事、とどんどん高じています。
書評のスタイルにとらわれず、「読めば読みたくなる文章」を心がけて文章を載せています。
多種多様、あるいは謎のテーマで三冊本のセットを組んで販売するネット古書店をやっています。
興味がありましたら一度HPにお越し下さい。
本業は現在「ブリコラジール」という屋号で個人事業をやっています。




第1の敗戦を明治維新、第2の敗戦を太平洋戦争とし、今年の関東大震災を第3の敗戦と位置づけたうえで、敗戦から復興してきた日本の歴史を糧に現代日本への処方箋を提言する書。
普段読まない系統の本なんですが,とある要請により感想文(書評ではないです)を書いたので. いつもよ…





『バスジャック』に続く短編集第2弾.「日常を少しだけズラしたリアル」が相変わらず冴える.現実との差異に最初は戸惑うが,それぞれの作品の確固とした世界観に引き込まれるうちに違和感は消え去る.
『バスジャック』に続く短編集第2弾. 「日常を少しだけズラしたリアル」が相変わらず冴える. 現実…






ポリシーが一貫していると書いていた。 それはとても分かりやすいとも。 その分かりやすいとは、「理解できる」とか「共感できる」ではなく、 「単純だ」ということだろう。
多少,私的詩的(?)妄想が入ってます. 僕自身の話はフィクションが織り混ざってると考えてもらって……





作り上げたものに対して、手先の器用さや(レプリカなら)本物との寸分の違わなさを褒め讃える視線には冷たく、ただ「創ろうと思った心意気」を褒めてほしい、と。道具はその心意気を培うための手助けとなる。
半分,私的な感想文ですが. +*+*+* 2010/11/20 15:26 本書への言…






本書は(…)外面的な生活の変化にもかかわらず、ある民族の文化のパターンはなかなか変化するものではない、という文化人類学的信念によって貫かれている。p422-423
本日読了。 凄い大作であった。 どのような書評を書こうか… 多くの人に読んでもらいたい…






本書には毒筆以外の成分が全くもって含まれておらず、つまりは言わずして伝わる、日本伝統の「以心伝心」本なのだ!何が伝わるかって、それは「本書は毒舌本です」というメタ・メッセージなんですが(笑)
久しぶりの投稿です、夏ですね。 読めても、書く気がなかなか起きない季節。 暑いとアウトプット…





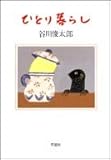
黙読であれ字面を追うだけであれ,どこかしら心地よさをもたらしてくれるリズムがある. 文章を信頼できるというか,ことばに寄り掛かれる,体をあずけられる未知の経験.
詩人の本を初めて読んだ. 詩の読み方(ではなく「感じ方」だろうが)がよくわからないという思いから,…
![]()





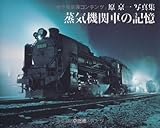
蒸気機関車を人に見立てる表現に違和感がないのは、 熱を持ち煙を吹き出し(さながら怒った人のように)、 そして力強さが一切の迂遠を排除して見る者に直接ガツンと響いてくるからだろう。
76年に国鉄のSLが運行を終えるまで、 9年に渡り全国を飛び回った原京一氏のSL写真集。 序盤に現…






なんでもググってすぐ「わかる」現代では,本来不安であるはずの「わからない状態」を常態とし,「わかった」を次の「わからない」に当然に繋げてけろりとするスタンスを「方法」と呼ぶに相応しい時代かもしれない.
変な紹介文書いてて良かった,と思われてしまう典型的な「書評」. つまり以下はぜんぶ「この本を読んで…





この小説の感覚経験はあまり常時携帯はしたくないなぁと怖気づいているので…開ける時に開ける,パンドラの箱,ということで.しかし…「開ける時」っていつだろう?
ネタバレにチェックを入れはしたが, 何のネタバレの恐れがあるかと言えば,何故か『火車』(宮部みゆき…






タイトルを見れば「この本には"不況"の話と"本"の話が書かれているのか」 と容易に思われ「今が不況なのは分かってるしどんな本を読めばいいのかが書かれているのだろう」 との推論が自然に展開されていいのだが…
僕は読む前から分かっていた。 本書でハシモト氏が言いたいことを一言で表すと(実は表せちゃうんです)…
![]()




「沈黙に耐えること」を言い換えると、「自分の中で震災を終わらせないこと」。これには、努力が要る。個人的な体験が希薄なほど、風化しやすい。その風化をくい止めるために、本書を読む。
献本書評なのだけど,自分に向けて書くことにする. というのも,今の時期にこのような本について意見す…





自由奔放さが満ち溢れていて、その「自由奔放さの表現」の選択までもが自由奔放で全体的に置いてけぼりを食らっていたようではあった。だがそれがいい(断言)
2010.7.15 Title : 平行多自己トークスタイル 『工学部・水柿助教授の解脱…
![]()





月並みな感想で締めるが、少女マンガを読みたくなった。「男より女の方が自分(の感覚)に自信を持っている」と世に言われる所以が少女マンガにあるのやもしれぬ、と思いつつ。
「男にこそ読ませるべき」というのは本当。 少女マンガを読まずにバカにしてきた男子が読めばカルチャーシ…





現象の原理やものの道理について確認できる事柄を用いた推論が大胆に行なわれる.その証明については科学が発達した現代においてうなずけるものはあまりないが,推論の方法やその緻密さには目を見張るものがある.
現象の原理,ものの道理について, 確認できる事柄を用いた推論が大胆に行なわれる. その証明内容に…






多国間関係の歴史を「なまもの」として扱う稀有の書.論理の飛躍はおかまいなしでそれとは別次元の「肌感覚の納得」がもたらされる.生態学と民族学のコラボレーションが生み出した革命的な視点に震える.
注)本書の内容紹介は絶無です. +*+*+*+* 「東南アジアの国から」(梅棹忠夫『文明…




絶対的な意味では形式も内容もなく,現実の世界においても数学の場合と同じく,あらゆる形式はそれを包含する形式に対して内容であり,あらゆる内容はそれが包含する内容に対して形式なのである.(p115)
2009.2.7 長かった.今まで読んだ新書の中で最も手強かったのではないか. というか,何…






自身を問題の渦中に投げ込みつつも全体的に問題から距離を置いて論じる手法は学ぶべきところがある.投げ込んだ自分は一人の自分.外から見る自分はもっと沢山いると思われる.
08.10.29 Title : 中庸の居場所 カミュの『異邦人』を読んだことがある人は…




地方新聞・周縁メディアは読者の政治参加を促す機能の素地を持っている.市民が政治に興味を持てば,それが「市民同士の議論の場」へと発展すると説く.パブリック・ジャーナリズムの可能性を好意的にとらえた著書.
2009.1.28 地方新聞・周縁メディアは読者の政治参加を促す機能の素地を持っている. …



合理的思考だけでは深く進めない以上,「自死」についてこのような考え方(感じ方)があり,それを死をもって伝えようとした人間が実際にいたことを記憶しておくこと以上に,今の自分にできることはない.
自分でいうのもなんですが,珍しく辛口書評です. ちょっと耳が痛いかもしれません(今の自分には痛いで…