双頭の船






とても大きな悲劇があったのだから、それを凌駕するだけの大きな物語が、今は必要なのだ。
もうずいぶんと前に読んだのだが、やはり紹介しておこう。今のところ今年(2013年)のベストワン。池澤…

本が好き! 1級
書評数:382 件
得票数:2900 票
村上主義者。






とても大きな悲劇があったのだから、それを凌駕するだけの大きな物語が、今は必要なのだ。
もうずいぶんと前に読んだのだが、やはり紹介しておこう。今のところ今年(2013年)のベストワン。池澤…





廃墟となったラブホテルが、まるで自身の記憶をたどるかのよう。
直木賞受賞作。ラブホテルを舞台にした短編連作集である。いわゆる「グランドホテル方式」をとっていて、北…






僕がこの作品を再読して「忸怩たる」思いを抱いてしまうのは、この三十年間、泥水をすする勇気を持たなかった自分自身に対する憤りを感じずにはいられないからだ。
宮本輝の、いわゆる「川三部作」を読んだのは高校生のときだった。『青が散る』がドラマ化され、当時の宮本…






タイトルは『小説の読み方、書き方、訳し方』だけれども、これはすなわち「世界のつかみ方」ということでもある。
柴田さんの著作はあらかた読んでいたつもりだったのだけども、この本は見落としていた。高橋源一郎との対談…






小川さんの言葉がなかったら、僕はどこかで佐野元春のファンであることをやめてしまっていたかもしれない。
僕が小川洋子の作品に惹かれ続けているのは、そのリリカルな作風に魅了されていることはもちろんだけれども…






「インタビュー」は「官能」だ――このふたつが結びついたとき、著者の松原さんの頭の中では、この作品の構想が瞬時にできあがったのではないかと思う。
「インタビュー」は「官能」だ――このふたつが結びついたとき、著者の松原さんの頭の中では、この作品の構…





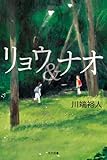
ジーコーズの子どもたちは、僕らの代わりにあちこちを旅して、僕たちに「ほら」という感じで、世界のいろんな問題を手渡してくれる。
「可愛い子には旅をさせろ」とはよく言うけども、さて、どこに旅に出せばよいのか分からない。「好きなこと…






もしかしたら普段僕らが当たり前のように乗車している新幹線の中では、毎日のように殺し屋たちが戦いを繰り広げているのかもしれない。
伊坂幸太郎を初めて読んだのは『重力ピエロ』という作品だった。僕はそれをゲラだかパウンドプルーフ(見本…






結論めいたことを書けば、どうやら人間は「がん」には勝てないらしい。
2009年にNHKで放送された同名番組の書籍版である。単行本には番組のDVDが付録としてついていたが…






ずいぶんとアナログなことをしているなと自分でも思うけれど、そこで生まれる「体感」が心地いい。
「人狼ゲーム」というのはもともとはボードゲームだったらしい。それを大規模なイベントにしたのが、京都で…






これが1939年に書かれたというのだから、驚くしかない。
クリスティーといえば、僕らの世代であれば、まずは映画でその名を知ったという人も多いのではないだろうか…






行政という「怪物」は日本全国にいて、多くの人たちが泣き寝入りしているだろうことは想像に難くない。
哲学者・國分功一郎の名前を知ったのは、2011年秋に刊行された『暇と退屈の倫理学』を手に取ったときだ…






いつか〈永遠の女性〉が、再び目の前に現れることを漱石は望んでいたのかもしれない。
そういえば、漱石の『夢十夜』も教科書に載っていた。こちらは高校のときだと記憶している。十話すべてが収…






宮崎駿が描く那美を、僕は観てみたい。
漱石の『草枕』は、初期の傑作とされるがどうも読みにくい。〈智に働けば角が立つ。情に棹させば流される。…






文庫本にしてわずか11ページの作品だが、永井は「色彩」を使って、男の気持ちが移ろっていくさまを見事に表現している。
湯河原に一泊した。到着した旨を宿に伝えると、駅まで迎えに来てくれるという。これはありがたい。案内に「…






中学生の僕にとって、それはあまりに衝撃的な内容だった。
新しいKindleが来たので、さて何を読もうかと考えた。これまでに購入した書籍を読めばいいのだけど、…





「DX9」の歌声は、僕たちに「想像せよ」と呼びかけている。
南アフリカを舞台にした小説といえば、クッツェーの『鉄の時代』を思い出す。主人公は老女。アメリカに渡っ…
![]()






八谷さんのメーヴェを、僕は見に行きたい。そこではきっと、17歳の頃、『風の谷のナウシカ』を初めて観たときの僕に出会えるような気がするのだ。
タイトルには「作ってみた」と軽く書かれているが、これは10年をかけた一大プロジェクトの記録である。八…






ずいぶん前に読了した光文社版の『カラマーゾフの兄弟の感想です。ふざけてるようにしか読めないとは思いますが、まあ、こんな風に気軽に、自分の得意な(?)土俵にあげておいてがっぷり組んでみるのもありかなと。
【一日目】 朝五時起きで『カラマーゾフの兄弟』を読んでおります。しくしく。なんとなく(なん…






いまだ戦い続けている作家たちからの、円熟味を増したメッセージの集成であるのだ。
翻訳家の柴田元幸の『Monkey Business(モンキービジネス)』が、新しく『MONKEY』と…