東京の自然史

東京の地形について考える。
武蔵野台地は多摩川のつくった扇状地である。不老川、黒目川、石神井川、神田川、目黒川、野川などは、いず…

本が好き! 1級
書評数:85 件
得票数:1983 票
読んでいて面白い~と思った本の読書記録です。

東京の地形について考える。
武蔵野台地は多摩川のつくった扇状地である。不老川、黒目川、石神井川、神田川、目黒川、野川などは、いず…

名匠アーサー・C・クラークの海洋SF。
名匠アーサー・C・クラークの海洋SF。ジュブナイル小説なので、基本的に悪人は登場しない。 密航…

陽明学から主観と客観について考える。
本書はいわずと知れた陽明学の大家、安岡正篤(やすおか まさひろ)の講演を筆録したものである。話し言葉…

多様性予測定理、主観知、客観知により集合知を考える。
集合知を考えるときに、まずおさえておく必要があるのは、多様性予測定理である。これは、 集団誤差 …

自由恋愛環境下における安定出生率は、厳しい経済状況下であっても、しっかり機能していたようである。これは驚くべきことである。
世代による変化をみるときには、出生コーホート別の集計が重要である。ここで、コーホートとは、ある期間に…

面白いものに出くわしたときには、その法則を考えると楽しい。
本書は、ピタゴラスイッチなどでお馴染みの佐藤雅彦さんが、毎日新聞で月一回連載していた記事をまとめたも…

種として、あるいは生物全体として、あらゆる可能性に備えて、様々な遺伝子に分散投資することが、生命の連続性を支えているのだ。
一卵性双生児は見た目がそっくりなので、性格や好みや得意なこと、更には、考えていることや歩む人生までそ…

暗渠となったかつての川は、大雨のときにだけ、本来の流れを取り戻す。
たとえば、東京都の目黒川をずっと上流にたどっていくと、池尻大橋駅近くの国道246号線と交差するところ…
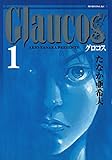
フリーダイビングから、海とヒトとの関係を考える。
人間の比重は水の比重とほぼ同じなので、水中では、浮きも沈みもしない中性浮力をとることができる。青くて…

味の好みから文明圏を考える。
古代ローマの歴史は長いので、その調理習慣や料理技術にも様々な展開がある。ここでは、古代ギリシャ発祥の…

絶対音感という事象の簡潔明瞭さが生み出す様々な状況や思い。他の感覚との比較から。
絶対音感とは、ある音を聞いたときに、他の音と比較することなく、その音の高さを正確に判別できる能力のこ…

子どもの世界認識と大人の世界認識、子どもの感じる時間の流れと大人の感じる時間の流れ
3歳から10歳までの息子に対して、父親が年に1回試みた全8回のインタビュー記録である。 大人が…

荘園───日本の中世社会を説明する最重要ワード
荘園は日本中世社会の基幹的な制度であり、中世史の最重要ワードであるといってよいであろう。中世の公領や…

現生鳥類のありさまから恐竜の生態を推測するのも面白い。
鳥は恐竜から進化したどころか、鳥は恐竜そのものであって、恐竜のなかの獣脚類に含まれるという説も定説と…

AF(人工親友)のクララによる口述記録
AF(人工親友)のクララが、廃品置き場で沢山の記憶を整理するなかから生み出された口述記録が、この『ク…

渋滞のときにみられる、相転移しそうなときのどっちつかずの状態の解明は、様々な自然現象を読み解く上での鍵になるだろう。
車の渋滞について考える。 車は、自発的に動くことができる。それを自己駆動粒子とよぼう。自己駆動…

LLM(大規模言語モデル)の登場もふまえて、自然言語の文法という現象の面白さについて、もう一度考えてみても良いのではないか。
まずは、世界中の全ての言葉に共通する現象を考えてみたい。 言葉を波形でみたときのかたまりは音節…

老子で考える部分と全体
老子には様々な解説があるが、英文で読むと、また違った趣がでて色々と考えるきっかけになる。本書は、言語…

大規模言語モデルの性能は、規模の大きさが効果を発揮するように実装され、規模の大きさに支えられている。
2022年11月に登場したChatGPTを皮切りにして、 大規模言語モデル の高い対話能力と汎用的な…

オマル・ハイヤームの四行詩は、想像力をかきたてられるなあ。
ルバイヤートの詩人オマル・ハイヤームは、セルジューク朝の科学者で、ジャラーリー暦を定めた人物である。…