宮本常一 (ちくま日本文学全集)






歌垣がまだ日本に残っていた時代の話。そんなに古いことではない。つい最近の逞しくそしてちょっと切ない日本の近代の話。
私が読んだのは1993年5月20日第1刷発行のもの。著者は1907年山口県大島生まれ。1981年没…

本が好き! 1級
書評数:90 件
得票数:794 票
pandaNo30です。
漫画サザエさんとワイルド7を暇があれば読み直しています。金満チームになるずっと以前からヴィッセル神戸のファン。今年は上位に食い込めるのか。
★2019年3月4日 書評数50冊






歌垣がまだ日本に残っていた時代の話。そんなに古いことではない。つい最近の逞しくそしてちょっと切ない日本の近代の話。
私が読んだのは1993年5月20日第1刷発行のもの。著者は1907年山口県大島生まれ。1981年没…





私は民家好きなのだ。世界中の民家を見て歩くのが夢。柳宗悦氏の文章が紹介されていて、面白かったので全文書き写す。
いつも利用している図書館に頼んで別の図書館から取り寄せてもらった本。であるから延長することもできず…





還暦を前にしたオッサン(爺さん)がこういう本を読んでも良いのか?と少しためらったんですけどね。ヒロインの名前は栞子。シオリコと読むそうだ。もっとひねった読み方をすると思っていたら、そのままだった。
単に前から気になっていたということで購入。私の読書友達も気にはなっていたそうですが、なんせ表紙の絵…




著者は1967年福岡県北九州市に生まれる。1990年福岡大学卒業。東京の証券会社へ就職。いくつかの会社に勤めた後、10年にわたりフリーター生活をする。
2005年6月17日第1版第1刷。フリーター、明るく楽しそうに書いてあるのだが、、、、。健康であっ…





なんかずっと思い込みで過ごしてきた事が間違いだったことに気づかされた。
1987年7月25日初版発行。著者は1934年岡山県生まれ。青山学院大学卒業。編集者。地方新聞(6…




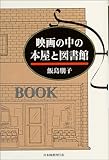
図書館映画というのがあるそうだ。一番多く出演しているのはジュリア・ロバーツとある。ここでいう図書館映画とは図書館のシーンが出てくる映画を指す。例えば「love letter」の中山美穂は図書館勤務。
私は別のところで「映画と食事の場面」についての文章をだらだらと書いているのですが、この本は映画の中…




最初に読んだのは高校のとき。あれから40数年たってしまった。
昭和58年5月25日初版、平成19年6月25日改版初版。 星新一は高校の頃によく読んだ…






朝鮮の相続について調べていた時に読んだ本。両班の相続制度について詳しく書かれてあり非常に面白く読んだ。
私は朝鮮という国がはるか昔から儒教の国であったように思っていたのだが、どうも違うらしい。1290年…





サンダーバードの題名に出てくる「危機」は10回、「恐怖」は4回。21世紀の世界は危機と恐怖に満ち溢れていた。
サンダーバードのリニューアル版を息子と見ていて以前から疑問だった事をふと口にした。 サンダーバ…





カフカの変身を思い出した。不条理。
人は誰しも役を演じなければならない。それを意識しているかどうかは別として。 子、甥、兄、従兄弟…




老後資金の1200万円は娘の結婚式費用と舅の葬儀費用に消えた。おまけに50歳を過ぎて夫婦そろってリストラ。神も仏もない。一寸先は闇。姑と同居を始めたあたりから一気にエンターテインメントへ。
私の友人から借りた本。読もうと思っていたら偶然友人が持っていることを知り借りました。 その…




何気なくお付き合いしているあなたの隣人が一番怖いっていうお話。
かつて東ドイツにあったシュタージ(秘密警察)は徹底した監視態勢で反体制分子の密告を奨励し、親が子を…




陳舜臣的神戸物語。神戸という街の生い立ち。陳舜臣の子どもの頃の思い出。1995年1月17日のこと、それから。
1998年1月15日 初版第1刷 神戸市は行政的には垂水区・須磨区・長田区・兵庫区・中央区…




西暦2000年の頃の作品群。15年ほど前、最近のようにも思えるしずいぶん昔のようにも思える。現在の感覚で読むと状況説明が当時流行のファッションを見せられているようで違和感があるものもある。
列車で移動する時に読むために購入しました。12の作品を集めた短編集。ここ何年も滅多に小説を読まない…





非常に情報量が多い本。上下段組み。図も多い。最初のページから順に一気に読もうとすると疲れる。体力、気力が必要なのだ。読み通せるものではない。気に入ったページを暇つぶしに時々読むのがよろしいかと。
2011年6月25日発行。著者は1925年、京都生まれ。京都大学農学部農芸化学科卒。1959年農学博…






父を亡くした後の私の気持ちを端的に表してある本。
著者はフロイト研究で知られる精神分析学者。ベルギーのブリュッセル在住のフランス人。フランスでの本書…




落語のネタに出てくる食べ物を軽妙洒脱な語り口でつづる。
まるで落語家が喋っているように脳内で変換される。池波正太郎の「そうざい料理帖」を思い出す作品。「そう…




白土三平の描いたカムイは中学の頃の社会科教師(共産党員)がたまに紹介していたので、その頃より白戸三平が描くものはそっち系なのかという印象があった。
だからといってカムイを何か色眼鏡をかけて読んだ覚えもないけど。 著者は1952年 横浜生まれ。…






アウトローとは匪賊、馬賊のこと。時代の衰退期であった民国期の記録からその破滅への過程を描いた本。遠い過去を見ているよう。身内の極大化、百子千孫、異姓結拝とか。まるで三国志演義。
ネットでこの本を検索すると「共産趣味」の本とある。「趣味」である。 私が子供の時に近所に中国…





武士は狩人であると。山の民、川の民、海の民。殺生を生業とする集団。
いつ買ったのか覚えていないのだが栞の代わりに挟み込んでいたハガキの消印が平成18年になっているから…