自省録

善い人間のあり方如何について論ずるのはもういい加減で切り上げて善い人間になったらどうだ。
アウレリウスの『自省録』は、ストア学派の影響を受けたローマ皇帝の『武士道』である。 太田愛…

本が好き! 1級
書評数:1073 件
得票数:19944 票
文学作品、ミステリ、SF、時代小説とあまりジャンルにこだわらずに読んでいますが、最近のものより古い作品を選びがちです。
2019年以降、小説の比率が下がって、半分ぐらいは学術的な本を読むようになりました。哲学、心理学、文化人類学、民俗学、生物学、科学、数学、歴史等々こちらもジャンルを絞りきれません。おまけに読む速度も落ちる一方です。
2022年献本以外、評価の星をつけるのをやめることにしました。自身いくつをつけるか迷うことも多く、また評価基準は人それぞれ、良さは書評の内容でご判断いただければと思います。
プロフィール画像は自作の切り絵です。不定期に替えていきます。飽きっぽくてすみません。

善い人間のあり方如何について論ずるのはもういい加減で切り上げて善い人間になったらどうだ。
アウレリウスの『自省録』は、ストア学派の影響を受けたローマ皇帝の『武士道』である。 太田愛…

歴史小説の功罪。司馬遼太郎は乃木をなぜあのように描いたのか。
乃木大将が殉死なされた。 夏目漱石の『こころ』においても印象的で、しかも重要な意味をもって…

ドイツ人は泥酔するまで酒を飲むことを認めながら、自分を抑制し、争わず、羽目を外さない酒の飲み方をするらしい。
「ドイツの女性は大抵センチメンタルだ」 あるいは、 「ドイツ人特有のロマンチック…

平安の婚姻制度は、やはり女性の我慢のうえに成り立っていたようだ。
万能の主役は時として物語を停滞させる。それゆえ、その力を上回る強敵を出現させるか、あるいは何らかの…

別な文明体系へ転換してから三十余年後にその能力を世界史の上でテストせざるをえなくなった。それが日露戦争である。その戦争を接点にして当時の日本人というものの能力を考えてみたい、というのがこの作品の主題。
作者によるこのあとがきがすべてを語っている。そんな気がしてくる。 「この作品は、小説である…

高い地位にいる人物の能力がすべて高いとは限らない。しかし人間は地位についてくる権限を過大に考え勝ちである。そうさせるのは勘違いしている上司か。それに従ってしまう部下なのか。
「自分ひとりだけが天才で他は手のつけられぬ愚物だと思っている」 そうささやかれていたのは…

興味のない人には苦痛以外の何ものでもないだろう。しかし、興味がある者にはこれは宝の山のようだ。インスピレーションを呼び起こす宝庫としても興奮を禁じ得ない。
遠野市にある柳田國男展示館にはガラスケースに納められた『金枝篇』が展示されている。子供のころから読…

専制君主の統べる当時の帝政ロシアの体制の弊害は、当然現在との比較をしたくなるわけだが、それ以上に自分の身近な組織にも共通する事実に唸る。
朝令暮改の指示にとまどう部下たち。 そんな部下たちはすべて馬鹿ばかりに見え、ことごとく…

戦争という特殊な状況の中で、国家という神以上の命令者によって動かされる人間たち
「お国のために」と命を投げ出した者も、 嫌々ながら動員された者たちも、 戦争という…

「司令部の無策が、無意味に兵を殺している。貴公はどういうつもりか知らんが、貴公が殺しているのは日本人だぞ」
理屈ではなくトップの好き嫌いでものごとが決まる会議。 お気に入りの者の意見だけが採用され、反対…

上巻に登場した「社会的無責任」という言葉のイメージが逆転する。社会の方におかしな部分が多いのだ。それに対して責任など感じず、自分の思う通りに行動する。そういうこと。
テレビでやっている、有識者たちが集まって行う討論会のようなものを見ていられない。それぞれが好き勝手…

ノーベル賞科学者は金庫破りの名人でもあった
ファインマンは好奇心旺盛で、どんなところにも首を突っ込む。 催眠術にかかる被験者に手を…

司馬の考える輝かしき時代なのか。
日露戦争前夜。 司馬はこの時代の日本人を買っていたのだろう。 主人公のひとり秋山好…

国家像や人間像を悪玉か善玉かという、その両極端でしかとらえられないというのは、いまの歴史科学のぬきさしならぬ不自由さである。(本文より)
司馬遼太郎の小説は、小説というよりは司馬の歴史解釈である。 そんな言葉をどこかで見たような…
![]()





その広範囲な影響。水戸学にとどまらず様々に興味を広げてくれる良書。
尊王攘夷。倒幕。 幕末を扱った小説を読めば必ず目にする言葉だが、その旗印の意味を深く考えもせず過…

『山月記』だけで中島敦を終えるのはもったいない
「大きな疑問が一つある。子どもの時からの疑問なのだが、成人になっても老人になりかかってもいまだ…

明治維新後。近代国家への道を急いでいた日本。四国松山出身の三人の男の物語。軍人である秋山兄弟と正岡子規。
第一巻は三人の少年時代から青年期への時間を、日本が激しく変化する様子と重ね合わせながら進んでい…
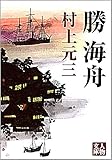
勝海舟の物語は安吾の『安吾捕物帖』しか読んだことなかった
時の権力者に、あるいは上役に、進言するということはなかなか難しい。 それに必要なのは、自…

タイパを重視するような人々にはお勧めしない
日本人で宮本武蔵を知らぬ人は少ないだろう。本人ほどではないだろうが、この五輪書の名前を知っている人…
![]()





朱子学を通じて考える日本人
人間とは何か。世界とは何か。 その答えを見つけようとするのはなかなかに荷が重い。 そもそも、数…