剣と清貧のヨーロッパ - 中世の騎士修道会と托鉢修道会




修道院というものは古くからありましたが、中世になってヨーロッパに新たな修道院が生まれました。騎士修道会と托鉢修道会というものです。
キリスト教の修道院といえば古代から町を離れた荒野の中で信仰の生活を送るというものでしたが、中世の12…

本が好き! 1級
書評数:2616 件
得票数:37717 票
小説など心理描写は苦手という、年寄りで、科学や歴史、政治経済などの本に特化したような読書傾向です。
熊本県の片田舎でブラブラしています。
コメント大歓迎です。ご感想をお聞かせください。




修道院というものは古くからありましたが、中世になってヨーロッパに新たな修道院が生まれました。騎士修道会と托鉢修道会というものです。
キリスト教の修道院といえば古代から町を離れた荒野の中で信仰の生活を送るというものでしたが、中世の12…



昔の合戦の話を聞いていると、なぜこちらが負けたのか不思議に思うこともあります。敗者がどうすれば勝てたのか、今更言っても仕方ないことかもしれませんが。
柘植さんはフランス外人部隊やアメリカの特殊部隊に所属、その後軍事評論家として多くの本を書いています。…





現代のクルーズ船では豪華な食事が売り物というものもありますが、船の中での食事というものの歴史はどうなっているのでしょうか。
人類は移動や運送の手段として古代から船を利用してきました。 乗組員は必ず食事をしなければならないの…






日本の経済格差が拡大しているとか、貧困層が固定化しているとか言われます。しかし経済に苦しむ人が健康かどうかということはあまり語られていません。貧困層が病気を治せないということはありそうですが。
日本で格差が拡大したとか、貧困に苦しむ人が増えたといったことは言われていますが、その人たちの健康はど…




今では「ニッポンの技術一流」などと言うこともあまりなくなったかもしれませんが、一時期はそのような言説が溢れていました。その頃に経済学者の内橋さんがその内情を描いたものです。
経済学者の内橋克人さんは先年お亡くなりになりましたが、多くの著書を発表してきました。 その最も活躍…




熊本日日新聞社の常務まで務めた久野さんが、育った宇土について書き記したものです。熊本市や八代市とは少し違ったその土地柄について描写されています。
著者の久野さんは専門の著述業ではないのですが、熊本の地元新聞の熊本日日新聞に長く勤め最後は常務まで昇…




題名を見て音楽の本と思ったら間違いです。哲学的要素が強いようです。
題名の最初の文字だけで判断し、音楽の表現などについて書かれた本かと思って図書館から借りてきましたが、…




「科学」とは書かれていますが、それよりもユーモアの要素が強い本でした。
かつてはNASAのロボット技術者だったがその後著述業に転進したという著者が、暮らしの様々な要望に対し…






気候変動ということが盛んに言われていますが、今に始まったことではありません。人類の歴史には常に気候変動が強く影響を与えていたようです。
かつての歴史学界では気候変動のことを持ち出すと批判されていたということですが、最近の研究では明らかに…

マルティン・ルターに始まり、ヨーロッパ世界を巻き込んだ宗教改革ですが、その真実の姿はあまり知られていないようです。
キリスト教の宗教改革は1517年にドイツの修道士マルティン・ルターが、当時蔓延していたローマ・カトリ…




江戸時代の食文化の中でも「江戸の蕎麦」というものは特異的であり粋を追及してたどり着いたものでした。そこには様々な要因があったようです。
食べ物で江戸(東京)の名物とされてきたものには鮨、天婦羅、うなぎ蒲焼、そして蕎麦が挙げられます。 …




作家の筒井康隆さんは演劇好き、映画好きとして知られていますが、その遍歴を綴りました。
筒井康隆さんはSF作家として名を成しましたが、演劇が非常に好きであり自らも映画俳優を目指して映画会社…





音楽を重要な要素としている劇として、オペラやミュージカルといったものがあります。そういった音楽劇はどのように発展してきたのでしょうか。
音楽を劇の重要要素として取り入れている音楽劇というものは、現在でもオペラやミュージカルとして人気があ…





世界中で人々の移動が活発になると国籍というものも複雑になってきます。国籍を持たなかったり、複数の国籍であったり。そういった問題点を説明しています。
著者の陳さん、名前は難しいですが愛称はララさんということですが、現在は大学教授の傍らNPO法人無国籍…




「歌う国民」といっても今のような老若男女みなカラオケで歌う状態のことではなく、明治から昭和にかけての状況を説明しています。
「歌う国民」といっても、昨今のカラオケで老若男女問わずにマイクを握るという状況は触れていません。 …




最近市町村合併で誕生した自治体名には変なものがたくさんあります。しかしこれまでにもそういった例はよくあったようです。
著者の宇田川さんは長年中高で地理を教え、退職後は地理教育のコンサルタントをされているということです。…




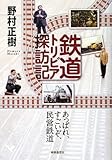
作家の野村さんは民鉄協会の広報誌から執筆を頼まれ、一般人は入ることのできない現場の取材ができました。鉄道ファンとしてはうらやましい話です。
著者の野村さんは作家ですが、子どもの頃からの鉄道ファン。 それを口にしていたら民営鉄道協会というと…




「あの人は人望がある」などと言われます。しかしそもそも人望とはいったい何なのか。そういった例を歴史上の人物を見ながら論じていきます。
小和田さんは戦国時代が専門の歴史学者ですが、一般向けの本も多数書かれており、また歴史ドラマの時代考証…




東京オリンピック開催には反対の声が強く上がりました。世界各国でもその意見が強まっているようです。オリンピック開催の問題点とは何なのか。
著者のボイコフさんは現在は大学の政治学教授ですが、もとはサッカー選手でバルセロナ五輪には米国代表とし…




![[ヴィジュアル版]地図でたどる世界交易史](https://m.media-amazon.com/images/I/61mCbSMjspS._SL160_.jpg)
世界の文明はごく一部を除き古代から互いに品物を交換する交易というものを行ってきました。 それを地図上に示してみればまた気が付くことがあるようです。
交易というものは人類が定住し文明を開いてきたかなり早くから行われてきたようです。 それはグローバル…