ヘンな論文





たった一人でも興味を抱き、心に湧き出した疑問を突き詰めていけば学問になる。
学問とは「問い」について学ぶこと。既に分かっていること、分かってるっぽいことを覚える小学校から大学(…

本が好き! 1級
書評数:1216 件
得票数:19478 票
山口での単身赴任を終え大阪に戻りました。これからは通勤時間を使っての読書が中心になります。





たった一人でも興味を抱き、心に湧き出した疑問を突き詰めていけば学問になる。
学問とは「問い」について学ぶこと。既に分かっていること、分かってるっぽいことを覚える小学校から大学(…





想像と創造の世界へ一歩踏み出すための軸
ほとんどのホテルは高品位のサービスを提供するために、徹底したマニュアル研修を行う。マニュアル研修はそ…




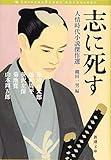
令和の世には通用しないかもしれない「名こそ惜しけれ」とは何か
『もののふは、名こそ惜しけれ』 平家物語でも台詞として用いられていた武士の矜持だ。本書のタ…






「倒れたままでいさせてくれる枕」絶望して倒れ込んでしまった人に寄り添う言葉たち
失恋をしたときには失恋ソングを聴く。決してハッピーソングを聴くことはない(はずだ)。だから絶望したと…






恐竜は鳥であり、峰不二子である。
鳥が恐竜から進化してきたことは今では、多くの研究者の共通認識となっている。 「鳥は恐竜である」と言…





映画の視聴スタイルの多様性に、作り手がついていっているのかを考えさせられた本でした。
『倍速にして、会話がないシーンや風景描写は飛ばしています。自分にとって映画はその瞬間の娯楽にすぎな…





「さみしさ」は悪者じゃない。逃げずに正面から向き合って欲しい。
さみしいという感情は幼い頃から誰もが持っているものだ。しかし、青年期になり自我が目覚めるとさみしさの…






この妄想力。半端ない。やはり岸本佐知子は天才だ。妄想の。
数年前、 「ねにもつタイプ」 にて彼女の天才に触れ、大爆笑したあげく、プリティ・ウーマンとハリス…





専門的なことは脇に置いておいて、柴門さんと一緒に楽しい仏像鑑賞の旅に出かけよう
柴門ふみさんの仏像探訪記。雑誌「オール讀賣」で連載されたエッセイ。 『好きなものは、好き。恋…





鉄道ビジネスにおいて日本はなぜ中国に負け続けるのか
2015年インドネシア高速鉄道建設プロジェクトの落札をしたのは中国であった。これは、日本の経済界にと…






紫式部の大いなる企み。ここに完結す。
壮大なプロローグを終え『若菜』にたどり着く。女三の宮の降嫁により、紫の上の心中はいかばかりか。苦悩と…





日本人の美意識の規範となった桜という花はいったい何なのか
毎年春になると一斉に咲き誇り、一瞬にして何の未練もなく散ってしまう桜。日本人にとって桜という花はどの…




一生泳ぎ続けるサメと同様、エンジニアはイノベーションを起こし続けなければならない
サイクロン式掃除機を生み出したジェームズ・ダイソンのモノづくりの半生記。少年時代からロイヤル・カレッ…






源氏物語の最高峰『若菜』への壮大なプロローグを終え、今まさにその入り口に立つ。
第二巻は「第十四帖 澪標」「第十七帖 絵合」「第十八帖 松風」「第十九帖 薄雲」「第二十帖 朝顔」「…





思考OSのアップデートのために必要な視点を獲得する
『ものごとを「どこから見るか」がリベラルアーツだと思っています。』 冒頭に著者が述べたこの…






「自分らしく」は安易な甘え
自分に忠実に生きたいなんて考えるのは、むしろいけない。 そんな生き方は安易で、甘えがある。 …






旅に出よう。人生を、もっと足掻こう。
仕事をがむしゃらに頑張って、出世街道を邁進し、仕事イコール人生として生きていく。すべて順調。このまま…






二人だけの青春を、文章として文字として書き残すことの意味と力。
歌人河野裕子が64年の生涯を閉じたのは2010年。夫であり歌人の著者は、遺品整理をする中で河野から著…





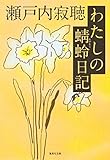
美と才能に恵まれながら、自我と自尊心が自らを不幸にする。そんな女性が20年もの長い間、夫を愛し、追い求めた半生記。
『今も昔も、ものを書く女などというものは、表面どのようにしおらしくつくろってみせたところで、心に鬼…






なにかに導かれるように目の前に現れた子猫と鬱病に苦しむ家主との物語
著者は医者と小説家の二足のわらじを履いていたが、ある日、医者の業に押しつぶされ鬱病になってしまう。同…