ことわざから出会う心理学
![]()
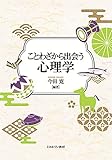
心理学を身近なものに
心理学という学問は、なんとなく難解でありうさんくさい、というような印象を持っている人は多いような気が…

本が好き! 1級
書評数:233 件
得票数:1367 票
だたの乱読家です。当然のことながら、書評は雑文。自己満足のために書いています。目も通さずに投票してもらう必要はありません。なお、今後はKADOKAWAの献本に対しての応募は致しません。
![]()
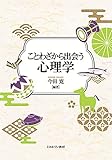
心理学を身近なものに
心理学という学問は、なんとなく難解でありうさんくさい、というような印象を持っている人は多いような気が…
![]()

元祖「自分探しの旅」
「自分とは何か」という問いに、多くの若者は直面する。そして、明確な答えを得ることができないままに、そ…

垂直的序列化と水平的画一化
日本における人間の望ましい姿は、教育の分野において典型的に現れると著者は述べる。本書ではそれを「垂直…
![]()
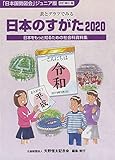
この国のことをより詳しく知るために
元々(小学校の頃から)地図帳、それも巻末の資料を読むのが好きだったが、それらの情報は表面をなぞるだけ…

遠藤周作による講演録
遠藤周作の作品は「沈黙」しか読んだことがない。日本の精神風土とキリスト教の問題を追及した作品群に、な…
![]()





注意欠陥多動性障害とはなにか
発達と障害を考えるための絵本である。 ADHDとは何なのか、ずうっともやもやし続けていた。 他の障…





コグトレに関心のある人はぜひ
かつて、同じ新潮新書から出ていた岡本茂樹著の「反省させると犯罪者になります」「いい子に育てると犯罪者…




陽の当たらない学校と子どもたち
筆者がこの本を書いた最大の理由、それは「教育困難校という存在に気づいてほしい」というものだろう。その…
![]()






イギリスの絵本作家の歴史がわかる
普段何気なく手に取っている絵本であるが、その中でもイギリスの作家による作品は小さな頃から親しまれてき…
![]()

宗教から平成を考える
「平成という時代は「いきづらさ」の時代である」ということは、平成の社会を生きてきたものにとっては共感…
![]()

社会科資料集として、活用できます
この本は、職業柄ほぼ毎年手に入れている。国土と人口、経済、農林水産業、工業、商業と貿易、交通と通信、…
![]()

WYSH教育について学ぶ
これまで、こういう名称の教育方法について、全く知らなかったのでどういうものなのか、関心を抱きながら読…

鶴見俊輔の生き方をえぐり出す
古本屋で購入。当時80歳を迎えた鶴見俊輔に上野千鶴子が絡み、小熊英二がなだめるという感じの鼎談集。発…

賢くなったような気にさせる
脳科学者の池谷裕二のエッセイ的な本は殆ど持っている。そして、読むたび毎に「ちょっと賢くなった」気分に…

専門外の人間も参考になります
中井久夫は知る人ぞ知る統合失調症の臨床医であり優れたエッセイストでありギリシャ文学の翻訳者。この1月…






ブルーバックスは良い本を作るなあ
これは錯視とパズルの本で、一人でも複数でも楽しめそうな一冊だ。 平和な世の中だからこそ、こうい…






宰相Aは読んでいないだろう
池内紀の解説によって、何とか本文を読むことができた。 210年前だろうが現在だろうが、状況が変…






これは、今時の読書人にとって必携かも
過去の哲学者、哲学で登場する用語をイラストを交えてものすごくわかりやすい解説で書かれている本。 …






反知性という言葉の源泉をたどる
日本ではネガティブ用語の代表的な言葉として扱われている「反知性」であるが、反知性主義という言葉はもと…






色んな人たちとの対談集
小学館のPR誌「本の窓」の連載を毎回楽しみにして読んでいた。文太の語る一つ一つの言葉が、あの声ととも…