「おそ松さん」の企画術 ヒットの秘密を解き明かす




人気アニメを仕掛けたプロデューサーによるヒット企画を生み出す方法論
2015年10月から2016年3月まで、最近では珍しく半年にわたって放送されたのが、テレビアニメ「お…

本が好き! 1級
書評数:927 件
得票数:17352 票
プロフィール写真変更してみました(2016/11/03)




人気アニメを仕掛けたプロデューサーによるヒット企画を生み出す方法論
2015年10月から2016年3月まで、最近では珍しく半年にわたって放送されたのが、テレビアニメ「お…





子どもたちの無邪気さというフィルターを通して描かれるジンバブエの現実。軽妙さが逆にその苛酷さを物語るような気がする。
ジンバブエは、アフリカ大陸の南部に位置する国である。周囲を南アフリカ、モザンビーク、ザンビア、ボツワ…




大切な家族だから、最期までキチンと看取るのが飼い主の責任だと思う
お久しぶり!タカラ~ム家のアイドル・ラムよ! 4月の 「世界で一番美しい犬の図鑑」 以来だから…




東京中を東へ西へ。老舗酒場で楽しく飲めば、今日も今日とて二日酔い
最近は、もっぱら家で飲んでいる。お酒のことだ。職場が、都内とはいってもちょっと辺鄙なところにあって、…






《アウシュヴィッツ》という絶望の中で、《本》という希望を守り続けた図書係の少女
アウシュヴィッツ=ビルケナウ強制収容所という場所と、そこで行われていた残虐非道な行為と囚われたユダヤ…





関ヶ原の合戦で徳川家康は死んでいた。その後の人生を徳川家康として生きることになった影武者の壮絶な戦いと生き様を描く
今年(2016年)の大河ドラマは三谷幸喜脚本による「真田丸」が放送されている。先日(9月4日)の放送…




あまりに激しい伊藤野枝の28年にわたる短い戦いの人生
冒頭に、地元の郷土史家である大内士郎氏から聞いたというこんなエピソードが紹介されている。 およ…



![東京人 2016年 08 月号 [雑誌]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51gMRh2%2BcNL._SL160_.jpg)
気づいたら2週間以上ご無沙汰だったので、とりあえずご機嫌を伺っておこうと思います。内容的には、ほぼ「シン・ゴジラ」の話(笑)
しばらくレビューアップしないでいたら、あっという間に8月も終わりじゃないですか。前回の更新が8月14…



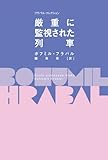
ナチス・ドイツ占領下のチェコ。とある駅を舞台に描かれる人間の本質
ボフミル・フラバルという作家の作品を読むのは、本書「厳重に監視された列車」が初めてだ。 ボフミ…




金権政治の象徴か、不世出の政治家か。田中角栄と戦い続けた著者が描く天才政治家の実像
片手に扇子を持って顔をパタパタと仰ぎながら、ややふてぶてしく憎たらしい傲岸な雰囲気を醸しつつダミ声で…





むかしむかし、遠い宇宙でひとりの少女が新しい命と出会った
人類が宇宙へと足を踏み出してから半世紀以上のときが過ぎた。 人類が宇宙に進出する前から、空想の…





ハンガリー人作家を魅了した街・京都
京都という場所は、訪れる人を魅了する街だ。それは、私たち日本人だけではなく、世界から訪れる外国人観光…





第一藤岡荘五号室、変な間取りのその部屋に住んだ歴代の住人たちそれぞれの交錯しない物語
インターネットでアパートやマンション、一戸建て住宅の間取り図の見るのが好きだ。別に、引っ越しを計画し…




昭和の大衆作家林芙美子を題材に、大胆に想像を加えた小説
太平洋戦争のまっただ中、「放浪記」で大衆小説の寵児となっていた林芙美子は、ジャワ、ジャカルタ、ビルマ…




“音速の貴公子”と呼ばれた天才ドライバーと“プロフェッサー”と呼ばれた正確無比のドライバーの物語
日本が、一番のF1ブームに沸いていたのは1980年代後半から1990年代中盤にかけてのおよそ10年間…




イタリア・ナポリの小島で生きる少年の成長と喪失
本書は、池澤夏樹個人編集「世界文学全集」の第12巻「アルトゥーロの島/モンテ・フェルモの丘の家」に収…




「われわれは明日のジョーである」と言い残して、彼らは北へと旅立った。そこは彼らの理想の国だったのか?
1960年代後半から70年代前半にかけて、学生運動に端を発した革命運動は大いなる盛り上がりを見せた。…





世界で活躍し、その国の人たちと未来のために貢献する日本人は私たちの誇りです
「いい質問ですね」のフレーズが2010年の流行語にも選ばれたジャーナリストの池上彰氏。その池上氏が世…





シンプルかつユーモアのある物語が教えてくれる人間の弱さと面白さ
「すべての道はローマに通ず」 この有名な言葉を残したのが、17世紀のフランスの詩人ラ・フォンテ…





本があって、人が集まれる場所になっている。それだけで図書館なのだ。
図書館をよく利用する。読みたい本はたくさんあるけれど、すべてを購入するわけでにはいかない(経済的にも…