いのちに共感する生き方―人も自然も動物も






アイヌ解放運動と動物保護活動に人生を費やした野上さんの自伝です。世の中にはいろいろなNPO活動があると思いますが、社会システムを変えると言う思想の元にそれを実践した人の生き方が綴ってあります。
自伝ですから、前半の三分の一を生い立ち、学生時代までに割き、残りのページで彼女の人生を捧げたふたつの…

本が好き! 1級
書評数:1680 件
得票数:37558 票
神奈川県に住むサラリーマン(技術者)でしたが24年2月に会社を退職して今は無職です。
読書歴は大学の頃に遡ります。粗筋や感想をメモするようになりましたのはここ10年程ですので、若い頃に読んだ作品を再読した投稿が多いです。元々海外純文学と推理小説、そして海外の歴史小説が自分の好きな分野でした。しかし、最近は、文明論、科学ノンフィクション、音楽などにも興味が広がってきました。投稿するからには評価出来ない作品もきっちりと読もうと心掛けています。どうかよろしくお願い致します。






アイヌ解放運動と動物保護活動に人生を費やした野上さんの自伝です。世の中にはいろいろなNPO活動があると思いますが、社会システムを変えると言う思想の元にそれを実践した人の生き方が綴ってあります。
自伝ですから、前半の三分の一を生い立ち、学生時代までに割き、残りのページで彼女の人生を捧げたふたつの…



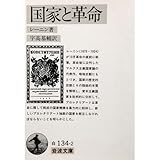
レーニンがマルクスとエンゲルスの理論をもとに彼の国家観を明らかにした書物。ロシアの11月革命直前に書かれただけあり、レーニンの並々ならぬ熱意が文章に見て取れる。
あまり社会主義や共産主義に詳しい訳ではないので、いたるところに出てくる、修正主義、レーニンと同時代の…





サスペンスの名手・J・アーチャーの短編集。O・ヘンリー並みのオチがある短編が15も並ぶ。あれこれ、目先を変えての読者サービスには脱帽。サーガものでは、マンネリズムの兆しがあるが、短編の腕は衰えていない
自分が中学生の頃、民放FM局で「音の本棚」というラジオドラマ番組がありましたが、この番組で長編サスペ…





少年王ルイ14世の秘密を探り当てたふたり。特ダネをものにしようとする新聞記者と組んでさらに調査を続ける。ダルタニヤンとシラノ、マザラン、そして王の叔父オルレアン公。三つ巴の戦いの結末は?
名うての剣豪ダルタニヤンとシラノは、宰相マザランからマリー・ド・カヴォアの監視を命ぜられた。何故マリ…





宰相マザランの指示で動いていたダルタニヤンとシラノ。しかし、ふたりは監視対象のマリー・ド・カヴォアの家に伝わるとんでもない秘密を探り当てた。マザランの指示とは離れていく。王の叔父の陰謀の絡んで・・。
マザランに元王付銃士隊長の娘マリー・ド・カヴォアを監視する様に命令されたダルタニヤンとシラノ。何故そ…





三銃士で有名なダルタニヤン、詩人で剣豪のシラノ・ド・ベルジュラック、ルイ13世亡き後、フランスの最高権力者に上り詰めた宰相マザランが、このふたりに下した指示は・・。
題名のガスコンとは、フランス北西部、ガスコーニュ地方出身者の呼称。二人の、とは一名が剣豪詩人として名…




古代ローマの有名な文人キケロの老年についての考察。4つの観点から老いは怖くない、という分析をしている。長生きが珍しい時代、老いるだけで十分なのか余生を良く生きるところまでの考察まではされない。
ギリシャのデモステネスと並び称されるローマの文人キケロの著作。古代の文書にしては珍しく欠落部分が非常…





植物にも人間同様な感覚、そして知性を持ちコミュニケーションまでしている、と言う見解をまとめた本。ただ肝心の化学物質を介しての「会話」の解読や根端の神経伝達に相当する遣り取りの方法は未解明とされている。
植物に感覚やそれを統合する知性がある、と言う内容の本。まとめれば、以下の様になる。「植物は動かないと…





人類の食糧の増産史をまとめた書物。農業には、ふんだんにある炭素の他にリンと窒素が必要で、これらの元素の活用にいかに人類が腐心してきたか、と言うお話。残念ながら環境破壊と農耕の両立の処方までには至らず。
太陽からの程よい距離、炭素や窒素、リンなどの循環するシステムなど地球環境の幸運さについての説明が2章…





題名の通り、漱石の「こゝろ」の解釈論。一読して納得の内容だった。
Wings to flyさん主催の読書会 100年目に読む夏目漱石 ↑そのままリンク先…






4つの海峡で隔てられている日本海は一種の独立した海で、全地球規模の海洋循環と同様な現象がみられる、と言うお話。今後の地球環境の行方を占うにも日本海の観測は欠かせない。
日本海についての科学的な考察をした本。人間の感覚では海は至る所でつながっている様に思えるが、陸に囲ま…




上巻に続き中世の芸術について分析を進める。特に絵画と詩に関してその精密性を中世の精神と関連付けて分析を掘り下げている。
上巻に続いて中世人の信仰生活、色や形にこだわった象徴主義、日常生活の思考形態を経て、最後に中世の芸術…




名高い中世論。著者が厳選した書籍をもとに人生観、身分制度、騎士道、恋愛観、宗教観などをいろいろな事例とともに分析する。
中世を舞台にした物語は比較的好きなので中世論で名高いこの著書を読んでみました。 本書の根幹は、著…





米SF界の大御所の短編集です。表題作、「時の門」はタイムパラドックスもの。名作「夏への扉」を彷彿をさせる作品
子供の頃に読んだ「四次元世界の・・」 と言った今で言う都市伝説をまとめた様な本に、ハインラインの名…





人間以外の動物が放射能汚染でほぼ死に絶えた地球。生きた動物はまさに貴重品だった。そこに火星から逃げ出した奴隷人造人間狩りの話も絡んで、一種のデストピア小説となっている。
変わった題名だが、映画「ブレード・ランナー」の原作本と言えば聞き覚えのある方も居るかも。自分は、この…





数学の考えまで取り入れて、テクストを99通りに変化させ、言語の可能性を追求した本。原文はフランス語だが訳者の努力により日本語でも楽しめるように非常に配慮されている。
日本でのバッハ研究・演奏の第一人者である鈴木雅明さんの御子息・優人さんが(と言うと大変失礼な紹介の仕…




「ゲイルズバーグの春を愛す」などで知られる作家の短編集。2,3の例外はあるものの、いずれも現在の状況から脱出しようと/してしまったひとたちの話。
時間移動の話が多いが、物理的な説明や、大げさな装置は出てこないし、なぜそうなのかの理由も語られない。…




ユダヤ、キリスト、イスラムの三大宗教を題材にした戯曲。テロの横行する今日、出自を同じくするこれらの宗教がお互いの立場を認め合うことを祈って・・
大学の教養課程の時に取った人文系の科目が、「西洋史」でした。授業も土曜の午前中で、理科系にとっては単…




金持ちの米国人令嬢ベッシーと英国人貴族ランベス卿との間の短い恋愛物語。中編だが話は米英間で繰り広げられる。いずれも民主主義的価値を重んずる国ではあるが、19世紀末、両国の価値観の差異は大きかった。
邦題の「国際エピソード」では何の小説か見当がつきませんが、お金持ちの家に生まれた米国人女性ベッシーと…




本国では有名な叙事詩。テンポ良い訳語を原文のリズムを現している。時代はレコンキスタの過程、スペインの誇り高い英雄の生涯を歌い上げる。
若いころにテレビで放映しているのをちょっとだけ見た映画の原作。スペインのレコンキスタの時代の英雄を扱…