ビーリャの住む森で―アフリカ・人・ピグミーチンパンジー (科学のとびら)





アフリカの姿 / タカルことの意味
狩猟といえば、獲物を追いかけてヤリや弓で殺す方法しか知らなかった数年前の私。 世界中で行われて…

本が好き! 1級
書評数:408 件
得票数:5120 票
言葉は真実を伝えるものではなく、真実の一部または虚構を加工したものでしかない。
「陰謀論にも一理あり」と受け止めることができるようになったことをきっかけに、人の本来のあり方をテーマに本を読んでいます。
https://rubyring-books.site/





アフリカの姿 / タカルことの意味
狩猟といえば、獲物を追いかけてヤリや弓で殺す方法しか知らなかった数年前の私。 世界中で行われて…





仏教とキリスト教の違い、牧畜や屠殺が与える心理的影響、ビルマまで遠征した日本軍に対する現地の反応、捕虜となってもしたたかを持っていた日本人兵士たち。この本は、読み継がれる価値がある。
ビルマの前線で終戦を迎え、捕虜となり、復員までの2年間を収容所で過ごした著者。自らが体験したことだけ…





島は奥が深いと改めて感じさせてくれた
東京都の青ヶ島は、カルデラ式の火山の頂上が島になっています。 独特の地形や、日本一人口の少ない自治…






無人島に漂着し、近隣の島の住民を従僕としたロビンソン・クルーソーとは逆に、夏を一人で過ごすことになった白人の少年はインディアンの少年から学ぶことばかりだった
フレンチ・インディアン戦争(1755~1763年)直後の1768年、米メイン州の森が舞台です。主人公…




メディア絶賛。読者の評価は両極端。果たしてその真価はどこに。
本屋さんで目立つところに面陳列してあり、「絵がないということは文字だけなのかな、それでどうやって絵本…






アリの世界の驚きを教えてくれる幼児~小学校低学年向けの写真主体の本
アリたちのように社会性の昆虫には、社会性の昆虫ゆえの力学があるようだ。 ありまき(あぶらむし)…






未踏破地に生きるマチゲンガ族家族の伝統的な暮らしと文明化の過程は人類史の縮図だ
1972年、文明の波をかぶったアマゾンに、わずかに残された未踏破地があった。そこはインカの遺跡が眠っ…





1970年頃の山里や峠の様子を写した白黒の写真と、写真家自身による紀行文+行き方案内
峠が交通の要衝であり続けてきたこの国では、山は人間の生活と深く結びついていた。近代アルピニズムの目指…





学校になんぞ行かなくてもいい。伝統医療が生きている。多くの食べ物が無償で手に入る。親戚の子を育てる余裕がある。それが、バンコクともチェンマイとも異なる2000年代のタイ東北部。
1971年に埼玉で生まれアメリカの大学に通った日本人女性が、タイで嫁ぎ、義母を頼って東北地方(イサー…




グリコのおまけは時代とともに
1992年発行の少し古い本。収録されているおまけは昭和20~30年代が中心で、40年初めまでが多く、…




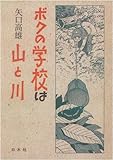
昭和14年に秋田の山村で生まれた著者は、どのような少年時代を過ごしたのだろうか
『釣りキチ三平』でおなじみの矢口高雄さんの著書です。 1987年の発行。子どもたちを取りまく環…





2000年代初頭の牧歌的な時代のお話
2003年の本なので、もう情報が古すぎて役に立たないかと思ったのですが読んでみました。 大型リ…





分かりやすく面白い考古学を提唱した佐原真さんによる、我々の生活に密接している「食」を扱った考古学専門書
1996年の本ですが、もっと古い本のような印象を受けます。本書に現代日本の食生活として描かれている習…




病気や症状を抑圧された潜在的な欲求と見ることで、才能開花への糸口を得る
この本は、症状が私たちに大切なことを教えてくれているという点で『 病気が教えてくれる、病気の治し方―…




命のファンタジーに導かれた、アラスカの日本人とアフリカのイギリス人
44歳で亡くなった伝説の写真家によるフォト・エッセイであるこの本は、研究活動よりも、資金集めや広報活…





昭和55年発行の小さく読みやすいながらしっかりした本。
1980年ころまでの本を読んでいると、とくに著者の熱意の感じられる本がよくあります。この本もそんな一…

「60分で読めるけれど一生あなたを離さない本」と帯にあるロングセラー
まえがきから数えると52ページほどの分量しかないこの本は、多くの読者がまた他の人にも薦めるという名著…




飢えのない社会の異常性や快楽追求の危険性を指摘するも予想は外れた。確かに外れたが、重要な指摘を含んでいる。
1990年の時点で、昭和34(1959)年生まれ以降の人びとだけで構成される社会になったとき、日本の…




いまを生きる子どもたちに向けて、文化人類学の知識・体験を背景に語りかける
著者の波平さんは1942年生まれ、本書は2001年発行。早ければ小学三年生から読めるようにとルビが振…




この本には何かがあるはずなのだが、読むほどに何もないと思えて来る。しかし、まだ何かがあると思わせる。
著者はUFO研究家の竹本良氏。本書はペンネームで著されている。 生命とは何かを問う中で、医の領…