マウントドレイゴ卿/パーティの前に





本書に収められている、木村政則の解説と訳者あとがきは、本編に負けないぐらい、面白くて、興味深いです。
W.S.モームというと、訳者あとがきにも述べられていますが、「いささか通俗的」というのが、少なくとも…

本が好き! 1級
書評数:2281 件
得票数:43628 票
「本職」は、本というより映画です。
本を読んでいても、映画好きの視点から、内容を見ていることが多いようです。





本書に収められている、木村政則の解説と訳者あとがきは、本編に負けないぐらい、面白くて、興味深いです。
W.S.モームというと、訳者あとがきにも述べられていますが、「いささか通俗的」というのが、少なくとも…





『アウルクリーク橋の出来事』は、ロベール・アンリコ監督の映画『ふくろうの河』の原作だというのは知っていましたが...
ロベール・アンリコは、私の世代の映画ファンの多くにとっては忘れられない映画『冒険者たち』(1967年…




本書『ビセートルの環』は、多作家ジョルジュ・シムノンの中でも、批評家には評価の高い作品とのことですが...
本書は、大新聞社を取り仕切る、53歳の主人公、社会的にも成功し、パリ社交界でも知られた男が、突然の脳…






20世紀初頭のパリの下町とそこに生きる人々を、包み隠さず、それでも温かな視線から描いて、正に傑作と呼ぶに値する見事な一冊です。
本書の訳者あとがきによると、シムノンの死後、アメリカの「ニューヨーク・タイムズ」紙がシムノン特集号を…





「ゴダールの映画はひと目で分かる。シャブロルの映画はおそらく分からない。ゴダールは映画を利用しているが、シャブロルは映画に奉仕しているからである。」(映画評論家A.S.ラバルトの言、本書より)
シャブロルは、ヌーヴェル・ヴァーグ誕生当時、ゴダール、トリュフォーと並んで、日本では三羽ガラスと呼ば…
![]()




江戸川乱歩が、黄金期ベスト10に選んだ作品とのことですが、う~ん....どうでしょうか、というのが率直な感想です。
ジョン・ディクスン・カーは、密室物の大家として知られていますが、個人的には、このジャンルはあまり好き…






「彼らはぴったり身を寄せ合っていることに気づいた。愛人同士ということではなく、長い間孤独のなかを彷徨ったあげく、やっと人との触れ合いという思いがけない恩恵を得た人間同士のように。」(本文より)
人生に疲れた、あるいは、愛情を失った、あるいは、愛情というものがどういうものか理解しないで生きてきた…






「パリが目覚めたとき、雨はすっかりあがっていた。昨日までよりいっそう淡いブルーの空からは、柔らかな光が降り注いでいる。屋根からは水がしたたり落ちている。歩道は乾いている」(本文より)
一連のシムノンの書評で、繰り返し述べてきましたが、彼の特徴の一つは、その場の情景を具体的に喚起させて…
![]()



映画007シリーズのように派手ではありますが...。小説としては、展開以上に、表現力が粗くはありませんか。
まず小説全体の構図として、一連の事件に絡む女刑事と伝説的犯罪者の存在は、明らかに『羊たちの沈黙』を踏…
![]()





女性に迫られる中年童貞男のうろたえぶりは、映画『卒業』のダスティン・ホフマンのそれを思い出させます。
本書は間違いなくミステリですし、きっちりした謎解きもありますが、最も印象的かつ面白い部分と言えば、遊…






ドストエフスキーの『罪と罰』に匹敵する、罪と贖罪の物語。
本書は、多作で有名なジョルジュ・シムノンの中でも、評価の高い作品の一つですが、それだけでなく、あらゆ…






至高のカップリング。
メグレ警視のロマン(長編小説)は75篇あるそうですが、一般読者を対象に、仮にメグレ警視ベスト10とい…




ジョルジュ・シムノンの『羅生門』
黒澤明監督の『羅生門』が、ヴェネツィア映画祭でグランプリを得たのは1951年、本書が出版されたのが1…





ジョルジュ・シムノンは、もっと評価されてしかるべき作家です。
ジョルジュ・シムノンというと、日本では、メグレ警視もので有名ですが、何よりも多作家であったことが、特…





子供の成長の物語です。
『北の森から」と題された、このシリーズのテーマは、家族だということは、他の書評でも述べましたが、本書…





タイトルは、作中でのパーティーの余興のゲーム名から来ていますが、これ自体が内容を暗示しています。
ヘレン・マクロイというと、どうしても、あの傑作『暗い鏡の中に』の印象が強いです。本格派という分類に当…





「北の森から」と題されたシリーズの一冊です。
このシリーズのメイン・テーマは、家族です。今回登場するのは、ひぐまの母子で、昼は山ぶどうの実をたっぷ…






「その醜悪な偶像を鏡に見いだしたとき、わたしが感じたのは嫌悪ではなく、むしろひときわ高まる歓迎の気持ちだった。これもまた自分なのだと思った。いかにも自然で人間らしく見えた。」(本文より)
物語そのものは、語る必要がないぐらい、有名です。そして、後世に与えた影響という点では、『フランケンシ…
![]()




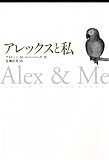
「科学的には、アレックスが私、そして私たち全員に教えてくれた一番大切なことは、動物の思考が、大部分の行動科学者が考えていたよりもはるかに人間と似ているということだ。」(本文より)
犬や猫を飼ったことのある人なら、そういう動物が、何らかの形で「思考」していることに、疑問を持つ人は少…






サイコ・スリラーの古典と言って良いでしょう。
作者が処女作を発表したのが1946年、第3作であるこの小説が発表されたのは1948年です。心理スリラ…