経済政策で人は死ぬか?: 公衆衛生学から見た不況対策





ジャスト・ナウなタイミングでよむと背筋が凍るというか生きた心地がしないというか……。
ジャスト・ナウな題名……だけれど、上梓されたのは2014年(原書は2013年)だ。 衝撃的な書…

本が好き! 1級
書評数:400 件
得票数:2489 票
2011年7月11日よりスタート。
乱読、雑読。献本歓迎。
Blogも始めました。コチラの内容と重複しますが。
【2024年9月追記】
コロナ禍以降、しばらくサボってましたが、また暫くつづけます。Blogは更新してません。





ジャスト・ナウなタイミングでよむと背筋が凍るというか生きた心地がしないというか……。
ジャスト・ナウな題名……だけれど、上梓されたのは2014年(原書は2013年)だ。 衝撃的な書…

物語形式でアドラー心理学を説く。
物語形式でアドラー心理学を説く。 『嫌われる勇気』の影響? コモンセンス、社会貢献という視座を得…

日本のヒップホップとハウス黎明期の話も出てきて読ませる内容。
日本スゲ〜と素直に思えるプロダクトだなぁ。 これがなかったらスクラッチは生まれてなかっただろうし。…

アインシュタインがいかに天才だったか。 研究室に属さず独立して相対性理論を構築した。つまり実験・検証を行わず思考実験で頭脳の中だけで相対性理論を発見したのだ。 これを伝えたいがための本?

日本語には生理作用についてはのんきだが、心的作用には詳しく規定する言語。 懐かしいという表現は英語独語では一言ではない。 日本語の音節によるメロディへの乗せ方なども興味深く読んだ。

なんとなく読むことの多い自分を反省したりした。
テキストのロジック構造を意識して読む。 学んだことを書いて話してアウトプットすることで身につく。 …




論理パズルは面白いけれど・・・
数学的論理学の本だから「Aは常に本当のことを言い、Bは常にウソをつく」といった現実的でない前提のもと…

例示にあげられる曲がデトロイトテクノとかミニマル・ミュージックとかパンクとかでサブカルぽいところが好感。
■ケンダル・ウォルトン「芸術のカテゴリー」 美的判断の相違の一部に知識が関係。→ 本文ではゲルニカ…




コロナウイルス喧騒で読んだ一冊
彼女(注;コロラド大学災害社会学者キャスリーンティアニー)はそれを「エリートパニック」と呼び、…






知的誠実さ…というのがキーワードになるかな。専門家にも、専門家に知見を求める人にも。
この本を読んで要点をまとめるには勇気がいる。 そのまとめサイトのような態度こそが「無知礼賛」ではな…

なぜ日本の都市は景観を重要視しないのだろう? という疑問から読んだ一冊。
欧米旅行を経験してなぜ日本の都市は景観を重要視しないのだろう? という疑問から読んだ一冊。 日本の…

これは公文書でないとかなんとかルールの隙間をついたりというか詭弁バッカをやっているのだな、霞が関の人たちは…という小並感。





『ペスト』を理解するにはベストの一冊
感染症の危機を目前に言葉を軽んじ、「言わなくても分かる」というコミュニケーションを重用する今の日本社…





国会議員をはじめ議員は全員この本を読んだ上で年に一度は「民主主義について」のテストを受けるべきだよなぁ。
これまでにもたびたび述べたように、政治上の制度のうえに現われた民主主義には三つのたいせつな原則がある…




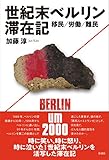
移民として暮らしたマイノリティの視線。マイノリティーのすすめ。
なぜ「本が好き!」の運営はこの本の献本申込抽選を外したのだ! 昨秋にベルリンに十日程滞在した私には…





サブカルチャー・サブカルについてちゃんと踏まえた論考なのでこの手の本にありがちな隔靴搔痒なところがないのがいい!
書名のとおり「カッコいい」とはなにかについて論考した本。 不勉強な自分は著者が人気作家だと途中まで…
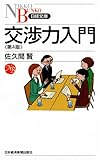
理論書と言っていいと思うのだけれど、であるが故に交渉に臨む同士が論理的に考えて合理的に動くという前提で書かれているなぁ……という印象。
交渉力とは互いの“パイ”を大きくする力。 利害の対立をお互いに満足出来るように問題解決出来る人が仕…

要点としては達意すなわち意味・意図が通じない文が悪文になる。
1960年に書かれた本なので「悪文」に関する感覚が2020年の感覚と乖離しているかと思われたけれど、…

デトロイト美術館に所属されたマダム・セザンヌを巡るいい話。
デトロイト美術館に所属されたマダム・セザンヌを巡るいい話。 公共意識というかアドラー心理学的な発想…




オーディオマニア且つギタリスト向けの本だけど…、そうでなくても面白い。
イカ天キングとして勝ち抜いていた時、賞品を全てアンプにしていたマルコシアス・ヴァンプのアキマツネオが…