真夜中のパン屋さん (ポプラ文庫)




平等な食べ物パン。何故平等なのか、それはこの本の中に。真夜中のパン屋に来るクセのある客(キャラ)が次々と登場して、そして仲間になっていく感じがとてもいい。

本が好き! 1級
書評数:368 件
得票数:405 票
好きな作家&好きな作品(トップ10順不同)
恩田陸 『光の帝国 常野物語』
東野圭吾 『白夜行』
宮部みゆき 『地下街の雨』
荻原浩 『メリーゴーランド』
伊坂幸太郎 『陽気なギャングが地球を回す』
横山秀夫 『第三の時効』
奥田英朗 『サウスバウンド』
石田衣良 『池袋ウエストゲートパーク』
真保裕一 『ホワイトアウト』
薬丸岳 『天使のナイフ』




平等な食べ物パン。何故平等なのか、それはこの本の中に。真夜中のパン屋に来るクセのある客(キャラ)が次々と登場して、そして仲間になっていく感じがとてもいい。




暴対法は世間的には正当な法律と思われていますが、それに一石を投じる作品。
完全に前の『インビジブルレイン 』を忘れてました。ちなみにこれが映画化されたらしい。しかし、読み進み…



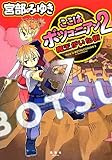
宮部みゆきの愚痴パワー?が本当にパワー全開ですね、はっちゃけるほうで(笑) ボツの世界、ボツコニアン、トリセツが出てくるが役に立たないところなんて現実世界でもありますね。 読んでいて楽しいです。




コーヒー好きな人楽しめるし、京都に馴染みのある人はあそこかとイメージ出来る楽しみがあるが、自分としてはこのキャラたちならもっと違う話が書けたのではないかとそれは贅沢なのだろうか。




宮部みゆきが手を抜いた、いやいや、肩をはらずに書いた感じの本と思う。エッセイというか、宮部みゆきの趣味がところどころにあるし、ファンとしては小学生向けながら楽しく読めた。




邦画がもっと繁栄するヒントがこの中にあると、この中の映画だったら見てみたい!ただ、ミステリーとして読むと物足りなさがある。




主人公の疑心暗鬼を描きながら、警察とマスコミの関係を明らかにしていく手法は面白かった。そして被害者遺族と警察の関係も考えさせられる話だった。




主人公が踏み込んでいくうちに自分もボクシング魅せられるのはそうなんだろうなと、でも、試合の臨場感はもうひとつのめり込めなかった。 読んでボクシングが身近になったように気がした。




陽気な悪魔と、そして自分が生きることによってひとつひとつ消えていく世界、 このなんともいいがたい世界観が、 物語は軽く感じられるが、そこには深い真相が見える。 大きな意味で人生を考えさせられる本。




人間は傷つく生き物だと、わざと傷つけたり、知らない間に傷つけたり、そんなことを振り返らせてくれる物語。 猫とこんな関係になりたいと、まぁ、猫飼ってませんがそう思いました。 いや、泣かせますね。




ただ、ただ、凄い、川崎製鉄を一代で大きくした西山弥太郎は凄いです。 それにしても、昔は官僚もいい働きをしていたのだと、つくづく思います。これこそ国を栄えさす、官民一体ですね。今の官僚に見習ってもらいたい





人はだれもが不正をしようとは思ってない、だが、魔がさすことはある。そんなことを描いた、人間ドラマだ。また会社を中心に物語は進むが、そのそれぞれの妻の立ち位置が微妙に違って、そこにも物語があるのだと。




読みやすいし面白いと思ったなのだが、なんとうか演出感というか、驚き感というか、それがもう少しあればもっと面白くなるのになと、アイデアは面白いと思った。




あのたぬき高階病院長の初丸投げ、そしてあの速水、彦根が駆け出しの頃、そして最後の天城と海堂尊ファンとしてはワクワクしたが、白鳥・田口コンビが出てこないのがちょっと寂しかった。



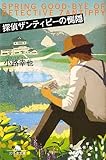
普通の日本の探偵がするとなんでもない話しですが、これがザンティピーがやるとなんとなくいいって思ってしまう。キャラ読みしているんでしょうね。





よく犬は人間お友達、これよ読むとそれがよく分かる。
野良犬して生まれて短い生涯を終えたと思っていたトビーは、また子犬になっていた、そう生まれ変わ…



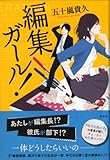
仕事とプレイベートの板挟みとあいながら、初めての編集だが自分を信じて進んでいく主人公は応援したくなったが、なんというかあらすじは面白いのだが、ちょっとあっさりしているなと、まぁ、その分さらっと読める。




あの山崎豊子さんの「華麗なる一族」を彷彿させる。 倒産してもおかしくない、無謀と言われた資本金5億の会社が百六十三億の投資してつくる千葉工場、いろんな苦難がまだまだ続くようだが、どう切り抜けていくのか。





実名の武将たちの史実を織り交ぜて、架空人物、石堂一徹を縦横無尽に動き回られたのは読んでいて楽しかった。このまま話を続けても面白いと、いや、続けてほしいと切に思った。




ドラマの影響なのか段々と湯川学が福山雅治近づいとというかやさしくなったような気がしていましたが、最後の『猛射つ』では、昔の湯川学が戻ってきたと感じました。