首無の如き祟るもの




解決に解説を重ねて、こうもああも、取れますね?と全ての可能性を潰していこうとしており 解説しすぎるというか、説明しすぎるというか… とにかく回りくどいのがこの作家の特徴かと。
「刀城言耶」シリーズ。といっても、語りは当時の捜査担当巡査の妻であり作家の、高屋敷妙子。 この辺り…

本が好き! 1級
書評数:283 件
得票数:905 票
引っ越し後、仕事が忙しく、読書はしても感想が書けなかったのですが、久しぶりに復活できたらな…と。映画好きの雑食ですが、今は面白いホラーを探しています。




解決に解説を重ねて、こうもああも、取れますね?と全ての可能性を潰していこうとしており 解説しすぎるというか、説明しすぎるというか… とにかく回りくどいのがこの作家の特徴かと。
「刀城言耶」シリーズ。といっても、語りは当時の捜査担当巡査の妻であり作家の、高屋敷妙子。 この辺り…



軽快に読める…と言う意味ではいいのでしょう。 さくっと読みたい人にはお勧めです。 それがこの作家の良い点なのかもしれません。
畠中恵の作品から妖怪を抜くと、こういう作品が出来るようです。 読了後の、率直な印象… 「軽い…
![]()





ぴりっとスパイスが利いているお店がずらり! エッジの利いたデザインにノスタルジックなモノ… どれもこれも魅力的!!
パッと目を引く赤に青い帯、ちょこんと載っているユニオンジャックなソファー! これぞロンドンという装丁…






芸術が、アートがこんなに溢れている現代でさえ、若冲の作品は奇想天外で斬新。 当時の江戸の人たちはどんなに驚いたことでしょう。
伊藤若冲は江戸時代中期に活躍した絵師です。 小さいころから絵が好きで、暇があれば絵をかいていたそう…





ルドゥーテはいくつか植物図譜を出していますが、その中でも本書「バラ図譜」は ナポレオンの皇后ジョゼフィーヌの庇護のもとに刊行され、植物画の最高傑作と言われています。
どうしようもなく好きなものの中に、ボタニカルアートがあります。 ボタニカルアートとは、ざっくり言え…






躍動的でありながら優美で、上品な女性像。 草花をモチーフにした幾何学的な装飾はファンタジックでロマンチック! 細部まで精緻に描きこめれた文様は、もう、ため息ものです。
アルフォンス・ミュシャは19世紀末から20世紀初頭、アール・ヌーヴォーの 代表的画家であり、グラフ…





「黄金の時代」の金箔をふんだんに使用した荘厳な作品も素晴らしいのですが 私は「医学」をめぐる逸話が波乱に満ちていて大変興味深い。
グスタフ・クリムト。 彼もまた大きく好みが分かれる作家ですね。 名前を知らなくても、絵画に詳しく…





大判で高価ではありますがデザインに携わる方なら、押さえておきたい1冊かと。 グラフィックデザインの教科書ともいえる作品集です。
デザイン界に大きな足跡を残した偉人、亀倉雄策。 東京オリンピックのポスターを手掛けたことは、有名す…






モノクロで描かれているのに、背景に色を感じるような華やかさがあります。 この圧倒されるような躍動感のある…それでいて上品な作風は群を抜いています。
ボルドーの布表紙に金色の箔押しで描かれた女性。 帽子の下からのぞく、意味ありげな視線。指先にきらめ…





コミックの形式をとっていますが、ビジュアルブックや画集のような趣の作品です。 まず、装丁が徹底して凝っている!
学生時代、妙にツボで好きだった水野純子。 今見ると…若かったな…。と、つくづく思う。。 6% D…





インパクトが強いので、目にした作品も多いはず! 沢山の商品の中から、ばっと目に飛び込んでくる「インパクト」はこの作者の魅力でしたね。
学生時代、まあ、若野桂が大好きでした! 引っ越しで当時買ったこの本が出てきたのですが 大胆な構図…





澪自身に大すぎる事件はなかったので「閑話休題」のようなムードも漂っていましたが やっぱり続きが楽しみです。
いくら人気といってもシリーズも5作目まで来ると、マンネリ化したりだれたりするものですが この作品は…





人間の悲哀をうまく描き、エンターテイメント作品としてはとにかく出来がいいと思います。 難を言うならラストにもうひとつ重さが欲しかったかな?と。
1988年に刊行された作品で、第10回吉川英治文学新人賞受賞作だそうです。 当時には目新しく、一般…
![]()





悪者を倒しました=みんな幸せになりました、という方程式に則らず 苦境を脱するには、何かしらの対価を払う… ご都合主義過ぎていないところに好感が持てます。
設定が見覚えあるな…と思っていたら、3巻まで読んでいたシリーズでした。 1巻では魔使いの見習いになっ…




この話自体、しっかり完結していますが、良くも悪くも最後まで 「しゃばけの番外編」いった印象が拭えませんでした。
ほのぼのしていて、じんわり感動して… 面白いのです。 たしかに面白いのです。 でも、これほど似…
![サンデー毎日緊急増刊 東日本大震災 2011年 4/2号 [雑誌]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/615prStFAzL._SL160_.jpg)
地域が偏っている印象を受けました。 発行は4月2日。 時期的にもすべての地域で資料を提供できるわけでは無かったのでしょう。
この本表紙を目にしたとき、私は耐えられるのだろうか?と不安だった。 ここに載っているであろう土地は…




裏家業の方は中盤までは放置の御様子。 と言っても、この巻では大きな流れで一貫していたので終盤にはぴりっと大立ち回りがありました。
鰹の刺身というと、生姜醤油か山葵醤油しか思いつかない私ですが 本作の中では、蓼酢、辛子酢、辛子味噌…




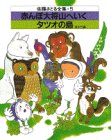
前作はシュールといいますか…斬新なイメージが強かったのですが 今回は昔話を踏襲しているためか、タッチュン達に慣れたのか すんなり受け入れられ、やり取りも楽しめました。
前回感想を書いた「海へ行った赤んぼ大将」の続編です。 (実際読んだのはタツオの島などの短編が載って…





作者ならではといいますか、この時代ならではといいますか エレクトリカルなテイストと、どこかローカルな雰囲気が融合した作品。
今回被災しまして、避難していた先が小学校だったので 眠れずに早朝に起きた時など、図書室へ通っていま…




序盤の逃走劇の後、緩やかな流れの中でも、じわじわと広がる不協和音。
怒涛展開のまま、中巻へ入りました。 ここを切り抜けるまでは目を離すことが出来ない!!とぐんぐんペー…