竜の学校は山の上 九井諒子作品集






お忘れかもしれませんが、今年2024年は「辰年」です。「竜関係の1冊を」ということであれば、本書を推します。
「ダンジョン飯」シリーズ(実は未読)の完結とアニメ化で話題の作家さんの初期の作品集です。表題作を含…

本が好き! 1級
書評数:696 件
得票数:8276 票
学生時代は書評誌に関わってました。今世紀に入り、当初はBK1(現在honto)、その後、TRCブックポータルでレビューを掲載してました。同サイト閉鎖から、こちらに投稿するようになりました。
ニックネームは書評用のものでずっと使ってます。
サイトの高・多機能ぶりに対応できておらず、書き・読み程度ですが、私の文章がきっかけとなって、本そのものを手にとってもらえれば、うれしいという気持ちは変わりません。 特定分野に偏らないよう、できるだけ多様な書を少しずつでも紹介していければと考えています。
プロフィール画像は大昔にバイト先で書いてもらったものです。






お忘れかもしれませんが、今年2024年は「辰年」です。「竜関係の1冊を」ということであれば、本書を推します。
「ダンジョン飯」シリーズ(実は未読)の完結とアニメ化で話題の作家さんの初期の作品集です。表題作を含…






現役の中学生に「中学時代で後悔していることはなんですか」と聞かれたら、「筒井康隆をほとんど読んでこなかったこと」ときっぱり答えてみたい。
親本は1989年刊行とのことですから、はや30年以上前の作品となります。今なお、定期的に話題になる…






「これで完璧になったかどうか、確信はない。歴史を正しく書くことの難しさは実感している。」(「あとがき」、361頁)
「終戦の日」の日本を取り上げた最も有名なノンフィクション。8月14日正午から、ポツダム宣言の受諾の…






「日米開戦というテーマは多くの人の関心を引くものであるが、同時に人々が自分の想いや立場をそこに反映させやすいテーマでもある。」(「おわりに」より、239頁)
刊行時に、日米開戦の意思決定に行動経済の視点を持ち込んだ新展開として話題となった1冊。同じ新潮選書…





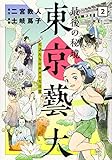
「僕に芸術はわからない…!」(第1巻より)
ベストセラーエッセイのコミック版です。 同名の原作 は2016年、 文庫化 が2019年で、コミッ…





本書の親本が日本で刊行されたのは東日本大震災の直前。文庫版表紙の写真は「東日本大震災で被災した南三陸町防災庁舎」である。
著者の専門は数学で惑星等の運航予測の研究をしている。地震や火山といった個別災害の専門家ではなく「予…





「この物語はこれまでの著者の作品の中で、一番『普通』の話です。(中略)あえて繰り返したいほど『普通』。」(345頁、藤田香織、文庫版「解説」)
ウラスジによると「姫野文学の隠れた名作」とのことです。親本は1996年刊行、新潮文庫に入ったのが1…





「痩せて、背の高い、黒い服の男がやってきて、耳もとでささやいた。/悪魔について書きませんか?」(あとがき、204頁)
1991年刊行、著者51歳の作品。現在は講談社学術文庫にも収録されています。「現代新書」判が貴重な…





MLBのボールパークにも、京都にも、そして埼玉のたんぽぽ球場にも決戦はある。
「野球の楽しさ再発見! 野球で挫折した人大歓迎! 元高校球児が丁寧にコーチします」(7ページ) …






本書の裏表紙には「交通安全」のたすきをかけ、二本足で立ったクマの像の写真が掲げられています。
裏表紙の写真を見る限りでは、「とんでも」な博物館たちを紹介しそうな趣向ですが、内容はいたってまじめ…





「海浜に住む者が、海の音を気にしないように、街中に住む者も、街の音は気にしない。」(「銀座のジンロク」の書き出し、51頁)
著者は『魚河岸ものがたり』で1985年の直木賞を受賞。本書は「受賞後第一作」という位置づけのようだ…






「墳墓が体系化された中国の周代以後、地獄の沙汰も権力次第であったが、今日世界の巨大都市は、先進国、発展途上国を問わず、あの世の沙汰は金しだいになりつつある。」(序、iii - iv)
『アジア厠考』 と対で企画された1994年刊行の書籍である。おそらく、カワヤといえばフンもでしょ…





「世に食糧経済学はあるが、出もの経済学はない。食文化論はあっても、厠文化論は寥々たるものだ。」(「序 厠学の問題」より、冒頭)
著者陣の専門は、経済学から政治学、社会学、文学などバラバラではあるが、共通しているのはアジア各国で…





「そのぼくが、知力のすべてを傾けて戦わなくてはならない相手は、・・・(後略)」(152頁)
こちら「本が好き」サイトでの紹介で存在を知った1冊です。あの有名作家が、あの有名私立探偵の、パロデ…






「日本の社会学者たちが現実と格闘してつくりあげてきた成果を、私たち自身が人間と社会をより深く理解するために用いようとする工夫や努力を、どれくらい試みてきたであろうか。」(編者まえがき、v)
戦後日本の社会学者16名を取り上げ、その社会意識論研究を紹介・検討する論集である。 タイトルに…






「その瞬間から(といっても、ボストンを離れるまでは心のなかだけで)、わたしは自分のことをフリモントと呼ぶようになった。もはや、キャロラインではなく!」(13頁)
最近、近くの図書館で「リサイクル本」と称して、それなりの数のハヤカワ文庫が放出されていました。現在…





「都市と建築の中間に存在する街並みのありかたに関する実体論的段階の本である」(正編の「あとがき」278頁)
親本の正編が1979年、続編が1983年の刊行。私の手元にある岩波同時代ライブラリー版はいずれも1…






「でもわたしはちがう。わたしは自分で決めて自分で行動する。そしてその結果は自分で引き受ける。」(式部の君があてきに、197頁)
2024年のNHK大河ドラマは紫式部が主人公とのこと。政争は相当ありそうですが、戦闘シーンはないの…





「経済学への入門は経済学を超えることにもなる」(はしがき、10頁)
むかしむかし、経済学を講じる教員から、「経済学は近経やマル経だけではなく他にもある」ということを何…






この物語に別の結末はありえなかったのだろうか。
2021年の刊行の、芥川賞候補ともなった小説。舞台は2020年3月、コロナ禍の最初期で、ちょうど学…