ジャパン・ハンドラーズ―日本を操るアメリカの政治家・官僚・知識人たち

恋愛もののスカスカな本ばかり読んでいて国際政治には全く興味がない若者ならば、一目見ただけではこのタイトルが意味することすら分からないのだろう。
副島国家戦略研究所の研究員である著者の中田さんは、まだ20代の青年だという。2005年5月初版。 …

本が好き! 1級
書評数:981 件
得票数:2069 票
“書いとかないと忘れちゃうから「読書記録」”を書いています。
私が書いているのは、一般的な書評ではありません。自分にとって印象的だった箇所を書き出して、それについて書いているだけです。
ジャンルは、偏らないように、あえてバラバラですね。
過去に自分のブログに書いたものの内、いくつかをここに掲載しています。リンク元のブログは他著作へのリンクが機能しているので、興味がある場合は、書評掲載URL を辿ってそちらを見てください。

恋愛もののスカスカな本ばかり読んでいて国際政治には全く興味がない若者ならば、一目見ただけではこのタイトルが意味することすら分からないのだろう。
副島国家戦略研究所の研究員である著者の中田さんは、まだ20代の青年だという。2005年5月初版。 …
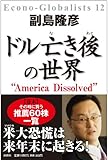
アメリカが計画しているシナリオやその仕掛けなど、書かれている基本的な内容は『すでに世界は恐慌に突入した』船井幸雄・朝倉慶(ビジネス社)と同じであるけれど、副島さんのこの著作の方が、先に出版されていた。
証券や債券に投資して運用しているお金持ちの皆さんが、この書籍や 『すでに世界は恐慌に突入した』 を読…

北京オリンピック終了後に中国は衰退すると語る人々が多い中で、副島さんは真反対のことを語っている。
その根拠は、世界的な景気後退を引き起こしたリーマンショック後、すでに中国経済が上向きとなっていること…

『歴史に学ぶ智恵 時代を見通す力』 よりも先に出版されていた書籍であるけれど、その書籍で言及されていることが、より具体的に分かりやすく記述されている。
【日中戦争を企画するAEI と 日本側受け皿人間の一大結集】 アメリカン・エンタープライズ・イ…

幕末に近い頃の江戸時代。日本全体を覆っていたであろう、儒学嫌悪の空気(ニューマ)が分かりやすく記述されている。
そして、真正な日本民族の精神の発露として成立したかに見える明治維新成功の背後にあったイングランド。そ…

アメリカの深謀遠慮に関わる国際情勢は、私のような一般の日本人にとって、第一級の推理小説よりも遥かに面白い。
基軸通貨ドルという最終ライン防衛をめざして見境のなくなっているアメリカ。アメリカ帝国のエンディングに…

インターネットに書いてきたコラム を編集した著作だという。日本とは違う国で育ってきた人だからこそ出てくる発想が、日本人に角度の違った気づきをもたらしてくれる。2007年4月初版。
【「いじめ」が自殺につながらないための処方箋】 このテーマは、一番反響が大きかったらしい。 …

副題にある通り “新しい時代の生き方” を指南しているのであるけれど、旧世代の教育者や経営者ならば、タイトルを見ただけで 「唾棄すべき書物」 と決めつけることだろう。
現代という時代状況にあっては、誰かれ問わず、偏見を排して一読に値する “生き方論” であり “社会論…

宋さんは来日して25年。自分で興した会社を上場させた実績のある方。コンサルタント業もしているらしい。ビジネス書のコーナーでは良く見かける。
著者名は宋文洲さんとなっているけれど、田原総一朗さんとの対談である。2010年3月初版。 …

国際関係を見る上での基本的な事柄を書き出しておいた。
【バビロン捕囚以降のユダヤ教の変質】 飛鳥 タルムードは元々なかったんだね。あれ、バビロンの捕…

やや眉唾的な情報に思える箇所がある。
このような本にはトンと興味がない。なのに読んだのは、竹島問題がニュースになるたびに、このチャンちゃ…

ロジック探しを意図して、前半部では、鍵になりそうな個所をチェックしながら読んでいたのであるけれど、それらは悉く外れていた。凄い構想である。
先んじて映画を見ていたわけでもないし、書評を通じてストーリーの概要を知っていたのでもないから、ロジ…

この作品は、 『リング』 の続編なのであるけれど、最初から 『リング』 ~ 『らせん』 ~ 『ループ』 という全体構想があって書かれたものではないという。それにしては、あまりに見事なつながりである。
『リング』 よりさらに面白い。特に終盤近くになったら最高である。 『リング』 の初版は91年…

この小説が映画化された当時、職場の何人かが 「小説の方が怖い」 と言っていた。今でも映画は見たことがないけれど、この小説、それほど怖いとは思わない。
貞子のような怪異に近い因縁話は、子供の頃からいくつか聞いたことがあったからなのだろう。面…

著者は、 『リング』 『らせん』 『ループ』 といったベストセラー小説を著した方だけれど、子どもに接する機会が多かったので、教育の分野でも意見を表明するようになったそうである。
タイトルの問いを、自分自身に問うたことのある人ってそんなに多くないことだろうけれど、教育する立場にあ…

第三の目は、一般的には “眉間にある霊性の目” を意味するけれど、本書は、一つ目となってしまいやすい職業(鍛冶・製鉄)を辿って、忘れ去られた古代神(埋没神)に再び光をあてようとしている。
一回通読しただけだけれど、しばらくして再読したら別の発見がありそうな書籍である。 『隠れたる日本霊…

かなり前に読み終わっていたけれど、読書記録を書かずに放っておいた著作。スピリチュアルな視点を取りこんだ科学的内容を期待したけれど、それには殆ど沿わない感じだったから。
それでも、隅が折り返してあったページを読んで、今さら読書記録を書いてみた。2011年4月初版。 …

スピリチュアルな著作において、チャクラといえば、第1のムラダーラから第7のサハスラまでのことが記述されているものだけれど、この本では、第8から第13のチャクラに関することが記述されている。
【第8のチャクラ】 自我に関わる7つのチャクラだけでは、 シフト後の世界には対応できませ…
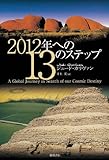
英国人の著者が、2003年以前に世界を巡って精神世界を認識しつつ、自らの魂も覚醒させていった旅の様子が描かれている。2010年1月初版。
【アヌンナキ】 古代シュメール人の神話には、爬虫類に属するアヌンナキという地球外生物が、太陽系…
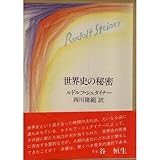
89年5月以来の再三読。ギルガメッシュとエンキドウの話を起点として、霊学的視点で世界史のエポックとなる人物と時代が相関的に記述されている。
【神話・伝説の意味】 通常の歴史学で明らかにされている時代よりも、数千年溯るだけで、人間は多か…