狼の幸せ





コニェッティはデビュー作『帰れない山』以来、作家本人を思わせる一人の男の目を通して、山で生きる厳しさと愉しさを描いてきたが、今回は四人の男女の視点を借り、山で生きる男と女の関係に迫っている。
ミラノ生まれの作家、パオロ・コニェッティは子どもの頃から夏になると一九〇〇メートル級の山地にあるホテ…

本が好き! 1級
書評数:317 件
得票数:6342 票
散歩と読書の毎日。心に残った本について、心覚えに書評らしきものを書いています。
外国文学が好きで、よく読みます。





コニェッティはデビュー作『帰れない山』以来、作家本人を思わせる一人の男の目を通して、山で生きる厳しさと愉しさを描いてきたが、今回は四人の男女の視点を借り、山で生きる男と女の関係に迫っている。
ミラノ生まれの作家、パオロ・コニェッティは子どもの頃から夏になると一九〇〇メートル級の山地にあるホテ…





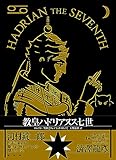
こんなに面白いのに「賞賛を受けたり影響力があったりしても当然なほど素晴らしいのになぜか見落とされている書物」として、長い間、世間から無視され続け、邦訳も今まで出ることがなかった問題作の本邦初訳。
今年の翻訳大賞はこれで決まりだ。もう何年も前に『コルヴォー男爵を探して』(A・J・A・シモンズ、河村…





世紀末の世界中の大都市を舞台に『テンペスト』、『ハムレット』、『ロミオとジュリエット』を下敷きにし、子どもの頃に師によって指環の呪縛を受けた魔法使いの弟子たちが命がけで愛を紡ぎ、技を競い合う物語。
十九世紀末から二十世紀初頭にかけて、ロンドンを拠点として世界各地を飛びまわるサーカスがあった。<ル・…





マラヤはキャメロン高原にある「夕霧」という名の日本庭園にまつわる男女の物語。突然姿を消した男との過去を封印した女は、自分の記憶が失われる危機に陥り、かつての記憶を呼び覚まそうと思い出の地を再訪する。
テオ・ユンリンはマラヤ連邦裁判所判事を定年まで二年残して辞職した。誰にも言わなかったが、少し前から突…





廃棄された古書の山の中から掘り当てた一冊の詩集が、時空を超えた人と人との邂逅をもたらした。古書ミステリとSFとラブストーリーが混然一体となった魅力的な小説。
ロンドンにあるアパートの一室で本に埋まり、ネットで古書を売っている「私」は、有名な古書店の閉店に伴う…






過去に偉大な文化を擁しながら、行路にはかつてを偲ぶよすがとてない。荒れ寂れて人も通わぬ道も、かつては隊商が駱駝に乗って通った道である。歴史家として彼はそこに何を見ていたのだろう。
二〇〇〇年のある日、ローリー・スチュワートは故郷のスコットランドを散歩していて、ふと、このまま歩き…





三十歳でスランプに陥って書けなくなった作家が、春から秋にかけて山小屋でひとり苦闘した日々を綴ったもの。『帰れない山』を発表する三年前のことを綴ったもので、小説ではないが、その前日譚の趣きを持つ。
人里離れた場所にひとりで暮らす生活に憧れる。昔のことになるが『独りだけのウィルダーネス』という本を読…





クリスマス・イブ、三人の死者から切断された六本の指が、次々と発見される。『ストーンサークルの殺人』で初登場したワシントン・ポーが分析官のティリーと組む、シリーズ第三作は、今までの中での最高傑作。
国家犯罪対策庁重大犯罪分析課(NCASCAS)の部長刑事ワシントン・ポーと同課分析官ティリー・ブラッ…





内戦からフランコ独裁政権というスペインの暗黒時代を背景に、史実を大胆に脚色し、入れ子状に構成された物語世界のなかで「ミステリ」と本をめぐる「メタフィクション」を融合させた、他に類を見ない稀書。
《上・下巻あわせての評です》 『風の影』『天使のゲーム』『天国の囚人』に続く「忘れられた本の墓…






人は弱いもので、時に愚かしい真似もするが、それでも人生は生きるに値する。どんな苦境に陥っても、人は一人きりではない。こんな時代、こんな世界だからこそ弱さや愚かしさを嘲るのでなく、そっと寄り添いたい。
三分の二は逃げそこなった、と思っている。彼とスーザンは――スーザンには息子のザックも合算して――一…

当時の日本は、戦争に駆り立てられていたように見えるが、果たしてそうだったのだろうか? 日本の戦争遂行能力を正確に把握していた者は一人もいなかったのか。仮にいたとしたらその結果はどうなっていただろうか
一八九九年の夏、南下を続ける帝政ロシア軍の狙いと開戦の可能性を調査せよ、という参謀本部の命を受け、高…




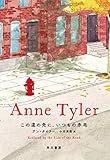
派手なところはまったくなし。可もなく不可もなしという中年男の日々が淡々と描かれる。こういう生き方を歯痒いと思う人にはまったく向いていない小説だが、こういう人生に共感する読者もいるのではないだろうか。
「マイカ・モーティマーのような男は、何を考えて生きているのかわからない。一人暮らしで、付き合いが少な…





見えない月を追いかけた。一度はその目でたしかに目にしたが、今はもう見ることはない。しかし、そこにあることは知っている。見えてはいないが、それはそこにある。自分はそれを知っている。それでいいではないか。
吹けば飛ぶような、将棋の駒に命を懸けた二人の若者の短すぎた青春を悼む鎮魂曲。一人は棋士を、もう一人は…






人に知られた悲劇、喜劇を換骨奪胎して一つに縒り合わせ、マギー・オファーレルは一篇の小説に仕立て直した。これはある「比類ない人」に捧げる一篇の叙事詩なのかもしれない。
髪を飾る花冠のために野に咲く草花を摘みに行く話といい、双子の兄妹の入れ替わりといい、魔女の予言によっ…





熟練スパイが組織の手を頼らず、自分が築き上げた人脈だけを使って、国家を揺るがす重大な機密漏洩事件を引き起こす。「一寸の虫にも五分の魂」を地で行った、ル・カレには珍しい、後味の爽やかなスパイ小説。
冷戦が終わったとき、これでスパイ小説も終わった、とよく言われた。米英を中心とする資本主義諸国と旧ソ連…





他のゴシック小説が次々と訳出されたのに本作は、ほぼ半世紀遅れての本邦初訳である。どうして今まで訳されなかったのだろう? 長丁場を最後まで付き合うと、その答えらしきものに出会えると思う。
《上・下巻合わせての評です》 待つこと久しというが、これほど長く待たされると、待っていたことさ…





その詩に感動した作家は、同じ人間がどうして世界のできごとに無関心でいられるのか、理解に苦しみ、小説を書くことでその疑問に答えようとした。ジョゼ・サラマーゴによるフェルナンド・ぺソア批判と言える。
存在したこともない人についてこんなふうに語るのはばかげていると言われたら、僕は答える。リスボンや…





史実を生かしつつ、実在の人物と架空の人物を絡ませることで、宗教裁判と黒死病、大聖堂建設という国家的規模の厄災に見舞われた当時の人々の姿を剔抉し、それにもめげず愛を貫き通す一組の男女の姿を描く。
一七一三年、ポルトガル王ジョアン五世は、首都リスボンの西、マフラの地に宮殿、修道院、大聖堂からなる壮…






「もしわれわれが全員失明したらどうなる?」という問いを思いついた作家はそれに答えるように考えた。「だけど、われわれは実際にはみんな盲目じゃないか!」。パンデミックを題材に、人間の真実を描いた寓話。
コロナ禍で、多くの人がパンデミック小説の存在に気づいたらしく、カミュの『ペスト』が話題となったが、こ…






「象は、大勢に拍手され、見物され、あっという間に忘れられるんです。それが人生というものです」作家も同じだ。あちこち引っ張り回され、見知らぬ人に愛想をふりまき、忘れられる。アイロニーに満ちた畢生の大作
フランシスコ・ザビエルが日本を訪れた頃の話。彼を派遣したポルトガル王ジョアン三世は、舅であるスペイン…