ビジュアル 職場と仕事の法則図鑑





一般的なビジネス書や自己啓発的な内容でなく、学術的な研究に裏付けられた内容がコンパクトにまとまっている。 参考文献が最後にまとまっているが、原典として各ページに掲載してあるほうが良かった。

本が好き! 1級
書評数:225 件
得票数:920 票
自己紹介文がまだありません。





一般的なビジネス書や自己啓発的な内容でなく、学術的な研究に裏付けられた内容がコンパクトにまとまっている。 参考文献が最後にまとまっているが、原典として各ページに掲載してあるほうが良かった。





地球歴2400年代。火星に入植、太陽系圏内にも進出した人類。伊藤計劃『ハーモニー』を思い起こさせる雰囲気の体内ナノマシン等が普及したテクノロジー系、恋愛宇宙SF。





大学入試改革に伴う今後の教育のあり方についての連載をまとめたもの。 ところが刊行前に改革自体が暗礁に乗り上げ、さらに刊行後にCOVID19による混乱。 それでも本書で述べられていることは未来を向いている。






ミルグラムの「6次のつながり」から始まり、社会ネットワークが、社会学、情報技術、感染症、停電や災害、経済学、マーケティングなどを縦横無尽に巡りながら語られる。研究書かつ自叙伝のようなつくり。




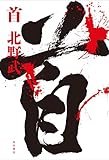
北野武(ビート武)の初時代小説。 織田信長に謀叛を起こした荒木村重は実は明智光秀にかくまわれていた、という設定で、本能寺の変と秀吉の大返しまでが軽い文体で描かれている。 中の扉絵は北野武の絵画。




Wシリーズ5作目。。






イギリス在住ライターのブレイディみかこ、経済学者の松尾匡、社会学者の北田暁大の3名による鼎談本。 ブレイディさんのヨーロッパ政治経済の知識と、松尾さんの経済学をベースに、北田さんが整理している感じ。
「アベノミクス憎し」で経済政策が混迷している左派に警鐘を鳴らしている。 第二次安部政権のアベノ…





![図解入門業界研究最新半導体業界の動向とカラクリがよ~くわかる本[第2版] (How-nual図解入門業界研究)](https://m.media-amazon.com/images/I/61rBlhYKS3L._SL160_.jpg)
半導体の歴史、仕組み、活用方法や関連メーカーなどを整理した初心者向けの良書。






組織において、人はなぜどのように動くのか。またはどうすればどう動かせるのかについての本。 人事評価やリーダー論、モチベーションや組織文化など。
「人が集まってみんなで考えることは、各自がバラバラで考えるよりパフォーマンスが悪い」や「組織文化を浸…






タイトルは自己啓発本っぽいが、ホームレス問題の実態と、その解決を目指す団体ホームドアの設立から本格運営開始までの自伝的エッセイがミックスされた本。




人事評価制度を賃金や待遇を決めるためのものでなく、リーダー育成や経営戦略に沿って従業員の方向性を合わせる手段と捉えて導入することを薦めている本。
人事評価制度を賃金や待遇を決めるためのものでなく、リーダー育成や経営戦略に沿って従業員の方向性を合わ…




人事評価制度を構築する際に、リーダー級も交えて策定し、評価と合わせて面談をすることを提案している本。





『世界の歴史』シリーズ(中央公論社)をベースにしているなど根拠がしっかりしていて新説が面白いものと、いまいちなものが混在しているが、一番有用なのは、世界史と日本史の比較年表。
『世界の歴史』シリーズ(中央公論社)をベースにしているなど根拠がしっかりしていて新説が面白いものと、…





旧約聖書の源流にもなっているシュメル神話についての本。
旧約聖書の源流にもなっているシュメル神話についての本。 例えば「ノアの方舟」では大洪水が起こるが、…





中小企業診断士の二次試験試験委員の著書ということで、受験者の中で試験対策として推奨されている本。
中小企業診断士の二次試験試験委員の著書ということで、受験者の中で試験対策として推奨されている本。 …






「花子とアン」の村岡花子訳。 某国内MBAスクールで「経営倫理」の教科書に指定されていた。 強欲で自分勝手な主人公のおじさんが不思議な体験を通して心を入れ換える話。




タレントは芸能人でなく才能のこと。 タレント・マネジメントの本。
タレントは芸能人でなく才能のこと。 タレント・マネジメントの本。 人的資源論、組織論だけでな…


スピノザの『エチカ』の超超超訳版。




『会社四季報業界地図』(東洋経済新報社)や『日経業界地図』(日本経済新聞社)の簡易版。 文庫サイズで、各業界について平易な説明と、業界上位3--~5してか掲載されていない。





1~3部からなる。 1はマルクス・ガブリエルから見た日本について。 2部はテレビ放送の書籍化。 3部は人工知能ロボット研究者との対談。
1~3部からなる。 1はマルクス・ガブリエルから見た日本について。 2部はテレビ放送の書籍化。 …