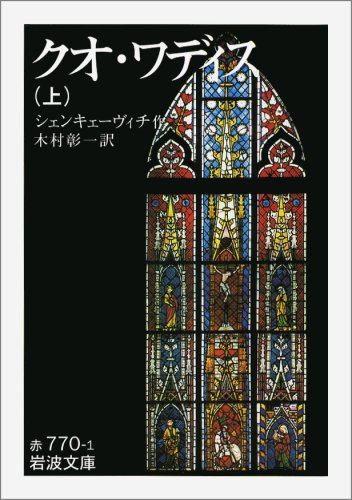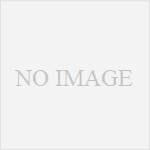ぷるーとさん
レビュアー:
▼
ネロ皇帝時代のローマを舞台に、青年貴族とキリスト教徒の女性の愛と信仰を描いたした歴史大河小説。
3巻合わせての書評です。
『クオ・ヴァディス』は、ローマの若き軍団将校ウィニキウスがキリスト教を信仰する女性を愛し、自らもその信仰に惹かれていくという話で、その背景として、暴君ネロの乱れきった政治、キリスト教徒に対する迫害などが描かれている。
ウィニキウスは、知人の館で見知った女性リギアに恋をし、何とか彼女を手に入れたいと叔父のペトロニウスに相談する。ペトロニウスは、気まぐれなネロの寵臣で、ネロの心を意のままに操ることのできる数少ない人間の一人だった。
ペトロニウスは、一旦リギアを宮廷に入れ、皇帝ネロから下賜されるという形で彼女をウィニキウスの妾にするという策を考えた。だが、その策はリギアの自尊心を深く傷つけ、リギアはウィニキスの前から去ってしまった。
リギアは、当時のローマで密かに信者が増え始めていたキリスト教の熱心な信徒で、信徒たちの中に逃れていた。そこで、ウィニキウスは、リギアに会いたい、彼女に好かれたいという一身から、キリスト教徒たちに近づくようになり、やがて自分も次第にその教えに惹かれてキリスト教徒となる。
一方、皇帝ネロの異常さは日に日にその度合いを増しており、「自作の詩の中の火事の描写がうまくできない」という理由で実際の大火事を起こそうとローマに火をつけてしまった。ネロは、自分のことを心から敬うことなく、長年の繁栄の果てに次第に倦み爛れ腐敗しきったローマ市民が大嫌いだったのだ。だが、ローマ市民たちの怒りはネロの想像以上のもので、ネロは彼らに放火の下手人を示してその怒りの矛先をかわさなければならなくなってしまった。そして、そのスケープゴートにされたのが、初期キリスト教徒たちだった。ローマの放火はキリスト教徒たちによるものだとでっち上げられ、キリスト教徒たちは捕えられ虐殺されていった。捕えられたキリスト教徒たちの中にはリギアもいた。
ネロの傍若無人さ、狂気の振舞いは、人間性などまったく感じられないおぞましいものだった。あまりにも度を越した特権を持つことが、いかに危険なことか。それは、正常な判断力を失わせ、狂気に走らせるものなのだろうか。そして、そんなネロの周辺に位置する廷臣たちは、誰もがネロのご機嫌を損ねることを恐れ、ただただネロに媚びへつらっていた。そんな中で、ウィニキウスの叔父であるペトロニウスだけは、自分の思ったことをずばずばと言い、かえってその大胆な発言がネロに気に入られていた。
この物語の中で、ペトロニウスがネロの寵臣でありながらネロの言動よりも自分の自由の方を尊重する人物だったということは、重要なキーポイントとなっている。ペトロニウスは最後までキリスト教徒にはならなかったが、ウィニキウスにはあくまでも好意的で、彼の恋を後押しした。保身に汲々としているような人物ではなかったからこそ、ウィニキウスがここまで自由にキリスト教徒たちと係わり合い、遂にはリギアを救い出すことができたのだ。
ペトロニウスは最終的にはネロの不興を買うが、死刑を言い渡される前に自らの命を絶って、ネロに一矢報いる。死を逃れるために醜いまでの嘆願を繰り返す小心者たちの最後の足掻きを見る事を楽しみとしていたネロに対して、最後の最後まで、自由人であり続け、ネロの思いのままにはならなかった。
ポーランドにはローマ・カトリック教徒が圧倒的に多く、それが作者が初期キリスト教徒の殉教の物語を書こうとした動機の一つとなったという。 そのため、キリスト教徒たちの受難とその苦境にも屈することなく信仰を貫いた人々の敬虔な姿が、非常に印象的な場面や描写で描かれている。だが、キリスト教徒ではなくても、退廃的な生活を享受することにあくせくしているローマ市民たちの中にあって、少しでも自分らしく生きようとするペトロニウスのような魅力的な人物の姿は、活き活きとして印象的だ。動乱時代のポーランドに生きた作者は、ポーランドの人々がペトロニウスのような自由な精神の人間になることを心から望んでいたのだろう。
『クオ・ヴァディス』は、ローマの若き軍団将校ウィニキウスがキリスト教を信仰する女性を愛し、自らもその信仰に惹かれていくという話で、その背景として、暴君ネロの乱れきった政治、キリスト教徒に対する迫害などが描かれている。
ウィニキウスは、知人の館で見知った女性リギアに恋をし、何とか彼女を手に入れたいと叔父のペトロニウスに相談する。ペトロニウスは、気まぐれなネロの寵臣で、ネロの心を意のままに操ることのできる数少ない人間の一人だった。
ペトロニウスは、一旦リギアを宮廷に入れ、皇帝ネロから下賜されるという形で彼女をウィニキウスの妾にするという策を考えた。だが、その策はリギアの自尊心を深く傷つけ、リギアはウィニキスの前から去ってしまった。
リギアは、当時のローマで密かに信者が増え始めていたキリスト教の熱心な信徒で、信徒たちの中に逃れていた。そこで、ウィニキウスは、リギアに会いたい、彼女に好かれたいという一身から、キリスト教徒たちに近づくようになり、やがて自分も次第にその教えに惹かれてキリスト教徒となる。
一方、皇帝ネロの異常さは日に日にその度合いを増しており、「自作の詩の中の火事の描写がうまくできない」という理由で実際の大火事を起こそうとローマに火をつけてしまった。ネロは、自分のことを心から敬うことなく、長年の繁栄の果てに次第に倦み爛れ腐敗しきったローマ市民が大嫌いだったのだ。だが、ローマ市民たちの怒りはネロの想像以上のもので、ネロは彼らに放火の下手人を示してその怒りの矛先をかわさなければならなくなってしまった。そして、そのスケープゴートにされたのが、初期キリスト教徒たちだった。ローマの放火はキリスト教徒たちによるものだとでっち上げられ、キリスト教徒たちは捕えられ虐殺されていった。捕えられたキリスト教徒たちの中にはリギアもいた。
ネロの傍若無人さ、狂気の振舞いは、人間性などまったく感じられないおぞましいものだった。あまりにも度を越した特権を持つことが、いかに危険なことか。それは、正常な判断力を失わせ、狂気に走らせるものなのだろうか。そして、そんなネロの周辺に位置する廷臣たちは、誰もがネロのご機嫌を損ねることを恐れ、ただただネロに媚びへつらっていた。そんな中で、ウィニキウスの叔父であるペトロニウスだけは、自分の思ったことをずばずばと言い、かえってその大胆な発言がネロに気に入られていた。
この物語の中で、ペトロニウスがネロの寵臣でありながらネロの言動よりも自分の自由の方を尊重する人物だったということは、重要なキーポイントとなっている。ペトロニウスは最後までキリスト教徒にはならなかったが、ウィニキウスにはあくまでも好意的で、彼の恋を後押しした。保身に汲々としているような人物ではなかったからこそ、ウィニキウスがここまで自由にキリスト教徒たちと係わり合い、遂にはリギアを救い出すことができたのだ。
ペトロニウスは最終的にはネロの不興を買うが、死刑を言い渡される前に自らの命を絶って、ネロに一矢報いる。死を逃れるために醜いまでの嘆願を繰り返す小心者たちの最後の足掻きを見る事を楽しみとしていたネロに対して、最後の最後まで、自由人であり続け、ネロの思いのままにはならなかった。
ポーランドにはローマ・カトリック教徒が圧倒的に多く、それが作者が初期キリスト教徒の殉教の物語を書こうとした動機の一つとなったという。 そのため、キリスト教徒たちの受難とその苦境にも屈することなく信仰を貫いた人々の敬虔な姿が、非常に印象的な場面や描写で描かれている。だが、キリスト教徒ではなくても、退廃的な生活を享受することにあくせくしているローマ市民たちの中にあって、少しでも自分らしく生きようとするペトロニウスのような魅力的な人物の姿は、活き活きとして印象的だ。動乱時代のポーランドに生きた作者は、ポーランドの人々がペトロニウスのような自由な精神の人間になることを心から望んでいたのだろう。
お気に入り度:







掲載日:
外部ブログURLが設定されていません
投票する
投票するには、ログインしてください。
ホラー以外は、何でも読みます。みなさんの書評を読むのも楽しみです。
よろしくお願いします。
この書評へのコメント

コメントするには、ログインしてください。
書評一覧を取得中。。。
- 出版社:岩波書店
- ページ数:355
- ISBN:9784003277010
- 発売日:1995年03月01日
- 価格:735円
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。